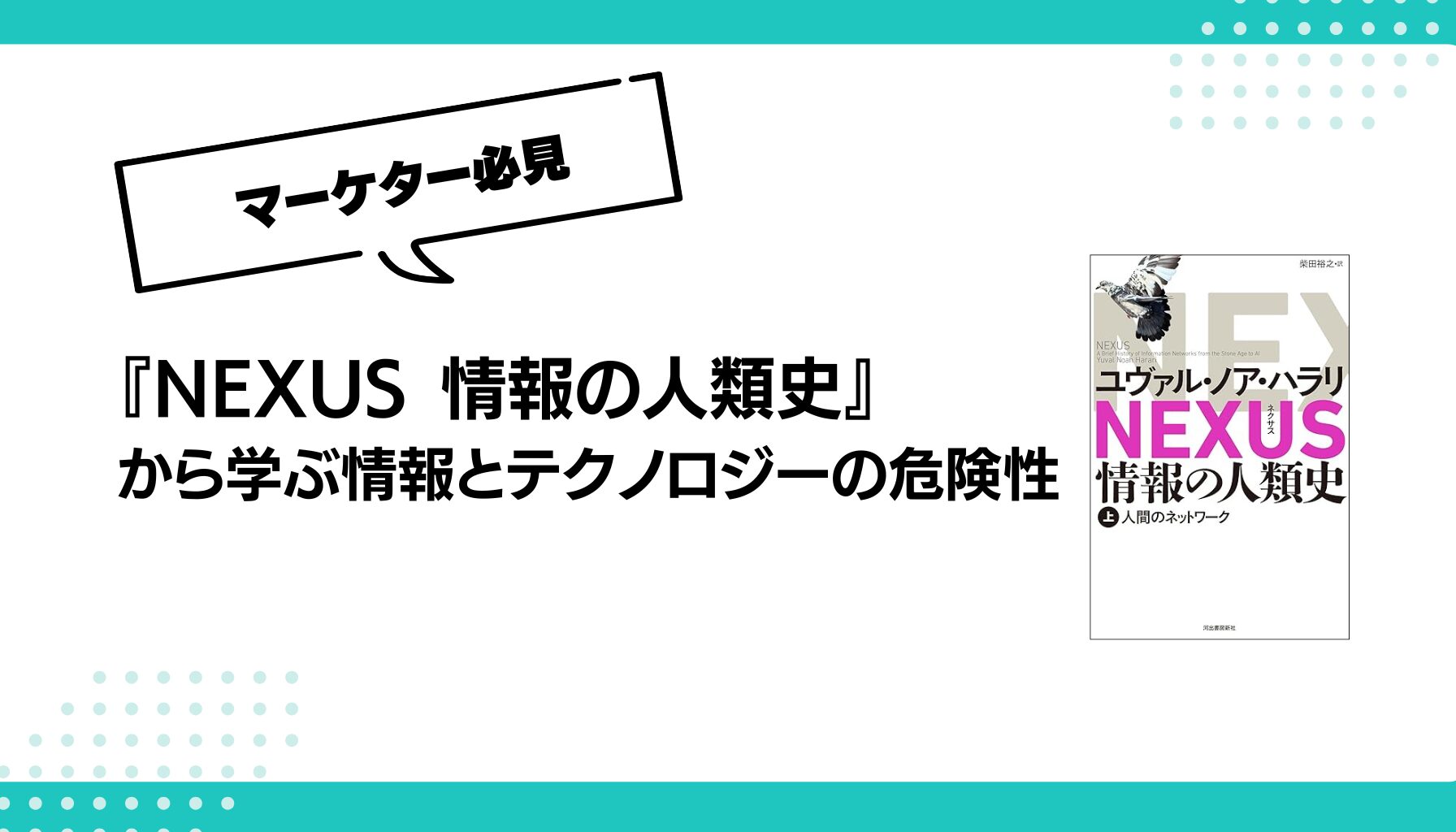はじめに
情報テクノロジーは私たちの生活を豊かにしてきました。スマートフォンで世界中の情報にアクセスでき、医療技術の進歩で平均寿命は延び、コミュニケーションはかつてないほど容易になりました。しかし、多くのマーケターやビジネスパーソンが感じているように「テクノロジーは常に善であり、情報が増えれば増えるほど良い」という単純な考え方には大きな盲点があります。
2025年5月時点で非常に話題であるユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』『ホモ・デウス』の著者)の新著『NEXUS 情報の人類史』では、「情報の素朴な見方」という考え方を批判し、情報とテクノロジーの複雑な性質を掘り下げています。本記事では、この著作のプロローグで紹介している内容をもとに、情報とテクノロジーに対する見方を再考し、AI時代の到来という大きな変化の中で、マーケターとして私たちが知っておくべき重要な洞察を紹介します。
本書の主要なテーマ
本書は、人間の情報ネットワークが歴史的にどのように発展してきたかを探究し、現在のAI革命がどのような変化をもたらすかを考察しています。
- 情報ネットワークの歴史と発展
- 古代から現代まで、人間が情報をどのように扱い、ネットワーク化してきたかを分析
- 神話、官僚制、宗教、科学などの情報システムの役割を探究
- 情報に対する誤った見方への警鐘
- 「情報の素朴な見方」:情報が多いほど真実に近づき、賢明になれるという考え
- 「情報の武器化」:情報は力を得るための武器にすぎないというポピュリスト的な見方
- どちらの極端な見方も不十分であると指摘
- AIという歴史的転換点
- AIが従来のツールと根本的に異なる「行為主体」である点を強調
- AIが自ら意思決定を行い、創造性を発揮できることの重大な意味
- 人間の決定をAIが代替していく過程で生じる社会的・政治的影響
- 未来の危険性と可能性
- 「シリコンのカーテン」:AI技術による世界の分断と対立
- AI支配:人間の理解や制御を超えたアルゴリズムによる社会管理
- これらの危険を回避し、AIの可能性を活かす方法の模索
本書の独自性
この本の独自性は、情報テクノロジーの問題を単なる技術的な観点からではなく、歴史的・哲学的な視点から分析している点にあります。ハラリは、現代のAI革命を理解するには過去の情報革命(文字の発明、印刷術、ラジオなど)と比較することが不可欠だと主張しています。
また、民主主義と全体主義という政治システムの違いを情報の流れという観点から分析し、AIがこれらの政治システムにどのような影響を与えるかを探っています。
簡潔に言えば、『NEXUS 情報の人類史』は、人類の過去・現在・未来を「情報」という視点から読み解き、AI時代を迎える私たちに警鐘を鳴らすとともに、より賢明な未来への道筋を探る本です。
情報の素朴な見方とその限界
情報の素朴な見方とは何か
ハラリによれば、「情報の素朴な見方」とは「情報は本質的に良いものであり、多ければ多いほど良い」という考え方です。この見方によれば、以下のような特徴があります:
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 情報と真実の関係 | 十分な情報があれば真実が明らかになる |
| 誤情報への対応 | さらに情報を集めれば誤情報は克服できる |
| 技術進歩の役割 | テクノロジーの進歩は必然的に社会を改善する |
| 価値判断の根拠 | 異なる価値観も、情報不足または偽情報が原因 |
| 長期的な結果 | 自由市場では真実がいずれ勝利する |
この見方は、IT業界やインターネット時代の半ば公式なイデオロギーとなっており、多くの政治家や起業家が支持してきました。
情報の素朴な見方の限界
しかし、ハラリはこの見方が現実の一部しか捉えていないと指摘します。確かに、医学的知識の増加により小児死亡率は大幅に減少しました。18世紀のドイツでは15歳まで生き延びる子供は約半数でしたが、2020年には世界全体で95.6%、ドイツでは99.5%にまで向上しています。
一方で、かつてない情報量とスピードで情報が行き交う現代社会では、以下のような逆説的な問題も生じています:
- 気候変動や生態系破壊が加速している
- 大量破壊兵器の開発と脅威が増している
- 国際的な緊張が高まり、協力がますます困難になっている
- 偽情報やポピュリズムの台頭により社会の分断が深まっている
AI革命:情報テクノロジーの最終段階?
AIの特異性:ツールから行為主体へ
ハラリは、AIが従来の技術と根本的に異なる点を強調しています。人類が発明してきたすべての技術(インターネットなど)はこれまで「ツール」でした。しかし、AIは単なるツールではなく「行為主体」であると紹介しています。
| 従来の技術 | AI |
|---|---|
| 使い方を人間が決定 | 自ら決定を下せる |
| 情報を処理する知能がない | 情報を分析し意思決定ができる |
| 新しいアイデアを生み出せない | 自ら創作・発見ができる |
| 人間の力を拡張する | 人間の判断に取って代わる |
AIはすでに住宅ローンの承認、採用、刑事裁判など、私たちの生活に関わる重要な決定に既に一部は関与しています。さらに、AIは音楽から医学まで、様々な分野で新しいアイデアを生み出しつつあります。将来的には、遺伝子コードを書き換えたり、新たな生命体を創造したりする可能性さえあります。
AIがもたらす脅威
ハラリは、AIがもたらす二つの主な脅威シナリオを指摘しています:
- シリコンのカーテン:かつての冷戦時代の「鉄のカーテン」のように、AIとコンピューターコードによって作られた「シリコンのカーテン」が世界を分断し、AI軍拡競争によって国際紛争が激化する可能性
- AI支配:人類全体がAIという新しい支配者から隔てられ、人知を超えたアルゴリズムの網に覆われ、生活を管理され、政治や文化を作り変えられる状況
これらの脅威は、ハリウッド映画のようなロボットの反乱ではなく、より微妙で根本的な変化を意味します。AI研究者2778人を対象とした2023年の調査では、回答者の3分の1以上が、高度なAIが人類の絶滅につながる可能性を少なくとも10%と見積もっています。
情報を武器化する:ポピュリズムの台頭
情報武器化の思想
情報テクノロジーの発展と並行して、情報そのものを武器と見なす考え方も広がっています。ハラリによれば、極端なポピュリズムは「客観的な真実などというものはまったく存在せず、誰もが『その人独自の真実』を持っている」と主張します。
この見方では:
- 力こそが唯一の現実
- 社会的関わりはすべて権力闘争
- 真実や正義に関心があると主張するのは、力を得るための策略
- 「事実」「真実」といった言葉の意味があいまいになる
このような考え方は右派のポピュリストだけでなく、左派の知識人やマルクス主義者の中にも見られます。両者は政策面では対立していても、社会や情報についての基本的な見方は驚くほど似ています。
ポピュリズムの矛盾
ポピュリズムには根本的な矛盾があります。エリートは皆、権力に対する渇望に駆り立てられていると警告しながら、最終的には「カリスマ的指導者」という単一の人物に全権力を委ねようとする点です。
ポピュリストたちはこの矛盾から抜け出すために、二つの方法を試みてきました:
- 過激な経験主義:「自分で調査し」、自分の目で直接確認できるものだけを信頼すべきだと主張
- 宗教的権威への回帰:神の啓示や神秘主義に立ち戻り、聖書やコーランなどの古代の聖典に絶対的真実を求める
どちらの方法も、現代の複雑な問題に対処するための大規模な協力や制度構築を困難にします。気候変動のような問題に対して、個人がすべての調査を行うことは不可能です。また、宗教的権威は、現代社会の複雑な課題に対して明確な解決策を提供できない場合が多いです。
マーケティングへの示唆:私たちは何をすべきか
この本を読むことで我々マーケターはどう行動を変化させてみるべきでしょうか。
1. 情報の素朴な見方を再考する
マーケターとして、「より多くのデータを収集すれば、より良い決定ができる」という前提を疑問視する必要があります。データ収集は重要ですが、それだけでは不十分です。
| 旧来の考え方 | 新しい考え方 |
|---|---|
| データ量が多いほど良い | データの質と解釈の仕方が重要 |
| アルゴリズムは客観的 | アルゴリズムにもバイアスがある |
| テクノロジーは常に進歩をもたらす | テクノロジーの影響は複雑で予測困難 |
| 情報は力である | 情報は力にも脆弱性にもなりうる |
2. AIを「行為主体」として扱う
マーケティングにおけるAIの活用を考える際は、AIを単なるツールではなく「決定を下す行為主体」として認識することが重要です。
- AIがマーケティング戦略や顧客体験に与える影響を批判的に評価する
- AIの推奨を盲目的に受け入れるのではなく、人間の判断の役割を明確にする
- AIシステムの「なぜ」そのような判断に至ったかを理解する努力をする
- AI活用の倫理的側面を常に考慮する
3. 人間同士のつながりと信頼を再構築する
情報が武器化され、真実が相対化される時代において、信頼構築はかつてないほど重要になっています。
- ステークホルダーとの透明で誠実なコミュニケーションを優先する
- 短期的な利益よりも長期的な信頼関係を重視する
- 情報源の多様性と信頼性を確保する
- 複雑な問題に対してシンプルすぎる「解決策」を疑う姿勢を持つ
4. 知恵を追求する
情報収集や技術的な力の追求だけでなく、その情報と力をどう使うかという「知恵」の側面にも注目すべきです。
- データだけでなく、その文脈や意味も考慮する
- テクノロジーの短期的効果だけでなく長期的影響も検討する
- 多様な視点からの批判的思考を奨励する
- 技術的可能性と倫理的妥当性のバランスを取る
まとめ
ハラリの『NEXUS 情報の人類史』から学べる重要なポイントは以下の通りです:
- 情報テクノロジーは単純に善でも悪でもなく、その影響は複雑で文脈依存的
- AIは従来の技術と根本的に異なり、「ツール」ではなく「行為主体」である
- 情報の素朴な見方と情報の武器化という両極端の間に、より微妙なバランスがある
- 情報ネットワークの歴史を理解することで、AIがもたらす変化をより深く理解できる
- マーケターとして、情報と技術に対する批判的思考と倫理的判断が不可欠
情報テクノロジー、特にAIの急速な進歩は、マーケティングの世界に革命的な変化をもたらしています。しかし、その変化に流されるのではなく、私たち人間が主体性を持ち、技術を賢く活用していくことが重要です。それには、情報と技術の本質を深く理解し、単純な見方を超えた、より洗練された視点を持つことが不可欠なのです。
本ブログはあくまでも本書のプロローグをもとに作成した内容になりますので、詳しく理解をしたい方はぜひ本を手に取ってみてください。