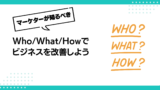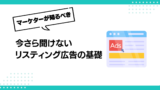はじめに
リスティング広告を運用していると、こんな悩みを抱えていませんか?
指名キーワードではコンバージョンが取れるけど、一般キーワードでは全然成果が出ない。一般キーワードの広告費用対効果が悪くて、予算を増やせない。潜在顧客にリーチしたいのに、CPAが高すぎて新規獲得が進まない。
この記事を読んでいるあなたは、おそらく指名キーワードでの獲得には成功していて、次のステップとして一般キーワードでの獲得を増やしたいと考えているマーケターではないでしょうか。実は、一般キーワードからコンバージョンを獲得するには、指名キーワードとはまったく異なるアプローチが必要なんです。
本記事では、リスティング広告で一般キーワードからコンバージョンを獲得するための具体的な戦略と実践方法を、マーケティング理論と実例を交えながら徹底解説します。単なるテクニック論ではなく、「なぜ一般キーワードでは成果が出にくいのか」という本質から理解することで、あなたの広告運用を劇的に改善できる内容になっています。
それでは、一般キーワード攻略の旅を始めましょう。
指名キーワードと一般キーワードの本質的な違い
まず最初に、指名キーワードと一般キーワードがどう違うのかを整理しておきましょう。この違いを理解することが、一般キーワード攻略の第一歩になります。
指名キーワードと一般キーワードでは、ユーザーの心理状態がまったく異なります。指名キーワードで検索するユーザーは、すでに自社を知っている、または具体的に探しているため、購買意欲は非常に高い状態です。認知段階でいえば、すでに認知済みで検討段階に入っています。競合状況も自社ブランドとの競合のみで、コンバージョン率は5から30パーセント程度と高く、CPAも低くなる傾向があります。情報収集の深さも浅く、決定に近い段階にいます。
一方、一般キーワードで検索するユーザーは、課題を解決したい、情報を探している段階です。購買意欲は低から中程度で、認知段階でいえば未認知から課題認識段階にいます。競合状況は多数の競合が存在し、コンバージョン率は0.5から3パーセント程度と低く、CPAは高くなります。情報収集の深さも深く、比較検討が必要な状態です。
例えば、会計ソフトを探している人を考えてみましょう。指名キーワードで「freee 料金」と検索している人は、すでに会計ソフトのfreeeを知っていて、料金を確認して契約するかどうか最終判断をしようとしています。この段階の人には、わかりやすい料金表と申し込みボタンを見せればコンバージョンしやすいですよね。
一方、一般キーワードで「クラウド会計ソフト おすすめ」と検索している人は、まだどの会計ソフトが自分に合っているのかわかっていません。freeeを知らないかもしれないし、知っていたとしても他の選択肢であるマネーフォワードや弥生などと比較検討している段階です。
この違いを理解せずに、指名キーワードと同じアプローチで一般キーワードに広告を出しても、うまくいかないのは当然なんです。
なぜ一般キーワードでコンバージョンが取りにくいのか
一般キーワードでコンバージョンが取りにくい理由は、主に3つあります。これらを理解することが、効果的な対策を立てるカギになります。
理由1:エボークトセット(検討セット)に入れていない
エボークトセットという言葉を聞いたことがありますか?これは、あるカテゴリーの商品を購入しようとしたときに、顧客の頭の中に浮かぶ「候補リスト」のことです。
例えば、ビールを買おうと思ったとき、あなたの頭の中には「アサヒ、キリン、サントリー」といったブランド名が浮かぶはずです。このリストに入っていないブランドは、そもそも選択肢として検討されません。
この図が示すように、カテゴリー全体の中から、まず名前を知っているブランドに絞られ、その中からさらに実際に検討するブランドが選ばれます。そして最終的に購入に至るのは、この検討セットに入ったブランドの中からなんです。
一般キーワードで検索しているユーザーは、まだあなたの会社がこのエボークトセットに入っていない可能性が高いんです。どんなに良い広告文を書いても、「そもそも候補として考えていない」段階では、コンバージョンに至りにくいのは当然ですよね。
理由2:Who/What/Howが明確になっていない
マーケティングの基本としてWho/What/Howという考え方があります。これは、誰のどんな課題を解決するのか(Who)、自社の商品・サービスを使うとどんな効果があるのか、なぜ競合ではなく自社が選ばれるのか(What)、どのように価値を届けるか(How)という3つを明確にするフレームワークです。
Whoの具体例としては「経理作業に時間を取られている小規模事業者」、Whatの具体例としては「経理作業時間を80%削減できる、簿記知識不要で使える」、Howの具体例としては「無料トライアルから始められる、サポートが手厚い」といった形で定義します。
一般キーワードで成果が出ないケースの多くは、このWho/What/Howが曖昧なまま広告を出してしまっているんです。
たとえば「会計ソフト」という一般キーワードで広告を出すとき、検索しているユーザーは多様です。個人事業主かもしれないし、中小企業の経理担当者かもしれない。それぞれが抱えている課題も、求めている解決策も違います。
ここで重要なのは、全員に刺さる広告文を作ろうとしないことです。むしろ、特定のWhoに対して明確なWhatを提示することで、その層からの高いコンバージョン率を実現できます。
理由3:プレファランス(好意度)を高められていない
プレファランスとは、消費者が特定のブランドや商品に対して持つ好意や選好のことです。簡単に言えば「このブランドが好き」「これを選びたい」という気持ちですね。
プレファランスを高めるには、3つの要素が重要だと言われています。まず、ブランド・エクイティ、つまり競合や代替品がある中で選ばれるための差別化要素です。一般キーワードでは、独自の強みを広告文とランディングページで明確に訴求する必要があります。次に、製品パフォーマンス、つまり製品の便益や機能的価値、情緒的価値です。具体的なベネフィットを数値で示すことが効果的です。最後に価格、つまりコストパフォーマンスの認識です。価格以上の価値があることを証明する必要があります。
一般キーワードで検索しているユーザーは、まだあなたの会社に対するプレファランスがゼロの状態です。この状態からプレファランスを高めて、「この会社の商品を試してみたい」と思ってもらう必要があります。
しかし多くの広告主は、このプレファランスを高める努力をせずに、いきなり「今すぐ申し込み」を求めてしまいます。これは、初対面の人にいきなりプロポーズするようなもの。うまくいくはずがありませんよね。
一般キーワードで成果を出すための5つの戦略
それでは、ここから具体的な戦略に入っていきましょう。一般キーワードでコンバージョンを獲得するためには、以下の5つの戦略が効果的です。
戦略1:Who/Whatを徹底的に明確化する
一般キーワード攻略の最初のステップは、誰のどんな課題を解決するのかを徹底的に明確にすることです。
まず、一般キーワードで検索する可能性のあるユーザーを複数のペルソナに分類しましょう。例えば「クラウド会計ソフト」というキーワードなら、個人事業主の田中さん(30代)、中小企業の経理担当・鈴木さん(40代)、スタートアップCFOの佐藤さん(20代)といった形でペルソナを設定できます。
個人事業主の田中さんは、確定申告が面倒で経理の知識がないという課題を抱えています。求めている解決策は、簡単に使えて確定申告を自動化できるツールです。検索しそうなキーワードは「確定申告 ソフト 簡単」や「個人事業主 会計ソフト おすすめ」といったものでしょう。
中小企業の経理担当・鈴木さんは、複数の帳簿管理が煩雑で人的ミスが多いという課題を抱えています。求めている解決策は、正確で効率的な帳簿管理ができ、複数人で使えるツールです。検索しそうなキーワードは「会計ソフト 法人 複数ユーザー」や「クラウド会計 比較」といったものでしょう。
スタートアップCFOの佐藤さんは、資金管理の見える化と投資家への報告という課題を抱えています。求めている解決策は、リアルタイムで財務状況を把握でき、レポート機能が充実したツールです。検索しそうなキーワードは「会計ソフト スタートアップ」や「資金繰り管理 ツール」といったものでしょう。
このように複数のペルソナを設定したら、それぞれに対して専用の広告グループを作りましょう。全員に向けた1つの広告よりも、特定の誰かに向けた広告の方が、圧倒的に成果が出やすくなります。
次に、各ペルソナに対して「自社の商品・サービスを使うとどんな効果があるのか」を明確にします。ここで重要なのは、機能ではなくベネフィットを伝えることです。
例えば「銀行口座と自動連携」という機能の説明ではなく、「入力作業を80%削減、本業に集中できる」というベネフィットを伝えます。「AIが仕訳を自動提案」という機能ではなく、「簿記の知識がなくても正確な帳簿が作れる」というベネフィットを伝えます。「クラウドで複数人利用可能」という機能ではなく、「どこからでもアクセス、チーム全員で最新情報を共有」というベネフィットを伝えるのです。
ベネフィットを伝えるときは、できるだけ具体的な数値を使いましょう。「経理作業を削減」よりも「経理作業時間を80%削減」の方が、効果がイメージしやすくなります。
戦略2:検索意図に合わせた広告文設計
一般キーワードの検索意図は多様です。その検索意図を正しく理解し、それに合わせた広告文を作ることが重要になります。
検索意図は大きく分けて4つのタイプがあります。まず情報収集型は、とにかく情報を集めたい段階です。「会計ソフト とは」や「クラウド会計 メリット」といったキーワードで検索します。この段階では、教育コンテンツへ誘導し、資料ダウンロードをコンバージョンポイントにするのが効果的です。
次に比較検討型は、複数の選択肢を比較したい段階です。「会計ソフト 比較」や「freee vs マネーフォワード」といったキーワードで検索します。この段階では、比較表を見せて、差別化ポイントを明確にすることが重要です。
解決策探索型は、具体的な課題の解決策を探している段階です。「確定申告 簡単にする方法」や「経理 効率化」といったキーワードで検索します。この段階では、課題解決のストーリーを語り、Before/Afterを見せることが効果的です。
購入直前型は、すぐに購入・申込みしたい段階です。「会計ソフト 無料トライアル」や「会計ソフト 価格」といったキーワードで検索します。この段階では、オファーを明確にし、申込みへの障壁を下げることが重要です。
それぞれの検索意図に合わせて、広告文の訴求ポイントを変える必要があります。
情報収集型の「会計ソフト とは」で検索した人向けの広告文なら、見出しは「初心者でもわかる!クラウド会計ソフトの選び方ガイド」、説明文は「会計ソフトの基本から選び方まで徹底解説。無料でダウンロードできる比較表付き」といった形になります。
比較検討型の「会計ソフト 比較」で検索した人向けなら、見出しは「主要3社を徹底比較!あなたに最適な会計ソフトはこれ」、説明文は「料金・機能・サポートを項目別に比較。導入実績No.1の〇〇なら初期費用0円」といった形です。
解決策探索型の「経理 効率化」で検索した人向けなら、見出しは「経理作業時間を80%削減した企業の事例を公開」、説明文は「月末の残業がゼロに。自動化で経理担当者の負担を大幅軽減。まずは無料で試せます」といった形です。
購入直前型の「会計ソフト 無料トライアル」で検索した人向けなら、見出しは「30日間無料トライアル実施中|登録3分で今すぐ始められる」、説明文は「クレジットカード登録不要。期間中いつでもキャンセル可能。導入サポート付き」といった形になります。
また、一般キーワードでは「8つの人間の欲望」を理解して広告文に取り入れると、より響きやすくなります。
人間には生存本能と生殖本能があり、そこから8つの欲望が生まれると言われています。「安らぐ」はストレスから解放されたい、安心したいという欲望で、広告文では「面倒な経理作業から解放」「ミスの心配なし」といった訴求に活用できます。「進める」は成長したい、前進したいという欲望で、「業務効率を次のレベルへ」「成長企業が選ぶ」といった訴求に使えます。「決する」は自分でコントロールしたい、自律したいという欲望で、「いつでもどこでも財務状況を把握」「自分のペースで」といった訴求が効果的です。
「有する」は所有したい、アクセスしたいという欲望で、「プレミアム機能が使い放題」「すべての機能にアクセス可能」といった訴求に使えます。「属する」は仲間に入りたい、つながりたいという欲望で、「10万社が導入」「業界トップ企業も利用」といった訴求が効果的です。「高める」は地位を上げたい、認められたいという欲望で、「プロフェッショナル向け」「一流企業の選択」といった訴求に活用できます。
「伝える」は自己表現したい、影響を与えたいという欲望で、「あなたのビジネスビジョンを数字で語る」といった訴求に使えます。「物語る」はストーリーの一部になりたいという欲望で、「成功企業のストーリーはここから始まった」といった訴求が効果的です。
自社の商品・サービスがどの欲望に訴求できるかを考えて、広告文に盛り込んでみましょう。
戦略3:エボークトセット(検討セット)に入るための差別化戦略
先ほど説明したように、一般キーワードで検索しているユーザーの頭の中には、まだあなたの会社が「候補リスト」に入っていない可能性が高いです。
エボークトセットに入るための最重要ポイントは、明確な差別化です。「他社と何が違うのか」を一瞬で理解してもらう必要があります。
差別化のアプローチは、大きく3つあります。まず機能的差別化は、他社にはない独自の機能や性能による差別化です。具体例としては「業界唯一のAI自動仕訳」「99.9%の高精度」といった訴求になります。
次に体験的差別化は、使いやすさやサポートの質による差別化です。具体例としては「初心者でも5分で使える」「24時間チャットサポート対応」といった訴求になります。
最後に感情的差別化は、ブランドイメージや共感による差別化です。具体例としては「スタートアップに寄り添う」「中小企業の味方」といった訴求になります。
ここで重要なのは、単に「機能が優れている」と言うだけでは不十分だということです。なぜその機能が重要なのかを、ターゲットの課題と結びつけて説明する必要があります。
弱い差別化の例は「当社の会計ソフトはAIを搭載しています」という表現です。これでは、なぜAIが重要なのか、ユーザーにどんなメリットがあるのかが伝わりません。
強い差別化の例は「簿記の知識がなくても大丈夫。AIが自動で仕訳を提案するので、経理初心者でも正確な帳簿が作れます。導入した企業の95%が『経理作業が楽になった』と回答」という表現です。これなら、AIという機能が、経理初心者の「簿記がわからない」という課題を解決し、「正確な帳簿が作れる」という結果につながることが明確に伝わります。
また、エボークトセットに入るためには、広告の見出し(ヘッドライン)で差別化ポイントを明確に伝えることが重要です。説明文まで読んでもらえる保証はないので、見出しだけで「ここが他と違う!」と伝わるようにしましょう。
戦略4:ランディングページでの信頼構築(E-E-A-T)
一般キーワードからの流入では、広告をクリックしてランディングページに来ても、まだコンバージョンには至りません。なぜなら、ユーザーはまだあなたの会社を信頼していないからです。
ここで重要になるのがE-E-A-Tという概念です。これはGoogleが検索品質を評価する際に使う基準ですが、ランディングページの信頼性を高めるためにも非常に役立ちます。
E-E-A-Tとは4つの要素の頭文字です。まずExperience(経験)は、実際の経験に基づいた情報という意味で、ランディングページでは導入事例、ビフォーアフター、実際の画面キャプチャなどで実装します。
Expertise(専門性)は、その分野の専門知識という意味で、専門家の監修、詳細な機能説明、業界用語の正確な使用などで実装します。
Authoritativeness(権威性)は、業界での認知度や評価という意味で、受賞歴、メディア掲載、導入社数、有名企業の導入実績などで実装します。
Trustworthiness(信頼性)は、情報の正確さと透明性という意味で、会社情報、セキュリティ対策、プライバシーポリシー、返金保証などで実装します。
ランディングページに入れるべき信頼要素としては、まず導入実績数です。「10,000社以上が導入」といった表示は、社会的証明による安心感を与え、ファーストビューに配置すべき高優先度の要素です。
顧客の声は、実際の利用者のレビューや評価を3から5件掲載することで、第三者からの推奨という効果があります。これもメインコンテンツ上部に配置すべき高優先度の要素です。
導入事例は、具体的な成果を数値で示すことで効果を証明します。1から2件をメインコンテンツ中部に配置すべき高優先度の要素です。
セキュリティ認証バッジは、ISO、プライバシーマークなどを表示することで安全性を保証します。フッターや申込みフォーム近くに配置する中優先度の要素です。
詳細な会社情報は、会社概要、代表メッセージ、オフィス写真などを掲載することで透明性を確保します。フッターに配置する中優先度の要素です。
メディア掲載実績は、テレビ、新聞、雑誌での紹介を表示することで権威性を補強します。サイドバーまたは専用セクションに配置する低優先度の要素です。
特に重要なのは導入事例(ケーススタディ)です。一般キーワードで流入してきたユーザーは「本当に効果があるのか?」を知りたがっています。
効果的な導入事例は、ストーリー形式で構成すると良いでしょう。
この流れで導入事例を構成することで、ユーザーは自分の状況に重ね合わせながら読み進めることができます。まず導入前の課題を提示し、共感を生み出します。次にどんな解決策を導入したかを説明し、理解を深めます。そして導入後の成果を具体的な数値で示し、効果を証明します。最後にお客様の生の声を添えることで、信頼性を確立するのです。
例えば、株式会社〇〇様(従業員15名)の導入事例であれば、次のように構成します。導入前の状況として、毎月20時間かかっていた経理作業で月末は終電帰りが当たり前だったという課題を提示します。解決策として当社のクラウド会計ソフトを導入したことを説明します。導入後の成果として、経理作業時間が月5時間に短縮され(75%削減)、月末の残業がゼロになったという結果を数値で示します。そして経理担当の佐藤さんからのコメントとして「以前は手作業で入力していた銀行取引がすべて自動化されて、本当に楽になりました。今では月末でも定時で帰れるようになり、ワークライフバランスが改善しました」という声を紹介するのです。
このように、課題から解決までの流れを具体的に示すことで、見込み客は「自分も同じような効果が得られるかもしれない」と感じることができるんです。特に重要なのは、できるだけ具体的な数値を使って説明することです。「経理作業が楽になった」よりも「経理作業時間を75%削減」の方が、効果がイメージしやすく、信頼性も高まります。
戦略5:段階的なコンバージョン設計
一般キーワードからの流入で最も重要なのは、いきなり本申込みを求めないことです。
検索意図のレベルに応じて、段階的なコンバージョンポイントを設定しましょう。これを「コンバージョンラダー(はしご)」と呼びます。
この図が示すように、ユーザーは認知段階から始まって、徐々に検討を深め、最終的に決定段階に至ります。はしごを一段一段登るように、ユーザーの関心度に応じて段階的にコミットメントを深めていくイメージです。
ユーザーの状態別:最適なコンバージョン設計
各段階に応じて、適切なコンバージョンポイントを用意することが重要です。以下の表で、ユーザーの心理状態とそれに合わせたコンバージョン設計を整理しました。
| ユーザーの心理状態 | 適切なCVポイント | CVハードル | 期待CVR | 設計のポイント |
|---|---|---|---|---|
| まだ課題を認識していない | お役立ちブログへの誘導 | 最低 | 30-50% | 何も入力不要、気軽に読める |
| 課題は認識しているが解決策を探している | チェックリスト、診断ツール | 低 | 5% | 名前とメアドのみ、簡単なアドバイス提供 |
| 解決策を比較検討している | 資料ダウンロード、比較表DL | 中 | 1-3% | メアド入力、役立つ情報を提供 |
| 具体的に検討している | 無料トライアル、デモ申込み | 中高 | 1-3% | 登録必要だが実際に試せる |
| 購入を決めかけている | 有料契約、購入 | 高 | 1-3% | すべての機能が使える |
この表を見ていただくとわかるように、ユーザーの関心度が低い段階ほど、ハードルを下げてコンバージョン率を高めることが重要です。そして、徐々に関心度を高めながら、最終的な有料契約へと導いていくのです。
なぜ段階的な設計が効果的なのか
この設計の良いところは、たとえ最終的な有料契約には至らなくても、リードとして獲得できることです。
例えば、資料をダウンロードしたユーザーには、後からメールでフォローアップできますよね。「資料はご覧いただけましたか?」「こんな事例もあります」「無料で試してみませんか?」といった形で、段階的に関係を深めていくことができます。
無料トライアルを始めたユーザーには、使い方のアドバイスや成功事例を送ることで、有料契約への転換率を高められます。「この機能を使うとさらに効率化できます」「同じ業種の〇〇社様はこんな使い方をしています」といった情報提供を通じて、製品の価値を実感してもらうのです。
コンバージョンハードルとベネフィットのバランス
段階的なコンバージョンを設定するときの重要なポイントは、CVハードルとベネフィットのバランスです。ユーザーが提供する情報(ハードル)と、あなたが提供する価値(ベネフィット)が釣り合っていることが重要なんです。
ハードルとベネフィットのバランス表
| CVハードル | ユーザーが提供するもの | あなたが提供する価値 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 何も不要 | 一般的な情報 | ブログ記事、FAQ |
| 低 | 名前とメールアドレスのみ | 簡単なアドバイス | 診断ツール、チェックリスト |
| 中 | メールアドレス、簡単な情報 | 役立つ情報、ノウハウ | 資料ダウンロード、比較表 |
| 中高 | 詳細な情報、登録が必要 | 期間限定ですべて使える、実際の効果を試せる | 30日間無料トライアル |
| 高 | クレジットカード情報、有料契約 | すべての機能、無制限利用、優先サポート | 有料プラン契約 |
たとえば、まだあなたの会社を知らない段階のユーザーに「無料トライアルに登録してください(会社情報やクレジットカード情報が必要)」と求めても、ハードルが高すぎてコンバージョンしません。信頼関係がまだ構築されていない段階で、個人情報や決済情報を求めるのは、相手に警戒心を抱かせてしまうのです。
実践例:段階的アプローチの具体的な流れ
それでは、具体的にどのような流れでユーザーをコンバージョンへ導くのか、会計ソフトの例で見てみましょう。
ステージ1:認知段階(初回接触)
ユーザーが「経理 効率化」というキーワードで検索し、あなたの広告をクリックしました。この段階では、まだあなたの会社のことを知りません。
ランディングページでは、いきなり「今すぐ申し込み」ではなく、「経理効率化のチェックリストを無料ダウンロード」というオファーを提示します。名前とメールアドレスだけで入手できるので、ユーザーは気軽にダウンロードしてくれます。ここでコンバージョン率は15パーセント程度を見込めます。
ステージ2:育成段階(メールフォロー)
チェックリストをダウンロードしたユーザーに、3日後にフォローメールを送ります。「チェックリストは活用いただけましたか?実は、このチェックリストの項目を自動化できるツールがあります」という形で、自社製品の存在を知ってもらいます。
さらに1週間後には、「同じような課題を抱えていた〇〇社様の事例」を送り、具体的な成果を示します。このメールには「詳細な資料をダウンロード」というリンクを設置します。ここでの資料ダウンロード率は20パーセント程度を見込めます。
ステージ3:検討段階(トライアル誘導)
資料をダウンロードしたユーザーに、さらに5日後に「30日間無料トライアル」のオファーをメールで送ります。ここまで来ると、ユーザーはすでにあなたの会社のことを知っていて、メールも複数回読んでいるので、信頼関係がある程度構築されています。
「実際に使ってみないとわからないですよね。30日間、すべての機能を無料でお試しいただけます。クレジットカードの登録は不要です」というメッセージで、トライアルのハードルを下げます。ここでのトライアル申込率は10パーセント程度を見込めます。
ステージ4:転換段階(有料契約へ)
無料トライアルを開始したユーザーには、使い方のサポートメールを定期的に送ります。「この機能は使いましたか?」「よくある質問をまとめました」といった形で、製品を使いこなせるように支援します。
トライアル期間の終了5日前には、「これまでの使用状況を見ると、すでに経理作業時間が20時間削減できています。このまま使い続けると、年間で240時間の削減になります」といった形で、具体的な効果を数値で示します。そして「今なら初月50%オフで有料プランに移行できます」というオファーを提示します。ここでの有料転換率は25パーセント程度を見込めます。
このように、段階的にアプローチすることで、最終的な有料契約数を大きく増やすことができるのです。
実践ステップ:明日から始められる改善プロセス
ここまで5つの戦略を説明してきましたが、「一体どこから手をつければいいの?」と思っているかもしれませんね。ここでは、明日から実践できる具体的なステップを紹介します。
ステップ1:現状分析(所要時間:1週間)
まずは、現在の一般キーワードの状況を正確に把握しましょう。闇雲に改善を始めるのではなく、現状を数値で理解することが成功への第一歩です。
現状分析で確認すべき5つの指標
| 分析項目 | 確認方法 | チェックポイント | 見るべき数値 |
|---|---|---|---|
| キーワード別CVR | Google広告の管理画面 | どのKWがCVRが高い/低いか | CVR、クリック数、CV数 |
| 検索意図の分類 | 実際に検索してみる | 情報収集/比較検討/解決策探索/購入直前型のどれか | 検索結果の傾向 |
| 競合の広告文 | 検索結果ページを確認 | どんな訴求をしているか、差別化ポイントは何か | 見出し、説明文の内容 |
| LPの離脱率 | Googleアナリティクス ヒートマップツール | どのセクションで離脱が多いか | セクション別離脱率 |
| CVまでの接触回数 | アトリビューション分析 | 一般KWからのユーザーは何回接触してCVしているか | 平均接触回数、期間 |
この分析で、「どの検索意図のキーワードでコンバージョン率が低いのか」「競合とどう差別化できていないのか」が見えてきます。特に重要なのは、一般キーワードと指名キーワードのコンバージョン率の差です。もし10倍以上の差があるなら、一般キーワードに大きな改善余地があるということです。
ステップ2:Who/Whatの言語化(所要時間:3日)
次に、ターゲットと価値提案を明確に言語化します。頭の中でなんとなく理解しているだけでは不十分です。言葉にして書き出すことで、チーム内での認識のズレもなくなります。
Who/Whatワークシートの使い方
このワークシートを使って、ターゲット顧客と提供価値を整理しましょう。重要なのは、できるだけ具体的に書くことです。「中小企業」ではなく「従業員10から50名の製造業」、「便利」ではなく「経理作業時間を月20時間から5時間に削減」といった形で、具体的に記述します。
まずWho(ターゲット顧客)のセクションでは、4つの項目を記入します。属性として年齢、性別、職業、企業規模などを記述します。抱えている課題として具体的な悩みや困りごとを記述します。現在の行動として課題を解決するために何をしているかを記述します。課題が解決されないとどうなるかとして、放置した場合の最悪のシナリオを記述します。
次にWhat(提供価値)のセクションでは、4つの項目を記入します。私たちの商品・サービスは何かとして一言で表現します。それによって何を解決するかとして、上記の課題に対する解決策を記述します。その結果顧客はどうなるか(ベネフィット)として、課題解決後の理想の状態を記述します。競合ではなく私たちが選ばれる理由(差別化ポイント)は何かとして、他社にない独自の強みを記述します。
このワークシートを、最低3つの異なるペルソナについて作成してください。そうすることで、どのペルソナが最も獲得しやすいか、どのメッセージが刺さりやすいかが見えてきます。3つのペルソナを比較して、最も市場規模が大きく、自社の強みが活かせるペルソナから攻略していくのが効率的です。
ステップ3:広告グループの再構築(所要時間:1週間)
現状の広告グループを、検索意図とペルソナで再構築しましょう。多くの広告主は、すべてのキーワードを一つの広告グループにまとめてしまっていますが、これでは各ユーザーに最適なメッセージを届けられません。
理想的な広告アカウント構造の例
キャンペーンレベルでは検索意図で分類し、広告グループレベルではペルソナで分類します。
まずキャンペーン「一般キーワード_情報収集型」を作成します。この下に広告グループ「個人事業主_確定申告の悩み」を作ります。キーワードとしては「確定申告 簡単」「個人事業主 会計ソフト」などを設定します。広告文では簿記知識不要を訴求し、ランディングページは資料ダウンロードへ誘導する専用ページを用意します。
同じキャンペーン内に広告グループ「中小企業_経理効率化」を作ります。キーワードとしては「経理 効率化」「会計業務 自動化」などを設定します。広告文では業務時間削減を訴求し、ランディングページは導入事例へ誘導する専用ページを用意します。
次にキャンペーン「一般キーワード_比較検討型」を作成します。この下に広告グループ「freee比較」を作ります。キーワードとしては「freee 競合」「freee vs」などを設定します。広告文ではfreeeとの差別化ポイントを訴求し、ランディングページは比較表ページへ誘導します。
この構造にすることで、各ペルソナ・各検索意図に最適化された広告文とランディングページを用意できます。最初は2から3つの広告グループから始めて、効果を見ながら徐々に増やしていくのがおすすめです。
ステップ4:ランディングページの信頼要素追加(所要時間:1週間)
既存のランディングページに、先ほど説明したE-E-A-Tの要素を追加していきましょう。一度にすべてを追加する必要はありません。優先順位をつけて、効果の高いものから実装していきます。
信頼要素追加の優先順位と実装方法
| 優先度 | 追加する要素 | 設置場所 | 実装のポイント | 期待される効果 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 導入社数 | ファーストビュー | 「10,000社以上が導入」など大きく表示 | 社会的証明、安心感 |
| 高 | 顧客の声(3-5件) | メインコンテンツ上部 | 顔写真、会社名、具体的な成果を記載 | 第三者からの推奨 |
| 高 | 導入事例(1-2件) | メインコンテンツ中部 | Before/After、数値での成果を明記 | 効果の証明 |
| 中 | セキュリティ認証バッジ | フッター、フォーム近く | ISO、プライバシーマークなどのロゴ | 安全性の保証 |
| 中 | 詳細な会社情報 | フッター | 会社概要、代表者、オフィス写真 | 透明性の確保 |
| 低 | メディア掲載実績 | サイドバー、専用セクション | ロゴを並べる、記事へのリンク | 権威性の補強 |
高優先度の要素は今週中に追加し、中優先度の要素は来週、低優先度の要素は余裕があればという形で進めましょう。特に導入事例は効果が大きいので、まだ用意していない場合は、既存顧客に連絡して事例インタビューをお願いすることをおすすめします。
ステップ5:A/Bテストと継続改善(継続的に実施)
最後に、仮説を立ててA/Bテストを実施し、継続的に改善していきます。改善は一度やって終わりではありません。市場環境やユーザーの傾向は常に変化するので、定期的なテストと改善が必要です。
A/Bテストの優先順位と実施方法
| 優先度 | テスト要素 | 期待される効果 | 実施方法 | テスト期間の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 広告文の見出し | CTRが20-50%変わる | Google広告の広告バリエーション機能 | 2週間 |
| 高 | CVポイントの種類 | CVRが2-3倍変わる | 資料DL vs トライアル申込み | 3-4週間 |
| 高 | LPのファーストビュー | 直帰率が10-30%変わる | Google Optimizeなど | 3-4週間 |
| 中 | 価格表示の方法 | CVRが10-20%変わる | 月額 vs 年額表示 | 2-3週間 |
| 低 | ボタンの色やデザイン | CVRが5-10%変わる | 定番だが効果は限定的 | 1-2週間 |
テストを実施する際の重要なルールがあります。それは、必ず1つずつ変更して効果を測定することです。複数の要素を同時に変更すると、何が効果的だったのかわからなくなってしまいます。
例えば、広告文の見出しを変更するのと同時にランディングページのファーストビューも変更してしまうと、コンバージョン率が上がったときに、どちらの変更が効いたのかわかりません。まずは広告文の見出しだけを変更してテストし、結果が出たら次にランディングページのテストをする、という形で順番に進めましょう。
また、テストは十分なデータが集まるまで継続することが重要です。クリック数が100未満では、統計的に有意な結果が出ません。最低でもクリック数が各バージョン100以上、理想的には300以上のデータを集めてから判断しましょう。
よくある失敗パターンと対策
最後に、一般キーワード運用でよくある失敗パターンと、その対策を紹介します。あなたも当てはまっていないか、チェックしてみてください。これらの失敗パターンを避けるだけで、コンバージョン率が大きく改善することも珍しくありません。
一般キーワード運用の8大失敗パターン
| 失敗パターン | なぜ起こるのか | どんな影響があるか | 今すぐできる対策 |
|---|---|---|---|
| 指名KWと同じLPに誘導 | 手間を省こうとして一つのLPで済ませている | CVRが1/3から1/5に低下 | 検索意図別に最低3つのLPを用意する |
| いきなり有料契約を求める | 段階的な設計の重要性を理解していない | CVRが1%以下に留まる | まず資料DLなど低いハードルのCVを設定 |
| 広告文が機能説明ばかり | ユーザー視点が欠けている | CTRが業界平均の半分以下 | すべての機能説明に「だから〇〇できる」を追加 |
| すべてのKWに同じ広告文 | セグメント化の重要性を理解していない | 特定のペルソナに刺さらない | ペルソナ別に広告グループを3つ作る |
| LPに導入事例がない | 信頼構築の重要性を理解していない | 離脱率が60%以上 | 最低1件の導入事例を追加する |
| 除外KWを設定していない | メンテナンスを怠っている | 無駄なクリック費用が30%以上 | 週1回、検索語句レポートを確認 |
| モバイル最適化されていない | PC画面しか確認していない | モバイルのCVRが極端に低い | スマホで実際に申込みまで試す |
| A/Bテストをしていない | 現状維持バイアスに陥っている | 改善機会を逃し続ける | 今月から月1回テストする習慣をつける |
特に最初の3つ、つまり「指名キーワードと同じランディングページに誘導している」「いきなり有料契約を求めている」「広告文が機能説明ばかり」は、多くの広告主が陥りがちな失敗です。もし当てはまっていたら、今週中に改善しましょう。これだけでコンバージョン率が2倍になることも珍しくありません。
失敗パターンの診断方法
自社の広告運用がこれらの失敗パターンに当てはまっているかどうか、簡単にチェックできる方法があります。
まず、一般キーワードと指名キーワードのコンバージョン率を比較してください。もし一般キーワードのコンバージョン率が指名キーワードの10分の1以下なら、上記の失敗パターンのいずれかに該当している可能性が高いです。
次に、広告文を見直してください。見出しに「誰のどんな課題を解決するか」が明確に書かれていますか?「〇〇な方におすすめ」という表現があるか、「〇〇を実現」というベネフィットが明記されているかをチェックしましょう。
そして、ランディングページを見直してください。ファーストビューから3スクロール以内に、導入事例や顧客の声が掲載されていますか?数値で示された具体的な成果がありますか?これらがなければ、すぐに追加しましょう。
まとめ:一般キーワード攻略のKey Takeaways
長い記事をここまで読んでいただき、ありがとうございました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。一般キーワードからコンバージョンを獲得するには、指名キーワードとはまったく異なるアプローチが必要です。
今日から実践すべき7つの重要ポイント
まず第一に、指名キーワードと一般キーワードは別物だと認識しましょう。顧客の心理状態がまったく違うので、同じアプローチでは失敗します。一般キーワードのユーザーは「まだあなたを知らない」「他の選択肢も検討している」という前提で、すべての施策を設計する必要があります。
第二に、Who/What/Howを徹底的に明確化しましょう。誰のどんな課題を、どう解決するのかを言語化することが出発点です。全員に刺さる広告を作ろうとせず、特定のペルソナに向けた専用の広告グループを作ることで、コンバージョン率が劇的に改善します。曖昧なターゲット設定は、結局誰にも刺さらない広告を生み出してしまうのです。
第三に、検索意図に合わせて広告文とランディングページを最適化しましょう。情報収集型、比較検討型、解決策探索型、購入直前型の4つの検索意図を理解し、それぞれに適したメッセージとコンバージョンポイントを用意することが重要です。同じ商品でも、検索意図によって訴求すべきポイントは変わります。
第四に、エボークトセット(検討リスト)に入るための差別化を明確にしましょう。「他社と何が違うのか」を一瞬で理解してもらう必要があります。機能ではなくベネフィットで差別化し、なぜそれが重要なのかをターゲットの課題と結びつけて説明することで、検討候補に入ることができます。
第五に、E-E-A-Tでランディングページの信頼性を高めましょう。一般キーワードからの流入では、まだ信頼がゼロの状態です。導入事例、顧客の声、実績数値などを使って、「この会社なら信頼できる」と思ってもらうことが、コンバージョンへの重要なステップになります。
第六に、段階的なコンバージョン設計でリード獲得を最大化しましょう。いきなり有料契約を求めず、資料ダウンロード、無料トライアル、有料契約というステップを踏むことで、より多くのユーザーを獲得できます。各段階で適切な価値を提供しながら、信頼関係を構築していくことが成功の鍵です。
第七に、継続的なA/Bテストで改善し続けましょう。一度設定して終わりではありません。広告文、コンバージョンポイント、ランディングページの要素を定期的にテストして、常に改善を続けることが、長期的な成果につながります。市場環境もユーザーの傾向も常に変化するので、それに合わせて最適化し続けることが重要です。
最後に:ユーザーの立場に立って考える
一般キーワードからのコンバージョン獲得は、確かに指名キーワードよりも難易度が高いです。しかし、ここで説明した戦略を実践すれば、必ず成果は出ます。
大切なのは、ユーザーの立場に立って考えることです。もしあなたが初めて会計ソフトを探していたら、どんな情報が欲しいですか?どんな不安を感じますか?どんな証拠があれば信頼できますか?その答えが、あなたの広告とランディングページに必要な要素です。
今日から、一つずつ実践してみてください。最初は小さな改善からで構いません。Who/Whatを明確にする、広告文を検索意図別に分ける、ランディングページに導入事例を1つ追加する。そういった小さな改善の積み重ねが、3ヶ月後、半年後には大きな成果の差となって現れます。
特に重要なのは、完璧を目指さないことです。まずは70点の施策を実装して、データを見ながら改善していく方が、100点を目指して何もしないよりもはるかに良い結果を生みます。今週中に一つ、来週中にもう一つと、着実に改善を積み重ねていきましょう。
あなたのリスティング広告運用が、より効果的になることを願っています。一般キーワードからのコンバージョン獲得という難しい課題に挑戦するあなたを、心から応援しています。頑張ってください!