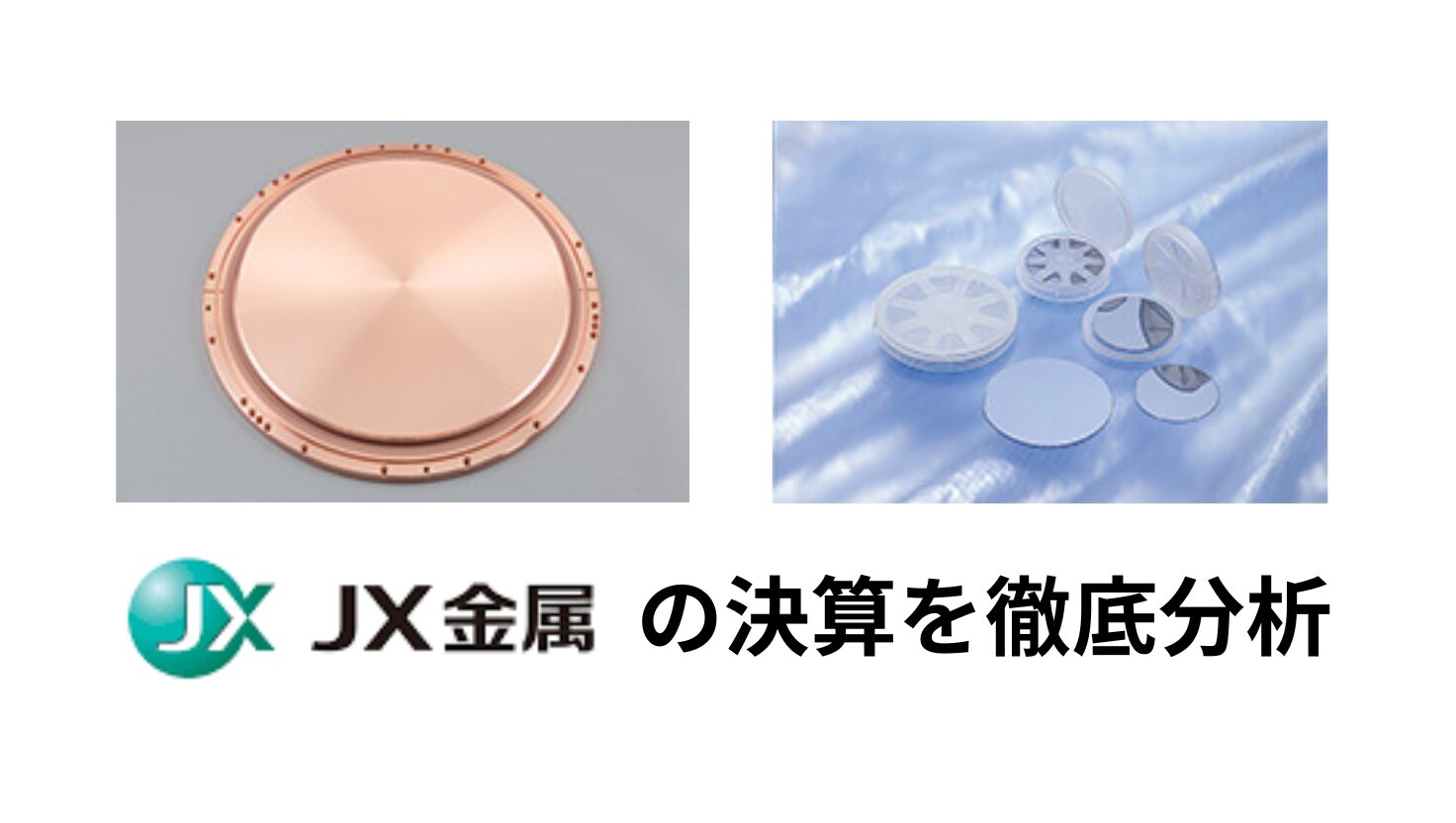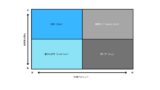はじめに──マーケターが決算資料から学ぶべき理由
最近、あなたの担当する商品やサービスは、どんな市場環境の変化に直面していますか? テクノロジーの進化、顧客ニーズの変化、競合の動向──マーケターとして日々考えるべきことは山積みですよね。
今回取り上げるのは、半導体材料や情報通信材料を手掛けるJX金属株式会社の決算資料です。「製造業の決算なんて、マーケティングと関係あるの?」と思うかもしれませんが、実はこの企業の決算には、マーケターが学ぶべき戦略のヒントが詰まっています。
特に注目すべきは、2024年度にフォーカス事業の営業利益が前年比90%増という驚異的な成長を遂げた点です。しかも2025年度第1四半期も前年同期比22%増と好調を維持し、通期見通しを150億円も上方修正しています。
なぜこのような成果が出たのか? それは、単に「運が良かった」わけではありません。市場の変化を先読みし、顧客ニーズに応える製品開発と販売戦略を実行した結果なのです。
この記事では、JX金属の決算内容を丁寧に紐解きながら、マーケターが自分の業務に活かせる「戦略」「勝因」「施策」を抽出していきます。
JX金属とはどんな企業か?──事業構造と市場ポジション
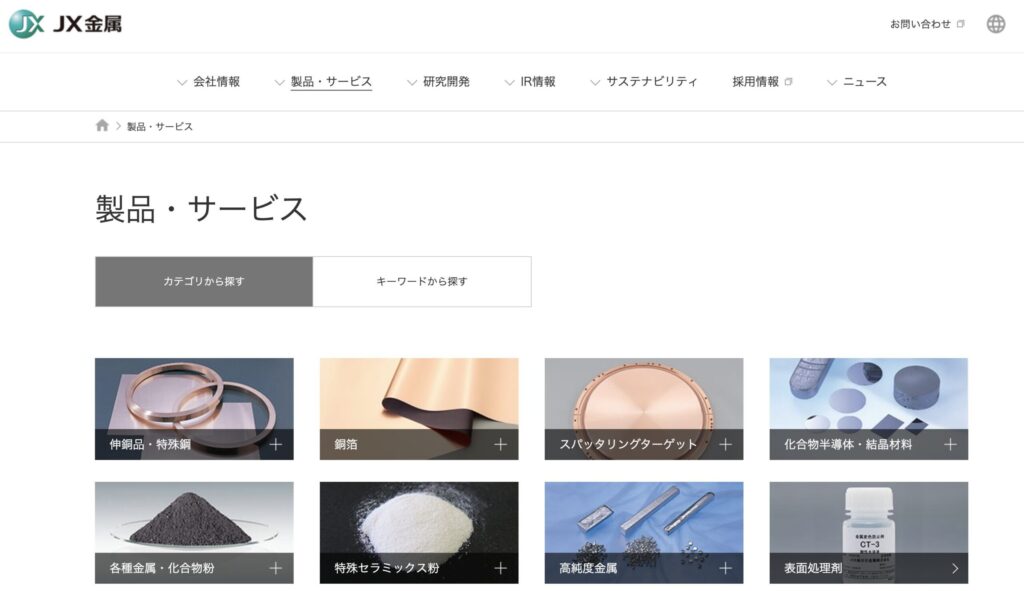
まず、JX金属という会社がどんなビジネスをしているのか、基本情報を押さえておきましょう。
JX金属は、半導体や情報通信機器に使われる「先端素材」を製造・販売するグローバル企業です。具体的には、半導体ウエハに薄膜を形成するための「半導体用ターゲット」や、スマートフォンなどに使われる「圧延銅箔」といった製品で、世界トップクラスのシェアを誇っています。
同社の事業は大きく2つに分かれています。
| 事業区分 | 主な内容 | 戦略的位置づけ |
|---|---|---|
| フォーカス事業 | 半導体材料、情報通信材料 | 高度な技術的差別化でグローバル競争優位性を持つ成長戦略のコア事業 |
| ベース事業 | 基礎材料(銅、レアメタル) | サプライチェーン強化を通じてフォーカス事業の成長を支える |

フォーカス事業には、以下のような主力製品があります。これらは全て、私たちが日常的に使っているデジタルデバイスに欠かせない素材です。
主な製品とグローバルシェア
| 製品名 | 用途 | グローバルシェア | 最終製品例 |
|---|---|---|---|
| 半導体用ターゲット | 半導体ウエハに薄膜を形成するための金属材料 | 64% (業界1位) | AIサーバ、スマートフォン、PC |
| 圧延銅箔 | フレキシブルプリント基板(FPC)に使われる屈曲性に優れた金属箔 | 78% (業界1位) | スマートフォン、ウェアラブル端末 |
| 磁性材用ターゲット | ハードディスクドライブに薄膜を形成するための金属材料 | 高シェア | データセンター向けHDD |
| InP基板 | 光通信用の受発光素子材料 | 約60% | データセンター、通信インフラ |
| チタン銅 | コネクタ等に使用される強度・導電性・曲げ加工性に優れた合金材料 | 約50% | AIサーバ、データセンター |
このように、JX金属は「ニッチだけど絶対に必要」な素材で圧倒的なシェアを持っている企業なのです。マーケティング的に言えば、技術的な参入障壁が高く、競合が少ない領域で強固なポジションを築いているということになります。
2024年度決算ハイライト──なぜ営業利益が90%も増えたのか?
それでは、2024年度(2025年3月期)の通期決算を見ていきましょう。
2024年度(2025年3月期)通期実績
| 指標 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,149億円 | ▲53% |
| ├ フォーカス事業 | 4,131億円 | +33% |
| ├ ベース事業 | 3,065億円 | ▲75% |
| 営業利益 | 1,125億円 | +31% |
| ├ フォーカス事業 | 518億円 | +90% |
| └ ベース事業 | 745億円 | ▲3% |
一見すると、売上高が前年比▲53%と大きく減少しているので、「業績が悪化したのでは?」と思うかもしれません。しかし営業利益は+31%と増えています。これはいったいどういうことでしょうか?
実は、売上高の減少は意図的な事業ポートフォリオの再構築によるものです。JX金属は、収益性が低く成長性も期待できない事業を切り離し、成長が見込める「フォーカス事業」に経営資源を集中させる戦略を進めています。
具体的には、ベース事業の一部である金属製錬の原料・販売子会社や銅鉱山会社を非連結化(売却)することで、構造的に売上高が縮小したのです。その結果、売上高は減ったものの、利益率の高いフォーカス事業の比率が高まり、全体の収益性が向上したというわけです。
マーケティング的に言えば、これは「選択と集中」の典型例です。全ての顧客セグメントに対応しようとするのではなく、自社が最も強みを発揮できる領域にリソースを集中させることで、より高い利益を生み出すことができるのです。
勝因その1:AI関連需要を的確に捉えた製品ポートフォリオ
それでは、フォーカス事業の営業利益が前年比90%増という驚異的な成長を遂げた理由を深掘りしていきましょう。
最大の勝因は、AI関連需要の拡大を的確に捉えたことにあります。
2023年後半からChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し、それに伴ってAI処理を行うサーバの需要が爆発的に増加しました。AI処理には膨大な計算能力が必要なため、最先端の半導体チップが大量に使われるようになったのです。
JX金属の主力製品である「半導体用ターゲット」は、まさにこの半導体チップを製造する際に使われる材料です。決算資料によれば、「薄膜材料事業はAI関連需要の拡大を受け、主力製品の増販により増益」と明記されています。
また、AI処理を行うサーバには高性能なメモリやストレージも必要になります。ここでも、JX金属の「磁性材用ターゲット」がデータセンター向けハードディスクドライブ(HDD)の需要増加により好調に推移しています。
さらに、AIサーバ内部の配線や接続部品には、信号の劣化を防ぐ高品質な素材が求められます。ここで活躍するのが「チタン銅」や「圧延銅箔」といった情報通信材料です。決算資料でも、「機能材料事業において、AIサーバ用途での採用拡大に伴う増販」が業績好調の要因として挙げられています。
このように、JX金属の製品ポートフォリオは、AI時代に求められる素材を幅広くカバーしていたため、需要の波に乗ることができたのです。
マーケターが学ぶべきポイント:
これは「市場のメガトレンドを捉える」ことの重要性を示しています。JX金属は、AIという大きなトレンドが来ることを予測し、それに必要な製品を事前に開発・供給体制を整えていました。マーケターとしても、自社の製品やサービスが「今後どんな市場の変化に対応できるか」を常に考え、先手を打っておくことが大切です。
勝因その2:圧倒的なグローバルシェアによる「選ばれる理由」の確立
JX金属のもう一つの強みは、主力製品で圧倒的なグローバルシェアを持っていることです。
先ほどの表でも示しましたが、半導体用ターゲットで64%、圧延銅箔で78%というシェアは、業界内で圧倒的な存在感を示しています。このシェアの高さは、単に「たくさん売れている」という以上の意味を持ちます。
なぜなら、半導体や電子機器の製造においては、材料の品質が最終製品の性能を大きく左右するからです。そのため、顧客企業(半導体メーカーやスマートフォンメーカー)は、実績があり信頼できるサプライヤーを選ぶ傾向が強いのです。
JX金属は長年にわたって高品質な製品を安定供給してきた実績があるため、顧客から「この材料ならJX金属」という信頼を得ています。これが高シェアの維持につながり、さらに新規顧客の獲得にもつながるという好循環が生まれているのです。
また、決算資料には「高度な技術的差別化の実現により、グローバル競争優位性を持つ」と明記されています。つまり、単に安く作るのではなく、他社には真似できない技術力で差別化しているということです。
マーケターが学ぶべきポイント:
これは「ブランド力」と「技術力」の重要性を示しています。価格競争に巻き込まれず、「この分野ならあの会社」と顧客に思ってもらえるポジションを確立することが、長期的な競争優位性につながります。マーケティング活動においても、自社の強みを明確に打ち出し、顧客に「選ばれる理由」を提供することが重要です。
勝因その3:事業ポートフォリオの最適化と「選択と集中」の徹底
JX金属の戦略で特に注目すべきは、事業ポートフォリオの大胆な見直しです。
決算資料によれば、JX金属は2022年度から2024年度にかけて、以下のような資産売却とサプライチェーン強化を進めてきました。
ベース事業におけるこれまでの主な取り組み
| 時期 | 取り組み内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 韓国の銅製錬JV LS-Nikko全持分売却 | 事業規模の適正化 |
| 2023年度 | カセロネス銅鉱山権益の一部売却 | 事業規模の適正化 |
| 2023年度 | Mibra鉱山(タンタル)投資 | サプライチェーン強化 |
| 2023年度 | eCycleの株式取得(双日との協業) | サプライチェーン強化 |
| 2024年度 | ロス・ペランブレス銅鉱山権益の一部売却 | 事業規模の適正化 |
| 2024年度 | Copi PJ(レアメタル・レアアース)参入 | サプライチェーン強化 |
| 2024年度 | 製錬・リサイクル事業の高付加価値化(三菱商事との協業) | 高付加価値化 |
| 2025年度 | 金属リサイクル事業 生産規模縮小の検討を開始 | 製錬事業強靭化の加速 |
この一連の動きから見えてくるのは、「収益性の低い事業から撤退し、成長が見込める事業に集中する」という明確な方針です。
特に注目すべきは、2025年6月に発表された「金属リサイクル事業の生産規模縮小の検討開始」です。決算資料には、その背景として「鉱石TC/RCの急速かつ極度の悪化」が挙げられています。
TC/RCとは、銅鉱石を製錬する際に受け取る製錬委託料のことです。近年、中国を中心に製錬所の生産能力が急激に増強された結果、製錬委託料が大幅に下落し、従来型の精鉱製錬の収益性が著しく低下してしまいました。2025年第1四半期のスポット価格はマイナス水準にまで落ち込んでいるとのことです。
そこでJX金属は、生産規模を縮小しつつ、収益性の高いリサイクル原料の比率を高めるという戦略に舵を切りました。これにより、投資規模を抑えつつ、利益率を向上させることができるのです。
マーケターが学ぶべきポイント:
これは「撤退の勇気」と「リソース配分の最適化」の重要性を示しています。全ての事業を同じように伸ばそうとするのではなく、市場環境が悪化した領域からは勇気を持って撤退し、成長が見込める領域に集中投資することが、結果的に企業全体の収益性向上につながります。
マーケティング活動においても、全ての顧客セグメントや販売チャネルに同じだけのリソースを投下するのではなく、ROI(投資対効果)の高い領域に集中することが重要です。
勝因その4:設備投資による供給能力の強化と需要の先取り
JX金属のもう一つの成功要因は、成長が見込める製品に対して積極的に設備投資を行ってきたことです。
決算資料によれば、2024年度の投融資額は923億円に達しており、「ひたちなかにおける半導体用ターゲット増産対応投資等を中心に、予定どおり実行中」とのことです。
また、2025年には以下のような追加投資も発表されています。
主な設備投資・増産対応
| 発表時期 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 2025年5月 | ひたちなか新工場(仮称)に隣接する工業用地の新規取得を決定 | 半導体用ターゲットの更なる増産対応 |
| 2025年6月 | CVD/ALD材料のフル稼働開始 | 次世代半導体の高性能化に対応 |
| 2025年7月 | InP基板の設備増強投資を決定(生産能力を現行から約2割アップ) | 光通信・データセンター需要への対応 |
これらの投資は、AI関連需要の拡大を見越して行われたものです。つまり、需要が顕在化する前に供給体制を整えておくことで、競合他社に先んじて市場シェアを獲得できたのです。
実際、2025年度第1四半期の販売数量増減率を見ると、主力製品が軒並み大きく伸びています。
| 製品名 | 販売数量増減率(前年同期比) |
|---|---|
| 半導体用ターゲット | +14% |
| 磁性材用ターゲット | +41% |
| InP基板 | +50% |
| 圧延銅箔 | +18% |
| チタン銅 | +37% |
特に、InP基板の+50%、磁性材用ターゲットの+41%という伸び率は驚異的です。これは、設備投資により供給能力を高めていたからこそ実現できた数字です。
マーケターが学ぶべきポイント:
これは「需要を先読みした供給体制の構築」の重要性を示しています。需要が顕在化してから対応していては、競合他社に市場を奪われてしまいます。市場のトレンドを読み、顧客が「これから必要とするもの」を予測し、事前に準備しておくことが、マーケティングの成功につながります。
また、単に製品を用意するだけでなく、「十分な量を供給できる体制」を整えておくことも重要です。せっかく需要があっても、供給が追いつかなければビジネスチャンスを逃してしまいます。
直近四半期(2025年度Q1)のハイライトと通期見通しの上方修正
それでは、最新の2025年度第1四半期(2025年4月〜6月)の実績を見てみましょう。
2025年度第1四半期実績
| 指標 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 営業利益 | 296億円 | +53億円(+22%) |
| ├ フォーカス事業 | 162億円 | +36億円(+29%) |
| └ ベース事業 | 146億円 | ▲23億円(▲14%) |
フォーカス事業が前年同期比+29%と好調を維持している一方、ベース事業は前年の一過性利益の反転や為替の影響で若干減益となっています。
この好調な第1四半期実績を受けて、JX金属は2025年度通期の業績見通しを大幅に上方修正しました。
2025年度通期見通し(8月上方修正)
| 指標 | 5月公表 | 8月公表 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 営業利益 | 950億円 | 1,100億円 | +150億円(+16%) |
| ├ フォーカス事業 | 520億円 | 590億円 | +70億円 |
| └ ベース事業 | 540億円 | 610億円 | +70億円 |
| 配当 | 15円/株 | 18円/株 | +3円 |
上方修正の主な理由は以下の3点です。
- フォーカス事業主力製品の増販: AI関連需要が想定以上に好調
- 米国関税影響の縮小織り込み: 当初懸念されていた関税の影響が想定より小さかった
- 銅価前提の更新: 銅価格が想定より高水準で推移
特に注目すべきは、配当を15円から18円に増配したことです。これは、単に業績が良いからというだけでなく、「今後も成長が見込める」という経営陣の自信の表れと言えるでしょう。
マーケターが学ぶべきポイント:
これは「市場環境の変化に柔軟に対応する」ことの重要性を示しています。当初の計画通りに進めるだけでなく、市場の動きを見ながら戦略を修正していくことが、ビジネスの成功につながります。
マーケティングにおいても、年初に立てた計画に固執するのではなく、市場の反応を見ながら予算配分や施策を柔軟に調整していくことが重要です。
JX金属の戦略から学ぶ、BtoBマーケティングの成功法則
ここまで見てきたJX金属の事例から、BtoB企業のマーケティングにおいて重要なポイントをまとめてみましょう。
成功法則1:メガトレンドを捉え、顧客が「次に必要とするもの」を先回りして提供する
JX金属はAIという大きな市場トレンドを捉え、それに必要な素材を事前に準備していました。BtoBマーケティングにおいては、目の前の顧客ニーズに応えるだけでなく、顧客業界全体のトレンドを把握し、「これから必要になるもの」を提案していくことが重要です。
成功法則2:技術的差別化により、価格競争に巻き込まれないポジションを確立する
JX金属は圧倒的な技術力により、競合他社が簡単には真似できない製品を提供しています。BtoBマーケティングでは、「安さ」で勝負するのではなく、「品質」「技術力」「信頼性」といった付加価値で差別化することが、長期的な競争優位性につながります。
成功法則3:選択と集中により、強みを活かせる領域にリソースを集中させる
JX金属は収益性の低い事業から撤退し、成長が見込める事業に経営資源を集中させています。BtoBマーケティングにおいても、全ての顧客セグメントやチャネルに同じだけのリソースを投下するのではなく、ROIの高い領域に集中することが重要です。
成功法則4:需要を先読みした供給体制の構築により、市場機会を最大化する
JX金属は需要が顕在化する前に設備投資を行い、供給能力を高めていました。BtoBマーケティングでは、「需要を作る」だけでなく、「需要に応えられる体制」を整えておくことも重要です。せっかくマーケティング活動で需要を喚起しても、供給が追いつかなければビジネスチャンスを逃してしまいます。
成功法則5:市場環境の変化に柔軟に対応し、戦略を修正していく
JX金属は四半期ごとに実績を見ながら、通期見通しを修正しています。BtoBマーケティングにおいても、計画に固執するのではなく、市場の反応を見ながら柔軟に戦略を調整していくことが成功につながります。
まとめ──JX金属の決算から学ぶマーケティング戦略のkey takeaways
最後に、今回の決算分析から得られたマーケティング戦略のヒントを箇条書きでまとめます。
今回の決算から得られるマーケティング戦略のヒント
| ポイント | 具体的な学び |
|---|---|
| メガトレンドの把握 | AI関連需要という大きな市場変化を捉え、それに対応する製品ポートフォリオを事前に準備していたことが成長の鍵となった |
| 技術的差別化 | 半導体用ターゲット64%、圧延銅箔78%という圧倒的なグローバルシェアを持つことで、顧客から「選ばれる理由」を確立している |
| 事業ポートフォリオの最適化 | 収益性の低い事業から撤退し、成長が見込める領域に経営資源を集中させることで、全体の収益性を向上させている |
| 先行投資による供給能力強化 | 需要が顕在化する前に設備投資を行い、競合他社に先んじて市場シェアを獲得している |
| 柔軟な戦略修正 | 四半期ごとに実績を評価し、市場環境の変化に応じて通期見通しを修正することで、機会を最大化している |
| 顧客との長期的信頼関係 | 高品質な製品を安定供給し続けることで、顧客からの信頼を獲得し、それが高シェアの維持につながっている |
| 複数製品による相乗効果 | AIサーバに必要な複数の素材(半導体用ターゲット、チタン銅、圧延銅箔等)を提供することで、一つのトレンドから複数の収益機会を得ている |
JX金属の決算資料から読み取れるのは、「単に良い製品を作る」だけでなく、「市場のトレンドを先読みし、顧客が必要とするものを適切なタイミングで提供する」というマーケティング戦略の重要性です。
また、全ての事業に同じだけのリソースを投下するのではなく、成長が見込める領域に集中投資することで、限られた経営資源を最大限に活用しています。
これらの戦略は、BtoB企業だけでなく、あらゆるビジネスにおいて応用可能な普遍的な原則です。ぜひ、あなた自身のマーケティング活動にも活かしてみてください。
参考資料