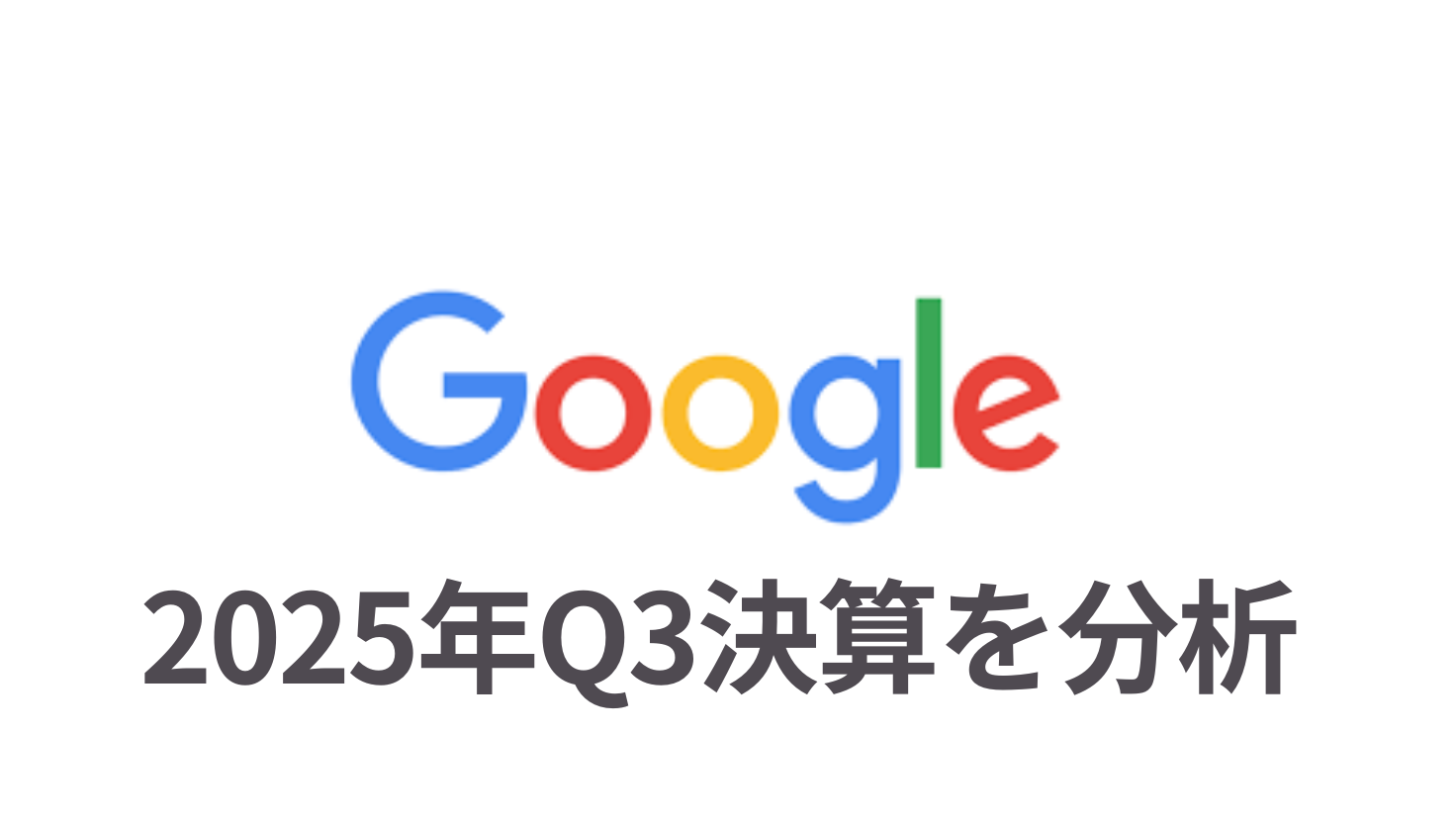はじめに:なぜ今、Googleの決算を読むべきなのか
皆さんは「競合他社の決算書なんて、数字ばかりで自分には関係ない」と思っていませんか?実は、決算資料にはマーケターが明日から使える「売れる仕組み」のヒントが山ほど詰まっているんです。
特にGoogle(Alphabet社)のような巨大プラットフォーマーの決算には、商品がなぜ売れるのか、どうやって顧客を獲得し続けるのか、そしてどこに投資すべきかという戦略が凝縮されています。2025年第3四半期(7-9月期)の決算を見ると、前年同期比で売上が16%増加し、1,023億ドル(約15兆円)という驚異的な数字を記録しました。この売上規模で16%増加は信じられない成長です。この成長の背景には、単なる広告収入の増加だけでなく、明確な戦略転換と市場への対応がありました。
この記事では、数字の羅列ではなく「なぜこの結果になったのか」「どんなマーケティング戦略があったのか」という視点で、Alphabetの決算を読み解いていきます。あなたが担当している商品やサービスにも応用できる実践的なヒントを見つけてください。
企業概要:Alphabetって何をしている会社?
まず、Alphabetという企業について簡単に整理しておきましょう。
Alphabetは、私たちが日常的に使っているGoogleの親会社です。2015年に企業再編によって設立され、Google本体の事業と、それ以外の実験的な事業(Other Bets)を分けて管理する持株会社として機能しています。

主な事業セグメントは以下の3つです。
| セグメント | 主な内容 | 2025年Q3売上 | 前年比成長率 |
|---|---|---|---|
| Google Services | 検索広告、YouTube広告、Google Play、Pixelデバイスなど | 約870億ドル | +14% |
| Google Cloud | クラウドサービス、AI/機械学習プラットフォーム | 約152億ドル | +34% |
| Other Bets | 自動運転(Waymo)、ヘルスケア、ベンチャー投資など | 非開示(規模は小さい) | - |
このうち、圧倒的に大きいのがGoogle Servicesです。全体売上の約85%を占めており、私たちが毎日使っている検索エンジンやYouTubeがこのセグメントに含まれます。一方、Google Cloudは規模こそ小さいものの、成長率が34%と非常に高く、Alphabetの次の柱として急成長している分野です。
全体の業績サマリー:数字から見える大きな流れ
2025年第3四半期のAlphabetの業績を、シンプルにまとめてみましょう。
売上・利益の推移
| 指標 | 2024年Q3 | 2025年Q3 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 総売上 | 882.7億ドル | 1,023億ドル | +16% |
| 営業利益 | 285.2億ドル | 312.3億ドル | +9%* |
| 純利益 | 263億ドル | 349.8億ドル | +33% |
| 1株利益(EPS) | $2.12 | $2.87 | +35% |
*注:2025年Q3には欧州委員会(EC)からの罰金35億ドルが含まれています。この罰金を除外すると、営業利益の成長率はさらに高くなります。
全体として、売上は順調に伸びています。特に注目すべきは、純利益とEPSの伸び率が売上の伸び率を上回っている点です。これは、事業効率が改善し、収益性が高まっていることを示しています。
コスト構造の変化
マーケターとして気になるのは、どこにお金を使っているかですよね。以下の表で、主要なコスト項目の変化を見てみましょう。
| コスト項目 | 2024年Q3 | 2025年Q3 | 前年比 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 売上原価 | 364.7億ドル | 413.7億ドル | +13% | TAC(広告パートナーへの支払い)とインフラコストが中心 |
| 研究開発費 | 124.5億ドル | 151.5億ドル | +22% | AI開発への投資が増加 |
| 販売・マーケティング費 | 72.3億ドル | 72.1億ドル | 0% | ほぼ横ばい |
| 一般管理費 | 36億ドル | 73.9億ドル | +105% | EC罰金が影響 |
ここで興味深いのは、販売・マーケティング費用がほとんど増えていないことです。売上が16%も伸びているのに、マーケティング費用は横ばい。これは、既存の顧客基盤やプラットフォームの力で成長できている証拠です。一方で、研究開発費は22%も増加しており、AI技術などの未来への投資を積極的に行っていることがわかります。
マーケティング観点での注目点:3つの成長ドライバー
ここからは、マーケターとして特に注目すべき3つのポイントを深掘りしていきます。数字の背景にある戦略を読み解き、自社のマーケティングに応用できる要素を抽出していきましょう。
注目点1:AI時代の検索広告戦略 ― 「情報提供」と「行動促進」の二段構え
Google検索広告(Google Search & Other)の売上は、前年同期比で15%増加し、565.7億ドルに達しました。これは全体売上の約55%を占める巨大な事業です。生成AIでの検索やAI Overview(AIによる要約機能)が検索結果に表示されるようになった今でも、なぜ検索広告は成長し続けているのでしょうか。
その仮説は、Googleが「情報提供」と「行動促進」を見事に使い分けているからです。ユーザーが情報を探している段階では、AIが無料で価値を提供します。たとえば「引っ越し 手続き 順番」と検索すれば、AIが手続きの流れを丁寧に説明してくれます。この段階では、ユーザーは広告をクリックする必要がありません。しかし、実際に引っ越しが決まり「引っ越し業者 見積もり 東京」と検索した段階では、ユーザーは具体的な業者を探しています。このタイミングで、信頼できる引っ越し業者の広告が表示されれば、クリックされる確率は非常に高いのです。
つまり、AIは広告の競合相手ではなく、むしろユーザーを「情報収集段階」から「購買検討段階」へとスムーズに導く役割を果たしているのではないでしょうか。AIによって初心者でも気軽に検索できるようになり、検索回数自体が増加しています。その中から、本当に購買意図のある検索を見極め、適切なタイミングで広告を表示する精度が向上していることが、検索広告の成長を支えています。
注目点2:YouTube広告の復調 ― ショート動画とAIレコメンデーションの相乗効果
YouTube広告の売上は、89.2億ドルから102.6億ドルへと15%増加しました。実は、YouTubeは2022年から2023年にかけて成長が鈍化していた時期があり、TikTokなどの競合サービスに視聴時間を奪われているのではないかという懸念がありました。しかし今回の決算は、その懸念を払拭する力強い成長を示しています。
復調の背景には、二つの戦略的な取り組みがあります。一つ目は、YouTube Shortsの成長です。TikTokに対抗して開始したショート動画サービスですが、現在では月間アクティブユーザーが20億人を超え、1日あたりの視聴回数は700億回以上に達しています。短い動画で素早くユーザーの関心を引き、そこからロングフォーム動画や商品ページへと誘導する導線が、徐々に確立されてきています。
二つ目は、AIによるレコメンデーション機能の進化です。YouTubeのホーム画面やショート動画のフィードは、AIがユーザーの視聴履歴や興味関心を分析し、最適な動画を推薦しています。この精度が向上することで、ユーザーはより長い時間YouTubeに滞在し、結果として広告の露出機会が増えています。実際、YouTube全体での視聴時間は前年比で増加しており、これが広告収益の伸びにつながっているのです。
またYouTubeがクリエイターエコノミーを強化している点も注目です。人気クリエイターが作る質の高いコンテンツが、視聴者を引きつけ、広告の効果を高めています。Googleは、クリエイターへの収益分配を増やすことで、より多くの才能あるクリエイターを惹きつけ、コンテンツの質と量を拡充しているのです。これは「プラットフォーム」と「コンテンツ提供者」と「広告主」の三者がwin-winになる、理想的なエコシステムと言えます。
注目点3:Google Cloudの急成長 ― AI技術の商業化という新しい収益モデル
Google Cloudの売上は前年比34%増の151.6億ドル、営業利益は85%増の35.9億ドルと、驚異的な成長を見せています。特に注目すべきは、営業利益率が17.1%から23.7%へと大幅に改善している点です。これは、ビジネスモデルが成熟し、収益性が高まっていることを示しています。
この成長の中心にあるのが「AI as a Service」、つまりAI技術をサービスとして提供するビジネスモデルです。Googleは、自社が開発したAI技術(Gemini、Vertex AIなど)を企業向けに提供し、他社がAIを活用したサービスを作れるようにしています。企業がゼロからAIを開発するには、膨大な時間と費用がかかります。しかし、GoogleのAIプラットフォームを使えば、既に高度に訓練されたAIモデルを利用し、自社のデータでカスタマイズすることが可能になります。
これは、BtoB市場での「価値提供の転換」を象徴しています。かつてのクラウドサービスは「サーバーを貸す」「ストレージを提供する」というインフラ提供が中心でした。しかし今は、「AIという知能を貸す」時代になっています。顧客企業は、Google Cloudを使って、AIチャットボット、画像認識システム、予測分析ツールなど、さまざまなAI活用サービスを構築できます。
今回の決算で、設備投資(Capital Expenditures)が前年比83%増の239.5億ドルに達している点も、この戦略と密接に関連しています。Googleは、AI開発のためのデータセンターやGPU(画像処理装置)に巨額の投資を行っています。これは短期的には利益を圧迫しますが、長期的には圧倒的な技術優位性を築くための戦略的な判断です。競合他社が追いつけないレベルのAI技術を持つことで、Google Cloudの競争力を高めているのです。
Alphabetから学べる良い点:マーケターが真似すべき5つの戦略
ここまでの分析を踏まえて、Alphabetの戦略から学べる「良い点」を整理します。自社のマーケティング活動にも応用できるエッセンスを抽出しました。
良い点1:AIと広告の「役割分担」による顧客体験の最適化
Alphabetの最も優れた戦略の一つは、AIと広告を競合させるのではなく、明確に役割分担させている点です。AIは無料で情報を提供し、ユーザーの信頼と満足度を高めます。一方、広告は購買意図が明確になったタイミングで表示され、具体的な行動を促します。この二段構えのアプローチが、ユーザー体験を損なうことなく収益化を実現しています。
マーケターが学ぶべきは、「無料で価値を提供する施策」と「収益化する施策」を明確に分けることです。たとえば、ブログ記事やYouTube動画で有益な情報を無料提供し、信頼関係を構築します。そして、より深い情報や具体的な商品が必要になったタイミングで、有料サービスや商品購入へと導くのです。無料コンテンツを「おとり」と考えるのではなく、顧客との長期的な関係を築くための投資と捉えることが重要です。
また、AIツールを活用して顧客の行動段階を見極め、適切なタイミングで適切なメッセージを届けることも可能になっています。Google Analyticsなどのツールを使えば、どのページで離脱しているか、どんなキーワードで検索してきたかがわかります。この情報を基に、顧客の購買ジャーニーのどの段階にいるかを判断し、次に取るべきアクションを最適化できるのです。
良い点2:複数のタッチポイントを持つエコシステム戦略
Alphabetは、検索、YouTube、Gmail、Google Maps、Android、Chromeなど、ユーザーの生活のあらゆる場面に存在しています。これにより、一人のユーザーと複数のタッチポイントで接触できる仕組みを作っています。しかも、それぞれのサービスで得たデータを統合し、ユーザーの全体像を把握することで、より精度の高いターゲティングが可能になっています。
マーケターが学ぶべきは、「一つのチャネルに依存しない」ということです。たとえば、自社のWebサイトだけでなく、SNS、メールマガジン、店舗、アプリ、イベントなど、複数の接点を持つことで、顧客との関係を強化できます。重要なのは、それぞれのタッチポイントが個別に存在するのではなく、相互に連携していることです。
具体的な例を挙げましょう。あるアパレルブランドが、Instagram広告で新商品を紹介し、興味を持った顧客がWebサイトを訪問します。その後、メールマガジンで限定クーポンを送り、実店舗での購入を促します。購入後は、LINEで新作情報を定期的に配信し、リピート購入を促進します。このように、複数のチャネルが連携することで、顧客との接触頻度が増え、ブランドへの親近感が高まります。Alphabetのように、それぞれのタッチポイントで得た情報を統合し、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供できれば理想的です。
良い点3:データドリブンな意思決定と継続的な改善サイクル
Alphabetの強みは、膨大なデータを持っているだけでなく、それを活用して継続的に改善している点です。検索アルゴリズムは年に何千回も更新され、広告配信の精度も常に向上しています。AIモデルも、新しいデータを学習することで日々進化しています。この「計測→分析→改善」のサイクルを高速で回す能力が、競合他社を引き離す原動力になっています。
マーケターが真似すべきは、データに基づいて意思決定する習慣を組織に根付かせることです。Google Analyticsなどのツールを使えば、小規模な事業でもデータドリブンなマーケティングは可能です。大切なのは、データを見るだけでなく、そこから仮説を立て、施策を打ち、結果を検証する習慣を持つことです。
たとえば、自社サイトで「商品ページの直帰率が高い」というデータが得られたとします。ここから「商品説明が不十分なのではないか」という仮説を立て、レビューや使用例の追加というアクションを取ります。その結果を数週間後に測定し、改善されていれば継続、改善されていなければ別の施策を試す、というサイクルを回すのです。このPDCAサイクルを高速で回すことが、マーケティング成果を継続的に向上させる鍵です。
良い点4:長期投資と短期利益のバランス
今回の決算で興味深かったのは、設備投資が前年比83%増の239.5億ドルに達している一方で、販売・マーケティング費用は横ばいに抑えられている点です。これは、AI開発という長期的な競争力を高めるための投資には惜しみなく資金を投じる一方で、短期的な広告宣伝費は効率化しているということです。
Googleは、既存のプラットフォームの力で顧客を獲得できているため、大規模な広告キャンペーンを打つ必要がありません。ブランド力と口コミ、そしてAIによる検索体験の向上が、自然と新規ユーザーを呼び込んでいるのです。一方で、AI技術への投資は、5年後、10年後の競争力を左右する重要な要素だと判断し、短期的な利益率の低下を許容しています。
マーケターが学ぶべきは、「今すぐ売上を上げる施策」と「将来の基盤を作る投資」のバランスです。目先のキャンペーンばかりに予算を使うのではなく、ブランディングやコンテンツ資産の構築、顧客データベースの整備など、長期的に効果が持続する施策にも投資することが重要です。短期的なROIだけで判断すると、将来の成長機会を逃してしまう可能性があります。優れたマーケターは、四半期ごとの売上目標と、数年先を見据えた戦略的投資を、バランスよく実行できる人です。
良い点5:既存事業の最適化と新規事業への挑戦の両立
Alphabetは、検索広告という既存の稼ぎ頭を最適化しながら、同時にGoogle CloudやAI技術など新しい分野にも積極的に投資しています。この「両利きの経営」が、持続的な成長を可能にしています。検索広告が成熟期に入っても、Google Cloudが34%成長することで、全体としての成長を維持できています。
マーケターも同じ発想が必要です。今ある商品やサービスの売上を伸ばす施策(既存顧客へのリピート促進、LTV向上、クロスセル、アップセル)と、新しい顧客層や市場を開拓する施策(新商品開発、新チャネル開拓、新規セグメントへのアプローチ)を同時に進めることで、安定と成長を両立できます。
既存事業に全てのリソースを集中すると、市場が飽和した時に成長が止まります。逆に、新規事業ばかりに注力すると、既存事業が疎かになり、収益基盤が揺らぎます。両方をバランスよく進めることが、長期的な成功の鍵です。組織としては、既存事業を担当するチームと、新規事業を探索するチームを分けることで、それぞれの役割に集中できる体制を作ることも有効です。
考えられる改善点:Alphabetにも課題はある
どんな優良企業にも課題はあります。Alphabetの決算から見えてくる「改善の余地」についても、公平に見ていきましょう。
改善点1:規制リスクへの対応と社会的信頼の維持
今回の決算には、欧州委員会(EC)からの罰金35億ドルが含まれています。これは、Google Shoppingサービスが競争法に違反したとして科されたものです。Alphabetは世界各国で独占禁止法の調査対象となっており、規制リスクは常につきまといます。検索市場で約90%のシェアを持つことは、ビジネス上は有利ですが、社会的には「独占」と見なされるリスクがあります。
さらに、AI技術の発展に伴い、プライバシーやデータ利用に関する規制も強化される傾向にあります。ユーザーの行動データを収集し、それを広告配信に活用するビジネスモデルは、今後さらに厳しい目で見られる可能性があります。実際、欧州のGDPR(一般データ保護規則)や、米国の一部の州で導入されている消費者プライバシー法など、データ利用に関する規制は年々厳格化しています。
マーケターの視点で言えば、「市場支配力が強すぎることのリスク」を認識すべきです。短期的には独占的な地位が有利に働きますが、長期的には規制強化や消費者の反発を招く可能性があります。自社が強いポジションにいる場合でも、公正な競争環境を維持し、社会的な信頼を損なわないように配慮することが重要です。透明性のある情報開示や、ユーザーの選択権を尊重する姿勢が、長期的なブランド価値を守ることにつながります。
改善点2:Google Networkの減収が示す「中間業者」の立場の弱体化
Google Network(パートナーサイトに配信する広告)の売上は、75.5億ドルから73.5億ドルへと3%減少しています。これは、広告主がGoogle検索やYouTubeなど、Google自身が所有するプロパティに予算をシフトしていることを示しています。パートナーサイトに広告を配信する際は、Googleはあくまで「仲介者」の立場です。広告主からすれば、どんなサイトに広告が表示されるかが見えにくく、ブランドセーフティ(ブランドイメージを損なわないこと)の懸念もあります。
一方、Google自身が運営する検索やYouTubeなら、広告が表示される文脈が明確で、効果測定もしやすく、ブランドセーフティも確保しやすいという利点があります。広告主は、より確実に成果が出るチャネルに予算を集中させる傾向があるため、Google Networkのような中間業者的な立場のビジネスは縮小していく可能性があります。
マーケティング的に見ると、「中間業者」のポジションが弱くなっているということです。広告主は、より効果が測定しやすく、ブランドセーフティが確保できるプラットフォームを好む傾向があります。ここから学べるのは、「自社が仲介者の立場にある場合、付加価値を明確にする必要がある」ということです。単に商品を右から左に流すだけでは選ばれません。独自のサービスやサポート、データ、品質保証など、他では得られない価値を提供することが求められます。
改善点3:設備投資の増加による利益率への圧迫と投資回収の不確実性
設備投資が前年比83%増と大幅に増加している点は、長期的には良い投資ですが、短期的には営業利益率を圧迫しています。実際、営業利益率は32.3%から30.5%へと低下しています(EC罰金の影響もありますが)。AI開発のためのデータセンターやGPUへの投資は、技術優位性を築くために必要ですが、その投資が将来的に確実に回収できる保証はありません。
AI技術の進化は非常に速く、今投資している技術が数年後には陳腐化している可能性もあります。また、競合他社も同様に巨額の投資を行っているため、投資競争に巻き込まれ、利益率が長期的に低下するリスクもあります。実際、Google Cloudは高い成長率を示していますが、競合のAmazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureとの競争は激しく、価格競争に陥る懸念もあります。
マーケターとして考えるべきは、「成長のための投資と利益率のバランス」です。売上を伸ばすためにマーケティング予算を増やすことは重要ですが、それが利益を圧迫してしまっては本末転倒です。ROI(投資対効果)を常に意識し、効率的な予算配分を心がける必要があります。また、投資判断においては、短期的な成果だけでなく、長期的な競争力を高めるかどうかという視点も必要ですが、同時に「投資回収の見通し」も冷静に評価すべきです。
今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの視点で予測
最後に、Alphabetが今後も成長し続けられるかどうかを、マーケターの視点から考察します。
成長余地1:AI技術の商業化がまだ初期段階であること
Alphabetは、AI技術で業界をリードしています。特にGemini(大規模言語モデル)やVertex AI(企業向けAIプラットフォーム)は、今後の収益源として大きな可能性を持っています。現時点では、AI技術の収益化はまだ初期段階です。Google Cloudの売上は151.6億ドルですが、これは全体売上の約15%に過ぎません。しかし、企業のAI導入が進むにつれて、この比率は確実に増加するでしょう。
今回の決算でGoogle Cloudが34%成長したことは、この方向性が正しいことを示しています。AI技術は、製造業での品質管理、小売業での需要予測、金融業でのリスク分析、医療業での診断支援など、あらゆる業界で応用可能です。市場調査会社のGartnerによれば、世界のAI市場は今後5年間で年平均30%以上の成長が見込まれています。この巨大な市場で、Googleが技術的な優位性を持っていることは、大きな成長余地を示しています。
マーケティング的に見ると、これは「新しいカテゴリーの創出」です。従来のクラウドサービス市場だけでなく、AI技術という新しい市場を作り出すことで、成長の天井を引き上げているのです。既存市場が飽和している場合、新しいカテゴリーを作ることが、次の成長ステージへの鍵となります。
成長余地2:新興市場でのユーザー獲得とデジタル化の波
Alphabetの主な収益源は、欧米や日本などの先進国です。しかし、インドや東南アジア、アフリカなどの新興市場には、まだインターネットを使い始めたばかりの膨大な人口がいます。これらの地域でスマートフォンの普及が進み、インターネット利用者が増えれば、Googleのユーザーベースはさらに拡大します。
実際、YouTubeはこれらの地域で急速に成長しており、新しい広告市場が生まれています。インドでは、地域言語でのコンテンツが増加し、都市部だけでなく農村部でもYouTubeが視聴されるようになっています。また、モバイルファーストの市場では、Androidスマートフォンが主流であり、Google検索やGoogleマップなどのサービスが標準で搭載されています。これにより、新興市場でのGoogleのプレゼンスは、先進国以上に強固になる可能性があります。
マーケターとして学ぶべきは、「既存市場の深耕」だけでなく「新市場の開拓」の重要性です。国内市場が飽和しているなら、海外展開や新しい顧客層へのアプローチを検討する価値があります。新興市場は、既存のビジネスモデルをそのまま持ち込むのではなく、現地の文化や経済状況に合わせたカスタマイズが必要です。たとえば、価格設定を現地の購買力に合わせる、モバイルファーストのサービス設計にする、現地パートナーと提携するなどの工夫が求められます。
成長余地3:サブスクリプションモデルの拡大による収益の安定化と多様化
サブスクリプション、プラットフォーム、デバイス事業は、前年比21%増の128.7億ドルと、高い成長率を示しています。これには、YouTube Premium、YouTube Music、Google One(クラウドストレージ)、Google Playの課金、Pixelスマートフォンの販売などが含まれます。広告モデルは景気の影響を受けやすく、不況になると企業の広告予算が削減されるリスクがあります。しかし、サブスクリプションモデルは、ユーザーが毎月定額を支払うため、安定した収益を生み出します。
Alphabetがこの分野を強化していることは、収益の安定性を高める戦略として評価できます。特にYouTube Premiumは、広告なしで動画を視聴できるだけでなく、YouTube Musicも利用できるため、音楽配信サービスとしての側面もあります。このように、複数の価値を一つのサブスクリプションにまとめることで、ユーザーにとっての魅力を高めています。
また、Google Oneは、Googleフォトの無制限バックアップ終了に伴い、有料ストレージの需要が高まっています。写真や動画を大量に保存するユーザーにとって、クラウドストレージは必需品となっており、安定した収益源になっています。さらに、Pixelスマートフォンは、ハードウェア販売という新しい収益源を提供しています。Appleのように、自社のハードウェアとソフトウェアを統合することで、ユーザー体験を最適化し、エコシステムに囲い込むことができます。
マーケターにとっても、サブスクリプションモデルは重要です。一度きりの販売ではなく、継続的な関係を築くことで、LTV(顧客生涯価値)を最大化できます。自社の商品やサービスに、サブスクリプション要素を組み込めないか検討してみる価値があります。たとえば、製品販売だけでなく、メンテナンスサービスや消耗品の定期配送、プレミアムコンテンツへのアクセスなど、継続的な価値提供の方法は様々です。サブスクリプションモデルは、顧客との長期的な関係を構築し、安定した収益基盤を作る上で、非常に有効な戦略です。
まとめ:Alphabetの決算から学ぶマーケティング戦略のエッセンス
それでは、この記事の内容を総括して、マーケターが持ち帰るべきポイントを整理しましょう。
Key Takeaways(重要なポイント)
以下の表に、今回の分析から得られた主要な学びをまとめました。
| カテゴリー | 学べるポイント | 自社への応用方法 |
|---|---|---|
| AI時代の広告戦略 | AIと広告は競合ではなく役割分担。情報提供と行動促進を使い分けることで、ユーザー体験と収益化を両立 | コンテンツマーケティングで信頼を構築し、購買検討段階で広告を活用する二段構えの戦略を実行する |
| 顧客接点 | 複数のタッチポイントを持つエコシステム戦略が、顧客との関係を強化し、データの統合を可能にする | Webサイト、SNS、メール、店舗など、複数チャネルで顧客と接触し、データを統合して最適な体験を提供する |
| データ活用 | データドリブンな意思決定と継続的な改善サイクルが成長を支える。AIによるターゲティング精度の向上が費用対効果を改善 | 計測→分析→改善のPDCAサイクルを高速で回し、AIツールを活用してターゲティング精度を高める |
| 投資配分 | 短期的な販促費を抑えながら、長期的な技術投資に資金を振り向ける。既存プラットフォームの力で効率的に顧客獲得 | 目先のキャンペーンだけでなく、ブランディングやコンテンツ資産、技術基盤への長期投資も行う |
| 事業ポートフォリオ | 既存事業の最適化と新規事業への挑戦を同時に進める両利きの経営で、安定と成長を両立 | 既存顧客へのLTV向上施策と、新規顧客獲得施策、新市場開拓を並行して実行する |
| ビジネスモデル | 広告モデルとサブスクリプションモデルの組み合わせで収益を安定化。複数の収益源を持つことでリスク分散 | 一度きりの販売だけでなく、継続課金モデルや複数の収益源を検討し、安定した収益基盤を作る |
最後に:AI時代だからこそ、マーケティングの本質を見失わない
最初にお伝えしたように、決算資料は数字の羅列ではなく、企業の戦略が凝縮された「教科書」です。特に今回のAlphabetの決算からは、AI時代のマーケティング戦略について、多くの示唆を得ることができました。
最も重要な学びは、AIは人間のマーケターを置き換えるものではなく、マーケティングをより効果的にするツールであるということです。Alphabetは、AIを活用して検索体験を向上させながら、同時に広告ビジネスも成長させています。これは、テクノロジーと人間の判断を適切に組み合わせることで、より良い成果が得られることを示しています。
あなたが担当している商品やサービスにも、きっと活かせるヒントがあったはずです。AI時代だからこそ、データを活用し、顧客の行動段階を見極め、適切なタイミングで適切な価値を提供することが、これまで以上に重要になっています。一方で、長期的な信頼関係の構築、ブランド価値の向上、社会的責任といった、マーケティングの本質的な要素も決して忘れてはいけません。
明日からの業務に、ぜひこの学びを取り入れてみてください。そして、他の企業の決算も読んでみることをおすすめします。競合企業だけでなく、全く違う業界の決算にも、意外な発見があるかもしれません。マーケティングは、常に学び続けることが大切です。この記事が、あなたのマーケティングスキル向上の一助になれば幸いです。
参考資料