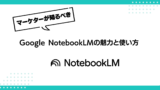はじめに
「情報が多すぎて整理できない」「社内ナレッジが活用されない」「コンテンツが再利用されない」──こうした悩みを抱えるマーケターや営業担当者は多いのではないでしょうか?
多くの企業では、社内に蓄積された膨大な資料や知見を十分に活用できず、同じようなコンテンツを繰り返し作成したり、必要な情報を探すだけで時間がかかったりしています。こうした“情報活用の非効率”が、意思決定や顧客対応のスピードを大きく損ねているのです。
Googleが提供するNotebookLMは、これまでのAIツールとは一線を画す“根拠に基づいたAIパートナー”です。ユーザー自身がアップロードした情報に限定して分析・要約・チャットができるため、企業固有のナレッジをベースにした判断や提案が可能です。
本記事では、NotebookLMの基本的な特徴から、マーケティング現場での実践的な活用法、成果につながるポイントまでを詳しく解説していきます。
NotebookLMとは?その特異性

公式サイト:https://notebooklm.google.com/
NotebookLMは、Googleが開発した生成AI活用のノートアプリケーションで、従来のChatGPTのようなプロンプト型AIとは異なり、特定の情報(Notebookにアップロードされたドキュメント)を元に、要約・分析・FAQ生成などのアウトプットを提供します。
以下はNotebookLMの概要です:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツール名 | Google NotebookLM |
| 特徴 | 自社データに基づいたAI活用(Web情報を勝手に参照しない) |
| 想定用途 | マーケティング資料の統合・要約・洞察抽出、営業支援、顧客理解 |
| 対象データ形式 | Googleドキュメント、PDF、Web記事、YouTube、音声など |
| 機能 | 要約、FAQ生成、タイムライン作成、チャット、マインドマップなど |
最大の強みは「根拠情報が特定可能」な点です。アップロードされた情報源に紐づいて回答が生成されるため、マーケティングレポートや提案資料などに“出典付きの情報”をスピーディに盛り込むことが可能になります。
また、Enterprise版ではコンプライアンスや社内共有の制御、利用制限の柔軟な設定が可能で、情報統制やリスク管理が求められる業界でも安全に導入可能です。
NotebookLMの活用法
NotebookLMはマーケティングや営業はもちろん、ナレッジマネジメント、教育、企画開発、CS、経営企画などあらゆるビジネスシーンで応用が可能です。以下では、10の具体的なユースケースをより詳しく解説します。
※ただし無料版だと読み込ませるソース数に限りがあります。
1. コンテンツギャップの特定と新規企画立案
- 読み込ませるソース:過去のブログ記事やホワイトペーパー、eBookなど
Notebookにまとめて読み込ませ、「どの顧客層に対してカバーできていないか?」「どのファネルステージのコンテンツが不足しているか?」を質問すると、AIが分析結果を返してくれます。さらに「○○業界の意思決定者向けに、今後書くべきコンテンツテーマは?」などの問いにも対応可能。これにより、感覚に頼らず論理的にコンテンツの方向性を決定できます。
2. 競合分析・差別化戦略の構築
- 読み込ませるソース:競合企業のWebサイト、プレスリリース、商品比較記事、IR資料など
「競合が強調している特徴」「逆に訴求していないニーズ」「自社が攻めるべきギャップは?」と質問することで、自社の差別化戦略や勝ち筋を発見できます。営業資料やポジショニングマップを作成する際の重要な基礎データにもなります。
3. 顧客の声(VOC)からインサイト抽出
- 読み込ませるソース:CSログ、アンケート結果、オンラインレビューなど、顧客の声に関するドキュメント
「よくある不満は?」「期待値を上回る要素は?」「キーワードの頻出傾向は?」とAIに尋ねることで、プロダクト改善、FAQ設計、顧客満足度向上のヒントを導き出すことが可能です。定性的なデータを構造化できる点が強みです。
4. 営業資料の自動要約と提案書テンプレート作成
- 読み込ませるソース:複数の製品パンフレットや導入事例資料
「3分で要点を伝える営業トークを作って」や「価格に対するメリット訴求を強調した提案構成を」と指示すると、営業現場で即活用できる要約とテンプレートが生成されます。新人営業やインサイドセールスの支援に最適です。
5. トレーニングコンテンツのFAQ化と要約
- 読み込ませるソース:社内研修資料、業務マニュアル、動画の文字起こしなど
「この資料を5つの質問と回答に要約して」や「新入社員が最初に覚えるべきポイントを抽出して」といった依頼で、教育コストを削減できます。生成されたFAQをeラーニングに活用することも可能です。
6. 会議議事録の要約・アクションリスト抽出
- 読み込ませるソース:Zoomの文字起こしデータや議事録テキスト
「誰が何を決めたか」「宿題は何か」「次回のToDoリストを抽出して」と指示すれば、議事録作成が劇的に時短され、会議後のアクション管理にも役立ちます。複数人の発言を混在させたままでも分析できる点が便利です。
7. Webサイトの改善案抽出
- 読み込ませるソース:アクセス解析データ(テキスト出力)、ヒートマップ分析コメント、各ページの文言や説明文
「ユーザーが離脱しているポイントは?」「コンバージョンの障害は?」「ページ改善案を3つ提案して」と尋ねることで、定性的・定量的な観点からWeb改善案を得ることができます。
8. 製品開発に向けた市場調査・ユーザー理解
- 読み込ませるソース:顧客インタビューの文字起こし、業界調査レポート、既存製品レビューなど
「新しい利用シーンの提案」「開発優先度が高そうな機能」「価格面でのハードル」などを抽出可能。開発初期フェーズでの顧客ニーズの解像度を大幅に上げられます。
9. ストーリーテリング型のプレゼン作成補助
- 読み込ませるソース:ブランドビジョン、社史、製品誕生エピソードなど
「ストーリー仕立ての構成案を」「エモーショナルな語り出しを提案して」と依頼することで、説得力と感情訴求を備えたプレゼン原稿をAIと共同制作できます。採用説明会やIR資料などにも活用できます。
10. 経営戦略・中計資料のインサイト抽出
- 読み込ませるソース:中期経営計画書、競合の決算資料、業界動向レポートなど
「5年後の成長分野は?」「次の中計で重視すべき施策は?」「競合が力を入れている領域は?」と質問することで、定量と定性の両視点から戦略検討の土台が構築されます。経営層の意思決定支援にも有効です。
その他にも、RFP作成、インサイドセールスの台本作成、顧客ごとの要望管理、チーム間のナレッジ統合など、あらゆる情報整理業務で活用が進んでいます。
NotebookLM Enterpriseの特徴とメリット
NotebookLMのEnterprise版は、単なる機能制限の拡張ではなく、「企業向けの安全性・運用性・統制性」を高めた設計が施されたエンタープライズ向けAI基盤です。
以下に、主要な比較ポイントを詳しく解説します:
| 項目 | Personal | Enterprise |
|---|---|---|
| クエリ上限/日 | 50 | 500(業務全体を通じてAI活用が可能) |
| ノートブック数 | 100 | 500(プロジェクト横断で知識資産を構築) |
| 情報源/ノートブック | 50 | 300(部門ごとのドキュメント蓄積・分析に対応) |
| 認証方式 | Google個人ID | Google Workspace、SAML認証(Okta連携可) |
| コンプライアンス | なし | VPC-SC準拠(業界標準のセキュリティフレームワークに対応)、リージョン指定可能 |
| 共有範囲 | 公開リンク可 | IAMロールベースで同一プロジェクト内に限定し、権限管理を徹底 |
主なメリット:
- セキュアな社内情報のみをソースにでき、情報漏洩リスクを排除
- 利用ログやアクセス権限の統制により、コンプライアンス要件を満たせる
- 大量のNotebookや情報源を扱えるため、部署横断的なナレッジ活用が可能
- SSOやIDプロビジョニングによる社内ITとの親和性も高く、導入後の管理工数が少ない
NotebookLM Enterpriseは、「セキュリティと拡張性を両立したAIツール」として、規模の大きい企業や高度なナレッジ統合が求められる組織にとって非常に有力な選択肢です。
ROIを最大化する活用ポイント
NotebookLMは導入するだけでは効果が最大化されません。目的に応じた使い方とKPI設定が鍵となります。
| 活用シーン | 測定KPI例 |
|---|---|
| コンテンツ制作支援 | 制作時間削減(Before/After比較)、再利用率、外注コストの削減 |
| 顧客理解・パーソナライズ | ペルソナ数の多様化、エンゲージメント率(CTR、CVR)、離脱率改善 |
| 営業サポート | 提案書作成時間、成約率、営業一人当たり対応件数の増加、ナレッジ共有率 |
| トレーニング用AI教材 | FAQカバー率、習熟時間の短縮、OJT工数の削減、自己解決率の向上 |
活用のカギは3つあります:
- 既存業務に組み込むこと(例:営業支援ツールと連携)
- 成果を測定できる形にすること(定量KPIの可視化)
- ナレッジ再利用の仕組みを設計すること(Notebookの再利用を促す設計)
また、CRMやMA(マーケティングオートメーション)と連携すれば、得られた示唆をそのまま施策に反映しやすくなり、インサイトから実行までのスピードが向上します。
まとめ|Key Takeaways
NotebookLMは単なる生成AIではなく、「業務の高度化・戦略支援を実現するAIパートナー」です。
本記事で紹介した3つの視点から、その価値を振り返ります:
1. エンタープライズ対応で、安心・拡張・統制の全てを両立
- 認証連携、リージョン制御、アクセス権限制限など、企業のセキュリティ要件を満たす
- 大規模なナレッジ統合・展開にも対応
2. 部門別・業務別にROIが明確化できる
- 制作、営業、顧客理解、教育の各シーンで時間短縮・精度向上を実現
- 活用領域が広いため、投資回収スピードが早い
3. 情報を“使えるナレッジ”に変換する新たなインフラ
- 文章や資料が単なるストックではなく、即座に活用できるインサイト源に
- 業務の非属人化・再現性向上につながる
今後NotebookLMは、「社内ナレッジを活用して成果を出せる組織」とそうでない組織の差を一層拡大させていく可能性があります。導入を迷っている企業こそ、いまこのタイミングで試してみる価値があります。