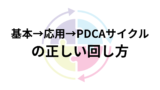はじめに:マーケターが直面する学びの課題
マーケティング担当者のみなさん、こんな悩みはありませんか?
「キャンペーンを何度も実施しているのに、なぜか同じような失敗を繰り返してしまう」「セミナーや本で学んだことが、実際の業務でうまく活かせない」「経験は積んでいるはずなのに、成長している実感がない」
実は、これらの悩みには共通する原因があります。それは「経験をしているだけで、経験から学べていない」ということです。
マーケティングの世界は日々変化し、昨日うまくいった施策が今日は通用しないこともあります。AIやデータ分析ツールなど新しい技術も次々と登場します。この環境で成長し続けるためには、単に経験を積むだけでなく、経験から効果的に学ぶ力が必要不可欠です。
そこで注目したいのが、教育心理学者デイビッド・コルブが提唱した「経験学習モデル」です。このモデルは、人がどのように経験から学ぶのかを体系化したもので、マーケターの成長を加速させる強力なフレームワークとして活用できます。
本記事では、コルブの経験学習モデルの基本から実践的な活用方法まで、マーケティング実務に即した形で徹底解説していきます。
コルブの経験学習モデルとは?
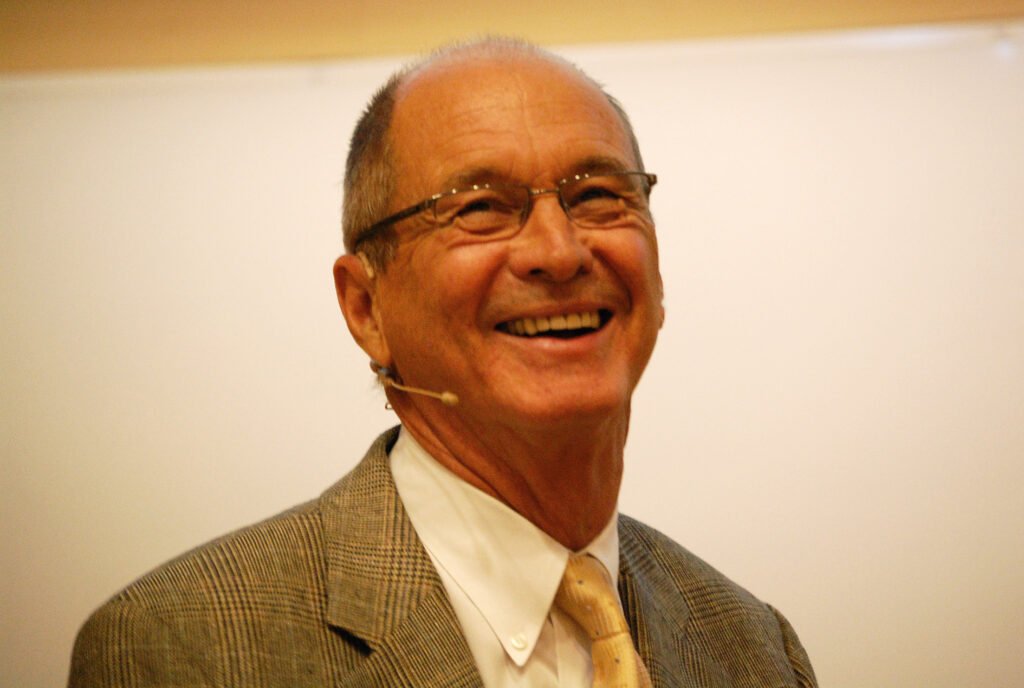
デイビッド・コルブ(David Kolb)は、アメリカの教育理論家で、1984年に「経験学習モデル(Experiential Learning Model)」を発表しました。このモデルは、人が経験を通じてどのように学習するかを説明する理論として、教育分野だけでなくビジネスの世界でも広く活用されています。
コルブの経験学習モデルの核心は、「学習は連続的なサイクルであり、4つの段階を循環することで深まる」という考え方です。つまり、一度きりの経験では本当の学びにはならず、そこから得た気づきを次の行動に活かし、さらにその結果を振り返る…というサイクルを回すことで、初めて成長につながるということです。
経験学習モデルの全体像
コルブは、学習プロセスを以下の4つの段階で説明しています。
| 段階 | 英語名 | 説明 | マーケティング業務での例 |
|---|---|---|---|
| 具体的経験 | Concrete Experience (CE) | 実際に何かを体験する段階 | SNS広告キャンペーンを実施する |
| 内省的観察 | Reflective Observation (RO) | 経験を振り返り、観察する段階 | キャンペーン結果を見て「なぜCVRが低かったのか」を考える |
| 抽象的概念化 | Abstract Conceptualization (AC) | 経験から一般的な法則や理論を導き出す段階 | 「ターゲット層に刺さるクリエイティブの要素」という仮説を立てる |
| 能動的実験 | Active Experimentation (AE) | 学んだことを新しい状況で試してみる段階 | 仮説を元に改善した新しいキャンペーンを実施する |
このサイクルを図解すると、次のようになります。
重要なのは、このサイクルが一方向に進む連続的なプロセスだということです。どこか1つの段階で止まってしまうと、本当の学びにはつながりません。
4つの学習段階を詳しく理解する
それでは、各段階について、マーケティング実務に即して詳しく見ていきましょう。
第1段階:具体的経験(Concrete Experience)
具体的経験は、サイクルの出発点です。ここでは、実際に何かを体験します。
マーケティングの文脈では、以下のような活動がこれに当たります。
| 具体的経験の例 | 詳細 |
|---|---|
| 新規キャンペーンの実施 | Google広告で新しいターゲティング設定を試す |
| 顧客インタビューの実施 | 実際に顧客と対話して生の声を聞く |
| A/Bテストの実行 | 2パターンのランディングページを比較テストする |
| 競合調査 | 競合他社の新サービスを実際に使ってみる |
| イベントへの参加 | 業界カンファレンスで最新トレンドを体感する |
この段階で大切なのは、先入観を持たずに、オープンな姿勢で経験することです。「こうなるはず」という予測にとらわれず、実際に何が起きるかを観察する姿勢が重要になります。
また、経験の質も重要です。ただ漠然と作業をこなすのではなく、「これは何のための経験なのか」「何を学びたいのか」という意図を持って取り組むことで、後の段階での学びが深まります。
第2段階:内省的観察(Reflective Observation)
内省的観察は、経験を振り返り、じっくりと観察する段階です。
ここでは、単に「うまくいった」「失敗した」という表面的な評価にとどまらず、多角的な視点から経験を分析します。
| 内省的観察で問うべき質問 | 目的 |
|---|---|
| 何が起きたのか? | 事実を客観的に把握する |
| なぜそうなったのか? | 原因を探る |
| 誰が、どのように関わったのか? | 関係者や要因を整理する |
| どんな感情や反応があったのか? | 主観的な側面も含めて理解する |
| 予想と異なっていた点は? | 意外性や学びのポイントを見つける |
| 他の類似経験と比べてどうだったか? | パターンを見出す |
例えば、SNS広告キャンペーンを実施した後の内省的観察では、次のような分析を行います。
事実の整理:クリック率は予想より30%高かったが、コンバージョン率は目標の半分だった。特に18-24歳の層でクリックは多いが購入に至らないパターンが見られた。
原因の探索:広告クリエイティブは魅力的だったが、ランディングページの商品説明が若年層には堅苦しすぎた可能性がある。また、価格表示が分かりにくく、決済直前で離脱が多かった。
感情的側面:チーム内では「クリック率が高いから成功だ」という雰囲気があったが、実際にはコンバージョンにつながっていないというギャップにもどかしさを感じた。
この段階では、データだけでなく、感覚や直感も大切にすることがポイントです。数字には現れない「何か違和感があった」という感覚が、重要な学びにつながることもあります。
第3段階:抽象的概念化(Abstract Conceptualization)
抽象的概念化は、個別の経験から一般的な法則やパターンを見出す段階です。
ここでは、「この経験から何が言えるのか?」「他の状況にも応用できる原則は何か?」を考えます。つまり、経験を抽象化して、再現可能な知識に変換するのがこの段階の目的です。
先ほどのSNS広告の例で言えば、次のような概念化ができるかもしれません。
| 経験から導き出した概念・法則 | 今後への応用 |
|---|---|
| 若年層は視覚的インパクトで興味を持つが、購入決定には明確な価値提示が必要 | ターゲット年齢層に応じて、広告とLPの訴求内容を変える |
| クリック率とコンバージョン率には相関がない場合がある | 成功指標を見直し、最終的な売上につながる指標に注目する |
| ユーザージャーニーの各段階で適切なコミュニケーションが必要 | 認知→興味→検討→購入の各段階で異なるコンテンツを用意する |
抽象的概念化のポイントは、「もし〜なら、〜である」という仮説の形で表現することです。これにより、他の状況でも検証可能な知識になります。
また、この段階では既存の理論やフレームワークと照らし合わせることも有効です。例えば、自分の経験が「カスタマージャーニー理論」や「認知的不協和理論」などの既存理論と一致するか確認することで、学びがより深まります。
第4段階:能動的実験(Active Experimentation)
能動的実験は、第3段階で導き出した概念や仮説を、新しい状況で実際に試してみる段階です。
この段階では、単に同じことを繰り返すのではなく、学んだことを応用して、意図的に変化を加えた行動をとります。
| 能動的実験の例 | 前段階で学んだこと | 新しい試み |
|---|---|---|
| 改善版キャンペーンの実施 | 若年層には明確な価値提示が必要 | LPのファーストビューに「3つのメリット」を大きく表示 |
| 新しいターゲティング | 興味関心と購買意欲は別 | リターゲティング広告で検討段階の層に絞る |
| 別チャネルでの検証 | ユーザージャーニーに応じた訴求が重要 | Instagram広告とLP、メールの連携で段階的アプローチ |
能動的実験の重要なポイントは、「実験」としての意識を持つことです。つまり、「これでうまくいくはず」と確信するのではなく、「この仮説が正しいか検証してみよう」という態度で臨むことです。
また、実験する際は、何を検証したいのかを明確にし、結果を測定できる状態にしておくことが大切です。そうすることで、次のサイクルの「具体的経験」がより意味のあるものになります。
こうして第4段階が終わると、再び第1段階の「具体的経験」に戻り、サイクルが継続します。このサイクルを何度も回すことで、学びが深まり、スキルが向上していくのです。
なぜ経験だけでは学べないのか?
ここで、多くの人が陥りがちな罠について触れておきます。それは、「経験さえ積めば自然と学べる」という思い込みです。
実際には、経験を積んでも学べない人は少なくありません。その理由は、経験学習サイクルのどこかが欠けているからです。
よくある失敗パターン
| 失敗パターン | 欠けている段階 | 結果 | 改善方法 |
|---|---|---|---|
| 行動主義タイプ | 内省的観察と抽象的概念化が欠如 | とにかく動くが、同じ失敗を繰り返す | 立ち止まって振り返る時間を意図的に作る |
| 分析麻痺タイプ | 具体的経験と能動的実験が欠如 | 考えすぎて行動できない | 小さく始めて実験する習慣をつける |
| 理論家タイプ | 具体的経験が欠如 | 知識は豊富だが実践できない | 理論を実際の業務に適用する機会を作る |
| 振り返り不足タイプ | 内省的観察が不十分 | 忙しさに追われて学びが定着しない | 週次で振り返りの時間を確保する |
例えば、あるマーケターは毎月新しい広告キャンペーンを次々と実施していました(具体的経験)。しかし、忙しさにかまけて結果を詳しく分析せず(内省的観察の欠如)、なんとなく「次はこうしよう」と思いつきで次の施策を決めていました(抽象的概念化の欠如)。結果として、1年経っても同じような失敗を繰り返し、成長が停滞していました。
別のマーケターは、マーケティングの本を読み漁り、セミナーにも頻繁に参加していました(抽象的概念化)。しかし、学んだ理論を実際の業務で試すことがなく(能動的実験の欠如)、知識だけが増えて実践力が伴わない状態になっていました。
このように、サイクルのどこかが欠けると、経験が学びにつながらないのです。だからこそ、意識的に4つの段階すべてを回していく必要があります。
コルブの4つの学習スタイル
コルブは、経験学習サイクルの研究を進める中で、人によって学習の好みやスタイルが異なることを発見しました。これが「学習スタイル理論」です。
学習スタイルの4タイプ
コルブは、「能動-内省」と「抽象-具体」という2つの軸で学習スタイルを4つに分類しました。
それぞれのスタイルの特徴を詳しく見ていきましょう。
| 学習スタイル | 強み | 好む学習方法 | マーケティング業務での傾向 | 成長のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 拡散型(Diverging) | 多角的な視点、創造性、共感力 | ブレインストーミング、グループディスカッション | アイデア出し、ユーザーインサイトの発見が得意 | 実行力を高める、決断を早くする |
| 同化型(Assimilating) | 論理的思考、体系化、理論構築 | 講義、読書、データ分析 | 戦略立案、レポート作成、理論的裏付けが得意 | 実践的な応用力を磨く、柔軟性を持つ |
| 収束型(Converging) | 問題解決、意思決定、実践的応用 | シミュレーション、ケーススタディ | 課題解決、A/Bテスト設計、最適化が得意 | 多様な視点を取り入れる、人の感情を考慮する |
| 適応型(Accommodating) | 行動力、直感、柔軟性 | 実地経験、トライアル&エラー | 新しい施策の実行、迅速な対応が得意 | 計画性を持つ、振り返りの時間を確保する |
自分の学習スタイルを知る意義
自分の学習スタイルを理解することには、次のようなメリットがあります。
まず、自分の強みを活かせる業務や役割を選びやすくなります。例えば、拡散型の人はユーザーリサーチやコンセプト開発に向いていますし、収束型の人はデータドリブンな最適化業務に適しています。
次に、自分の苦手な段階を意識的に補うことができます。例えば、適応型で行動力はあるけど振り返りが苦手な人は、週次で振り返りの時間を意図的に設けるなど、サイクル全体を回す工夫ができます。
また、チーム編成の際にも活用できます。異なる学習スタイルの人が集まることで、チーム全体としてバランスの取れた学習サイクルを回すことができます。拡散型の人がアイデアを出し、同化型の人が戦略に落とし込み、収束型の人が具体的な施策を設計し、適応型の人が素早く実行する、といった具合です。
ただし、重要なのは「自分のスタイルに固執しすぎない」ことです。コルブ自身も、効果的な学習には4つすべての段階を経験することが必要だと強調しています。自分の得意なスタイルを活かしつつも、苦手な段階にも意識的に取り組むことが成長につながります。
マーケティング実務での具体的な活用方法
それでは、コルブの経験学習モデルを実際のマーケティング業務でどう活用するか、具体的な方法を見ていきましょう。
ケーススタディ1:広告キャンペーンの改善サイクル
ある化粧品ブランドのデジタルマーケティング担当者が、新商品のローンチキャンペーンを実施したケースです。
【第1段階:具体的経験】
Instagram広告とGoogle広告を組み合わせた新商品キャンペーンを2週間実施。予算は各チャネル50万円ずつ、計100万円。ターゲットは25-35歳の女性。
結果:Instagram広告のCTRは業界平均の1.8倍だったが、コンバージョン率は目標の60%にとどまった。Google広告は逆にCTRは平均的だったが、コンバージョン率は目標を20%上回った。
【第2段階:内省的観察】
チームでキャンペーン結果を振り返るミーティングを実施。以下の観察結果をまとめました。
Instagramでは「かわいい」「気になる」といったコメントが多く、商品への興味は引けていた様子。しかし、購入ページまで遷移した人の半数が、商品詳細ページで離脱していた。離脱した人の動線を追うと、「成分」「使い方」「効果」などの詳細情報を求めてページ内を何度もスクロールしていた。
Google広告経由のユーザーは、元々「乾燥肌 化粧水」「敏感肌 スキンケア」など、悩みを検索していた人たち。こちらのユーザーは商品詳細をじっくり読み、レビューも確認してから購入に至るパターンが多かった。
【第3段階:抽象的概念化】
この経験から、以下の仮説を立てました。
「SNS広告は視覚的魅力で興味を引くには効果的だが、購入決定にはより詳細な情報と信頼性が必要。一方、検索広告経由のユーザーはすでに課題を自覚しており、解決策を求めているため、情報さえしっかり提供すればコンバージョンしやすい」
さらに一般化して、「認知フェーズと購買決定フェーズでは、必要なコミュニケーションが異なる。SNSでは興味喚起に特化し、詳細情報は別の手段で補完する戦略が有効」という原則を導き出しました。
【第4段階:能動的実験】
仮説を検証するため、次のキャンペーンで以下の実験を行いました。
Instagram広告では引き続き視覚的に魅力的なクリエイティブを使用しつつ、遷移先を商品詳細ページではなく、「使い方動画+before/after写真+成分解説」をコンパクトにまとめた専用ランディングページに変更。また、「今なら初回限定でミニサイズプレゼント」という試用のハードルを下げるオファーを追加。
Google広告では、より具体的な悩みキーワード(「目元 乾燥 対策」「季節の変わり目 肌荒れ」など)に絞り込み、広告文にも具体的な解決策を明記。
結果、Instagramキャンペーンのコンバージョン率は前回の60%から85%に改善し、Google広告はさらに効率が上がってROASが30%向上しました。
この成功をもとに、さらに次のサイクルへ。Instagram広告から一度離脱したユーザーに対して、使用者レビューを中心としたリターゲティング広告を配信するなど、新しい実験を続けています。
ケーススタディ2:チーム全体の学習文化構築
あるSaaS企業のマーケティングチームが、組織的に経験学習サイクルを回す仕組みを作った事例です。
導入した仕組み
| 仕組み | 対応する段階 | 具体的な内容 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| スプリント実行 | 具体的経験 | 2週間単位で施策を実行し、結果を記録 | 常時 |
| 振り返りミーティング | 内省的観察 | 各スプリント終了後、チーム全員で結果を多角的に分析 | 隔週 |
| 学びのドキュメント化 | 抽象的概念化 | 「今回の学び」を3つのポイントにまとめてNotionに蓄積 | 隔週 |
| 実験計画会議 | 能動的実験 | 学びを元に次のスプリントの実験内容を設計 | 隔週 |
| 月次ナレッジシェア | 全段階の統合 | 他チームメンバーの経験から学ぶ機会 | 月次 |
この仕組みを3ヶ月間運用した結果、チーム全体の施策成功率が向上し、新しいメンバーの立ち上がりも早くなりました。また、失敗を責める文化ではなく「失敗から学ぶ」文化が根付き、メンバーが主体的に新しいチャレンジをするようになったそうです。
日々の業務に取り入れる簡単な方法
大がかりな仕組みを作らなくても、個人レベルでできる実践方法もあります。
毎週金曜日の30分振り返り習慣
週末に30分だけ時間を取り、その週の経験を振り返ります。以下のようなシンプルなテンプレートを使うと効果的です。
今週実施したこと(具体的経験):新しいメールマーケティングキャンペーンを配信。開封率は18%、クリック率は2.5%だった。
気づいたこと(内省的観察):件名に絵文字を入れたものの方が開封率が高かった。一方で、クリックされたのは具体的なメリットを書いたメール本文だった。絵文字は目を引くが、それだけでは行動につながらない。
学んだこと(抽象的概念化):注意を引く要素と行動を促す要素は別物。件名では注意を引き、本文では具体的価値を伝えるという役割分担が重要。
次に試すこと(能動的実験):来週のキャンペーンでは、件名は引き続き絵文字でキャッチーに、本文の最初の1文でメリットを明示する構成を試してみる。
このように、たった30分の振り返りでも、意識的にサイクルを回すことで学びの質が格段に高まります。
経験学習を阻害する5つの罠と対策
経験学習サイクルを効果的に回すためには、よくある罠を知り、避けることも重要です。
罠1:忙しさを理由に振り返らない
最も多い罠がこれです。「忙しくて振り返る時間がない」という状態です。
なぜ危険か:振り返りなしでは、経験が単なる「作業」になり、学びにつながりません。同じ失敗を繰り返したり、成功の要因が分からないまま再現性のない仕事を続けることになります。
対策:振り返りを「時間があればやる」オプションではなく、「必ずやる」ルーティンにすることです。カレンダーにブロックして他の予定を入れないようにする、金曜日の最後の30分は必ず振り返りに使うなど、仕組み化が効果的です。
罠2:表面的な振り返りで満足する
「結果が良かった。よし、次も同じようにやろう」といった表面的な振り返りで終わってしまうパターンです。
なぜ危険か:表面的な分析では真の成功要因や失敗の原因が見えず、再現性が生まれません。また、環境が変わったときに対応できなくなります。
対策:「なぜ?」を5回繰り返す「5Why分析」を取り入れましょう。例えば「広告のCVRが高かった」→「なぜ?」「クリエイティブが良かった」→「なぜ良かった?」「ターゲットの悩みに寄り添う表現だった」→「なぜその表現が刺さった?」…といった具合に深掘りします。
罠3:理論だけで実践しない
本やセミナーで学んだことをノートに書き溜めるだけで、実際に試さないパターンです。
なぜ危険か:知識があっても実践しなければスキルにならず、理論と実務の間にギャップが生じます。また、自分の環境に合うかどうかも分かりません。
対策:学んだことは72時間以内に小さく試すという ルールを作りましょう。完璧に準備してから実行するのではなく、「まず小さく試して学ぶ」というマインドセットが重要です。
罠4:失敗を恐れて実験しない
失敗を恐れるあまり、新しいことに挑戦せず、安全な方法ばかり選んでしまうパターンです。
なぜ危険か:新しい実験をしなければ新しい学びは得られず、成長が止まります。また、市場環境が変化したときに取り残されるリスクがあります。
対策:失敗を「学びの機会」として再定義しましょう。「失敗」ではなく「仮説が検証された」と捉えることで、心理的なハードルが下がります。また、小さく始めることでリスクを最小化できます。例えば、予算の5%だけを使って新しいチャネルを試すなど、「実験枠」を設定すると良いでしょう。
罠5:他人の経験を軽視する
自分が直接経験したことしか学びにならないと思い込み、他人の経験や失敗から学ぼうとしないパターンです。
なぜ危険か:すべてを自分で経験するには時間がかかりすぎますし、避けられたはずの失敗を繰り返すことになります。
対策:他人の経験も「代理経験」として学習サイクルに組み込みましょう。チーム内での事例共有会、他部署との情報交換、業界カンファレンスでの学びなど、様々な経験に触れる機会を意識的に作ります。ただし、他人の経験をそのまま適用するのではなく、自分の環境で試す(能動的実験)プロセスは必要です。
経験学習を加速させる5つの実践テクニック
最後に、経験学習サイクルをより効果的に回すための実践的なテクニックを紹介します。
テクニック1:学習ジャーナルをつける
学習ジャーナルとは、日々の経験と学びを記録するノートのことです。
方法
毎日5分だけでも、その日の気づきや学びをノートやデジタルツールに記録します。フォーマットは自由ですが、前述の4段階を意識すると効果的です。
「今日やったこと」「気づいたこと」「学んだこと」「次に試すこと」といったシンプルな項目で十分です。
効果
記録することで振り返りが習慣化され、学びが定着しやすくなります。また、数ヶ月後に読み返すことで、自分の成長を実感でき、モチベーションにもつながります。パターンや傾向も見えやすくなります。
テクニック2:「もし〜なら」思考実験をする
実際に実行する前に、頭の中でシミュレーションする方法です。
方法
「もしこの施策を実行したら、どうなるだろう?」「もしターゲットをこう変えたら?」「もし予算が半分だったら?」など、様々な「もし」を考えます。
特に、第3段階の抽象的概念化で導き出した仮説を、別の状況に当てはめて考えてみることで、理解が深まります。
効果
実際に失敗するリスクなしに、多様なシナリオを検討できます。また、思考実験を繰り返すことで、状況判断力や応用力が向上します。
テクニック3:ペアラーニング(相互学習)
同僚やチームメンバーと一緒に学習サイクルを回す方法です。
方法
週に1回、30分程度、同僚と互いの経験や学びを共有する時間を作ります。一人が話す役、もう一人が聞いて質問する役を交代で行います。
質問する側は「なぜそう思ったの?」「他にどんな選択肢があった?」「次はどうする?」など、相手の思考を深める質問を投げかけます。
効果
他者の視点が入ることで、自分では気づかなかった観点に気づけます。また、説明することで自分の理解も深まります(教えることは最高の学習方法)。さらに、孤独感が減り、継続しやすくなります。
テクニック4:失敗プレイリストを作る
失敗や うまくいかなかった経験を記録し、そこから学んだことをまとめるリストです。
方法
失敗や期待外れの結果が出たとき、感情的になる前に、客観的に記録します。「何が起きたか」「なぜそうなったか」「何を学んだか」「次はどうするか」を書きます。
定期的に見返して、同じパターンの失敗を繰り返していないかチェックします。
効果
失敗をネガティブなものではなく、学びの宝庫として捉え直すことができます。また、失敗から学ぶ文化が自分の中に根付きます。時間が経ってから見返すと、「あの失敗が今の成功につながっている」という気づきも得られます。
テクニック5:多様な経験を意図的に積む
同じような経験ばかりではなく、意図的に多様な経験をする方法です。
方法
普段の業務に加えて、以下のような「越境経験」を意識的に取り入れます。
他部署のプロジェクトに参加する、異なる業界のマーケティングイベントに参加する、自分とは違うターゲット層向けの施策を担当する、新しいマーケティングツールや手法に挑戦する、といった具合です。
効果
多様な経験をすることで、物事を多角的に見る力がつきます。また、異なる分野の知識を組み合わせることで、イノベーティブなアイデアが生まれやすくなります。コルブも、最も効果的な学習は多様な経験から生まれると述べています。
まとめ:経験を学びに変える習慣を身につける
ここまで、デイビッド・コルブの経験学習モデルについて、基本から実践方法まで詳しく見てきました。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめておきます。
Key Takeaways
経験学習モデルの本質:学習は「具体的経験」「内省的観察」「抽象的概念化」「能動的実験」の4段階を循環するサイクルであり、どの段階も欠かせない。
経験≠学び:経験を積むだけでは成長しない。意識的にサイクル全体を回すことで初めて、経験が学びに変わる。
学習スタイルの理解:人それぞれ得意な学習段階があるが、効果的な学習には4つすべての段階を経験することが重要。自分の弱点を補う工夫をする。
振り返りの重要性:最も軽視されがちだが、最も重要なのが「内省的観察」の段階。振り返りなしでは、経験は単なる作業になってしまう。
実験のマインドセット:失敗を恐れず、「仮説を検証する実験」として新しいことに挑戦する姿勢が成長を加速させる。
習慣化がカギ:一度だけサイクルを回しても意味がない。週次や月次で継続的にサイクルを回す習慣を作ることが、長期的な成長につながる。
チーム学習の力:個人だけでなく、チーム全体で経験学習サイクルを回す仕組みを作ることで、組織としての学習能力が高まる。
記録の価値:学びを言語化し、記録することで定着しやすくなり、後から見返すことで新たな気づきも得られる。
マーケティングの世界は常に変化し続けています。新しいプラットフォームが登場し、消費者の行動も変わり、競合も進化します。この環境で成長し続けるためには、単に経験を積むだけでなく、経験から効果的に学ぶ力が必要不可欠です。
コルブの経験学習モデルは、その学ぶ力を体系的に高めるための強力なフレームワークです。この記事で紹介した方法を、ぜひ明日からの業務に取り入れてみてください。
まずは小さく始めることをお勧めします。週に一度、30分の振り返り時間を作ることから始めてみませんか?その小さな一歩が、あなたのマーケターとしての成長を大きく加速させるはずです。
経験を積むだけのマーケターから、経験から学び続けるマーケターへ。その変化が、あなたのキャリアを次のレベルに引き上げてくれるでしょう。