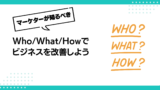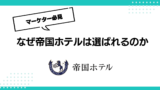はじめに
マーケティング担当者として、あなたは常に「なぜ特定のブランドが市場で選ばれ続けるのか」という問いと日々向き合っているのではないでしょうか。消費者の選択理由を深く理解することは、自社製品やサービスが選ばれる確率を高めるための重要な鍵となります。
本記事では、日本のビジネスホテル市場で独自のポジションを確立しているドーミーインを例に、このブランドが消費者から選ばれる理由を多角的に分析していきます。この分析を通じて、以下のメリットを得ることができるでしょう:
- 既存市場での差別化戦略の方法論を学べる
- 顧客の深層心理に訴求する効果的なブランディング戦略を理解できる
- 「当たり前」を超えた付加価値の設計方法を発見できる
日本のビジネスホテルの常識を覆したドーミーインの成功要因を紐解きながら、あなたのビジネスにも応用できる実践的な知見を提供していきます。
1. ドーミーインの基本情報
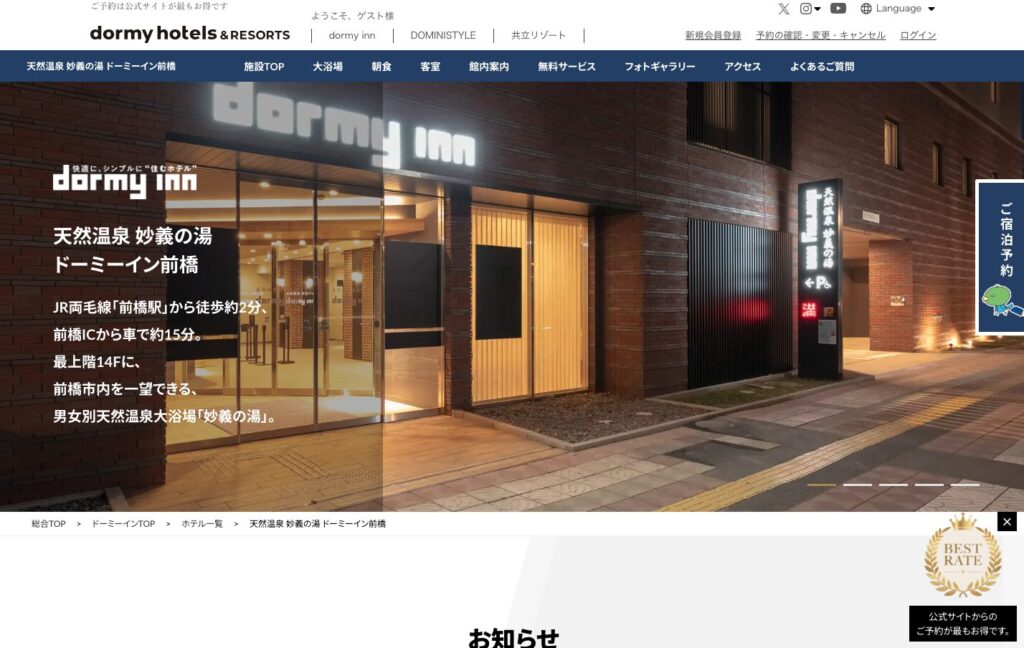
ブランド概要
ドーミーインは、株式会社共立メンテナンスが運営するビジネスホテルチェーンです。1986年に最初のホテルをオープンして以来、「温泉があるビジネスホテル」という独自のポジショニングで成長を続けてきました。元々は学生寮運営のノウハウから生まれた「帰ってきたような感覚」を大切にし、ビジネス出張者だけでなく観光客にも強く支持されています。
企業情報
- 企業名:株式会社共立メンテナンス(ドーミーイン事業部)
- 設立年:1979年(ドーミーインは1986年~)
- 本社所在地:東京都千代田区
- URL:https://www.hotespa.net/
主要製品・サービスラインナップ
ドーミーインは以下のようなブランド展開をしています:
- ドーミーイン:スタンダードタイプのビジネスホテル
- ドーミーイン PREMIUM:上位グレードのビジネスホテル
- 御宿 野乃:和風テイストのビジネスホテル
- ホテル・フォルツァ:機能性重視型ビジネスホテル
業績データ
ドーミーインは日本全国に97の施設を展開しており、年間客室稼働率は約86.9%と業界平均を上回っています。客室平均単価は約8,115円で、RevPAR(1室あたりの収益)は約12,000円と、競合のアパホテル(約7,000円)と比較しても高い水準を維持しています。また、顧客満足度調査ではビジネスホテル業界トップの評価を獲得しており、リピーター率の高さが特徴となっています。
2022年以降、インバウンド需要の回復もあり、業績は順調に伸長しています。ホテル事業を展開する共立メンテナンスの2024年3月期の売上高は2,000億円、営業利益は170億円となっています。
出典:共立メンテナンス IR
2. 市場環境分析
次にドーミーインが所属するビジネスホテル市場について理解していきましょう。
市場定義:顧客のジョブ(Jobs to be Done)
まずはドーミーインが所属しているカテゴリーは顧客の何を解決しているのかを考えてみましょう。ビジネスホテルが解決する主な顧客のジョブは以下の通りです:
- 「出張先での疲れを癒し、翌日のビジネスに備えたい」(機能的ジョブ):ビジネスパーソンが出張先で快適に休息し、翌日のビジネスに万全の状態で臨むための環境を得たいというニーズ。
- 「リーズナブルな価格で必要十分な宿泊環境を確保したい」(機能的ジョブ):過度な贅沢ではなく、清潔で必要な機能が整った宿泊施設を適正価格で利用したいというニーズ。
- 「観光地を効率的に巡りたい」(機能的ジョブ):観光客が観光スポットへのアクセスが良く、荷物を置いて身軽に観光を楽しめる拠点を確保したいというニーズ。
- 「旅先でも"自分らしく"くつろぎたい」(感情的ジョブ):非日常の旅先でありながらも、自宅のようにリラックスできる空間でくつろぎたいという感情的なニーズ。
これらのジョブの量と優先度はビジネスパーソンと観光客で異なりますが、特に「疲れを癒す」というジョブの優先度は両者ともに高いと考えられます。ドーミーインはこの点に注目し、温泉やサウナという差別化要素で強く訴求しています。
競合状況
ビジネスホテル市場における主要プレイヤーとその特徴は以下の通りです:
- アパホテル:低価格と高効率運営、立地の良さが強み
- 東横イン:標準化された品質と低価格が強み
- スーパーホテル:エコロジーと健康志向を強調
- リッチモンドホテル:上質なインテリアと朝食が強み
- ホテルルートイン:地方都市に強い展開と温泉設備
この中でドーミーインは、「温泉があるビジネスホテル」という位置づけで、価格帯は中~高めながらも温泉という付加価値で差別化を図っています。
POP/POD/POF分析
次に、このカテゴリーで戦って勝っていくために必要な要素を整理していきましょう。
Points of Parity(業界標準として必須の要素)
- 清潔で機能的な客室(ベッド、バス・トイレ、Wi-Fi等)
- アクセスの良い立地
- リーズナブルな価格設定
- 効率的なチェックイン・チェックアウトプロセス
- 基本的なセキュリティ対策
Points of Difference(差別化要素)
- 大浴場・サウナ・温泉施設の完備
- 「夜鳴きそば」など無料のフードサービス
- アットホームな雰囲気と「帰ってきたような感覚」
- 地域性を活かした朝食メニュー
- リピーターを意識したロイヤルティプログラム
Points of Failure(市場参入の失敗要因)
- 不十分な清掃や設備メンテナンス
- 不便な立地や交通アクセス
- スタッフの対応の悪さ
- 騒音や周辺環境の問題
- 予約システムの不備や使いにくさ
ドーミーインは、基本的なPOP(業界標準)を確保しながら、温泉や大浴場という強力なPOD(差別化要素)を前面に打ち出すことで、明確な市場ポジションを築いています。
PESTEL分析
ビジネスホテル市場を各視点で見たときの追い風と向かい風を分析します。
Political(政治的要因)
- 機会:観光立国政策によるインバウンド促進策
- 脅威:税制改正(宿泊税の導入など)による価格上昇圧力
Economic(経済的要因)
- 機会:ビジネス出張の回復、国内旅行需要の増加
- 脅威:景気後退によるビジネス出張削減、原材料・人件費の上昇
Social(社会的要因)
- 機会:ワーケーションの普及、健康志向の高まり
- 脅威:少子高齢化による国内旅行市場の縮小懸念
Technological(技術的要因)
- 機会:予約システムのデジタル化、IoT技術の宿泊施設への導入
- 脅威:オンライン会議の普及によるビジネス出張の減少
Environmental(環境的要因)
- 機会:環境配慮型ホテル運営への注目度上昇
- 脅威:温泉資源の枯渇リスク、エネルギーコストの上昇
Legal(法的要因)
- 機会:規制緩和による新規出店の容易化
- 脅威:労働法制の厳格化による人件費上昇
日本のビジネスホテル市場全体は、コロナ禍からの回復過程にあり、特にインバウンド需要の回復が追い風となっています。また、温泉や大浴場といった健康・リラクゼーション要素への注目度の高まりは、ドーミーインのビジネスモデルと親和性が高いと言えます。
3. ブランド競争力分析
続いて、ドーミーイン自体の強み、弱みは何で、それらが今の外部環境の中でどう活かしていけるのか、いくべきなのかを見ていきましょう。
SWOT分析
Strengths(強み)
- 温泉・大浴場という明確な差別化ポイント
- 「夜鳴きそば」などの独自の無料サービス
- 高い顧客満足度とリピート率
- 全国90箇所以上の店舗網
- アットホームな雰囲気と「帰ってきたような感覚」の提供
- 客室平均単価とRevPARの高さ
Weaknesses(弱み)
- 一部の立地が主要駅や観光地から離れている
- 競合と比較した客室数の少なさ
- 国際的な知名度の低さ
- デジタルマーケティングや最新テクノロジー活用の遅れ
- 温泉設備がない店舗の存在
Opportunities(機会)
- インバウンド需要の回復による外国人観光客の増加
- 健康志向の高まりによる温泉・サウナ需要の増加
- デジタル技術を活用した新サービス開発の可能性
- 地域観光資源との連携強化による差別化
- ビジネスと観光を組み合わせたブリージャー需要の拡大
Threats(脅威)
- 競合他社による温泉・大浴場の導入
- 人件費や光熱費の上昇によるコスト増加
- 新型コロナウイルスなど感染症リスクの再燃
- オンライン会議の普及によるビジネス出張の減少
- 若年層の温泉文化離れ
クロスSWOT戦略
SO戦略(強みを活かして機会を最大化)
- 温泉・大浴場の魅力をさらに高め、健康志向の顧客を積極的に取り込む
- インバウンド向けに温泉文化体験プログラムを開発
- 高いリピート率を活かしたロイヤルティプログラムの拡充
WO戦略(弱みを克服して機会を活用)
- デジタルマーケティングを強化し、若年層や外国人観光客へのアプローチを改善
- 最新技術を導入した客室管理システムやモバイルチェックインの導入
- インバウンド対応の多言語サービスの充実
ST戦略(強みを活かして脅威に対抗)
- 温泉と食事サービスの質をさらに高め、競合との差別化を強化
- アットホームな雰囲気や「夜鳴きそば」などの独自サービスのブランド価値を強化
- エネルギー効率の高い設備投資による光熱費の抑制
WT戦略(弱みと脅威の両方を最小化)
- オペレーション効率化による人件費抑制
- 立地の不利を補うための送迎サービスやパートナーシップの拡充
- オンライン予約システムの改善による直接予約の促進
この分析から、ドーミーインは温泉・大浴場という強みを最大限に活かしながら、デジタル化の推進と顧客体験の向上を同時に進めることが有効な戦略と考えられます。
4. 消費者心理と購買意思決定プロセス
続いて、ドーミーインの顧客はなぜこのブランドを選ぶのか、その購買行動の構造を複数パターンで見ていきましょう。
オルタネイトモデル分析
パターン1:ビジネス出張者
- 行動: 出張先でドーミーインを選んで予約する
- きっかけ: 会社からの出張指示、疲れた体を癒したい欲求
- 欲求: 翌日のビジネスに備え、効率的に疲れを取りたい
- 抑圧: 会社の出張予算の制限、贅沢をしているという罪悪感
- 報酬: 温泉での疲労回復、「夜鳴きそば」での小さな満足感、翌日の仕事への活力
このパターンでは、ビジネスパーソンは「ビジネスホテルなのに温泉がある」という特別感と、それでいて適正な予算内に収まるという安心感を同時に得ることができます。他のビジネスホテルでは得られない「ちょっとした贅沢」を感じられることが、選択の決め手となっています。
パターン2:観光客カップル/家族
- 行動: 観光地近くのドーミーインを選んで宿泊する
- きっかけ: 旅行プランを立てる際の宿探し、温泉を楽しみたい欲求
- 欲求: リーズナブルな価格で温泉を楽しみたい、観光の疲れを癒したい
- 抑圧: 旅行予算の制限、旅館よりも格下の宿に泊まる後ろめたさ
- 報酬: 予算内で温泉を満喫できる満足感、観光の疲れを癒す充実感
このパターンでは、観光客は「温泉旅館ほど高くなく、一般的なビジネスホテルよりも充実したサービス」という中間的ポジションに価値を見出しています。特に若いカップルや家族連れにとって、予算を抑えながらも温泉を楽しめるというバランスが魅力となっています。
パターン3:宿泊目的のない地元住民
- 行動: 日帰り入浴のためにドーミーインを利用する
- きっかけ: リフレッシュしたい気持ち、手軽に温泉を楽しみたい欲求
- 欲求: 自宅近くで手軽に温泉を楽しみたい、日常から少し離れたい
- 抑圧: 温泉施設として認知されていない、利用方法がわかりにくい
- 報酬: 都会の中での温泉体験、日常からの短時間脱出による満足感
このパターンでは、ホテルの宿泊客ではなく日帰り入浴を目的とした顧客が、アクセスの良さや設備の充実度に価値を見出しています。温泉旅館に行くほどの時間はないが、日常からちょっと離れたいという都市生活者のニーズに応えています。
本能的動機
ドーミーインが刺激する本能的動機を分析します。
生存本能に訴求する要素:
- 温泉やサウナによる身体的回復と疲労回復
- 清潔で安全な宿泊環境の提供
- 朝食や「夜鳴きそば」などの食事サービスによる栄養補給
- 快適な睡眠環境による休息の確保
繁殖本能に訴求する要素:
- カップルや家族での共有体験の場の提供
- 社会的つながりを感じられる共同浴場体験
- くつろぎ空間での対人関係の強化
- 「特別な体験」の共有による絆の深化
8つの欲望への訴求:
- 安らぐ:温泉やサウナでのリラックス体験、アットホームな雰囲気
- 進める:出張の効率化、翌日のビジネスへの準備
- 決する:自分の予算内で最適な選択ができた満足感
- 有する:ビジネスホテルでありながら温泉という「特別な体験」の所有感
- 属する:「ドーミーインのファン」というコミュニティ感覚
- 高める:「賢い選択をした」という自己肯定感
- 伝える:温泉体験や「夜鳴きそば」をSNSで共有する喜び
- 物語る:旅の思い出として後日語れるユニークな宿泊体験
特に「安らぐ」「属する」「高める」の3つの欲望に強く訴求していることが、ドーミーインの強みとなっています。温泉という日本文化に根ざした癒しの体験は「安らぐ」欲望に、アットホームな雰囲気は「属する」欲望に、そして「ビジネスホテルなのに温泉を堪能できる賢い選択をした」という感覚は「高める」欲望に強く訴求しています。
5. ブランド戦略の解剖
これまで整理した情報をもとに結局、ドーミーインはどういう人のどういうジョブに対して、なぜ選ばれているのか、そしてどうその価値を届けているのかをまとめていきます。
Who/What/How分析
パターン1:ビジネス出張者向け戦略
Who(誰に):30~50代の出張が多いビジネスパーソン
Who(JOB):出張先での疲れを効率的に癒し、翌日のビジネスに備えたい
What(便益):温泉・大浴場での疲れ回復、夜鳴きそばでの小さな満足感
What(独自性):一般的なビジネスホテルにはない温泉・大浴場体験
What(RTB):天然温泉の効能、サウナ設備の充実度
How(プロダクト):機能的な客室、本格的な大浴場・サウナ、夜鳴きそば
How(コミュニケーション):「ビジネスの疲れを癒す」訴求、法人営業
How(場所):主要ビジネス街や駅周辺への出店 H
ow(価格):一般的なビジネスホテルよりやや高めの価格設定(8,000円前後)
ビジネス出張者向け戦略では、「出張先の第二の我が家」というポジショニングで、単なる宿泊以上の価値を提供しています。特に、出張の疲れを温泉で癒せるという点が強力な差別化要素となっており、予算内ながらも特別感のある体験を求めるビジネスパーソンから強い支持を得ています。
パターン2:観光客向け戦略
Who(誰に):20~40代のカップルや家族連れの観光客
Who(JOB):観光の疲れを癒しながらも予算内で温泉を楽しみたい
What(便益):観光地アクセスの良さと温泉体験の両立
What(独自性):旅館より手頃な価格で楽しめる温泉体験
What(RTB):本格的な天然温泉設備、地域性を活かした朝食
How(プロダクト):使いやすい客室、充実した大浴場、バラエティ豊かな朝食
How(コミュニケーション):「観光も温泉も楽しめる」訴求、OTAでの訴求
How(場所):主要観光地や駅周辺
How(価格):温泉旅館より安く、一般ビジネスホテルより少し高い価格帯
観光客向け戦略では、「温泉旅館とビジネスホテルの良いとこ取り」というポジショニングで、コストパフォーマンスの高さを訴求しています。特に、若いカップルや家族連れなど、温泉を楽しみたいが旅館の価格は手が出ないというセグメントにとって魅力的な選択肢となっています。
成功要因の分解
ブランドのポジショニングと独自価値:
- 「ビジネスホテルに温泉という付加価値を提供する」という明確なポジショニング
- 「第二の我が家」のようなアットホームな雰囲気の提供
- 「夜鳴きそば」などの独自サービスによる差別化
コミュニケーション戦略の特徴:
- 温泉・大浴場の魅力を前面に押し出したビジュアルコミュニケーション
- 「帰ってきたような感覚」を強調するメッセージング
- リピーターを意識した口コミ・体験重視のプロモーション
- 地域特性を活かした訴求ポイントの調整
価格戦略と価値提案の整合性:
- 一般的なビジネスホテルよりやや高めの価格設定(平均単価約8,115円)
- 温泉・大浴場という付加価値と価格のバランス
- 「夜鳴きそば」などの無料サービスによる価値の上乗せ
- 直接予約の促進による顧客との関係強化
カスタマージャーニー上の差別化ポイント:
- 認知段階:「温泉があるビジネスホテル」という明確なメッセージ
- 検討段階:大浴場の写真やサービス詳細による他社との明確な差別化
- 購入段階:ロイヤルティプログラムや直接予約特典の提供
- 体験段階:温泉、「夜鳴きそば」などの期待を超える体験の提供
- 推奨段階:リピーターを大切にするサービスによる口コミ促進
顧客体験(CX)設計の特徴:
- 「帰ってきたような感覚」のためのアットホームなサービス設計
- 多様な顧客ニーズに応える複数ブランド展開(ドーミーイン、御宿野乃など)
- サービス品質の一貫性を重視した運営体制
- 地域性を活かした朝食メニューなど、立地に応じた体験のカスタマイズ
見えてきた課題
外部環境からくる課題と対策:
- インバウンド需要への対応
- 課題:言語対応や文化的ニーズへの対応不足
- 対策:多言語対応の強化、外国人向け温泉利用ガイドの整備、インバウンド向けプランの開発
- 競合他社による模倣リスク
- 課題:他のビジネスホテルチェーンによる温泉・大浴場の導入
- 対策:サービス品質のさらなる向上、「夜鳴きそば」など独自サービスの強化、ロイヤルティプログラムの充実
- エネルギーコスト上昇への対応
- 課題:温泉・大浴場の維持にかかるエネルギーコストの上昇
- 対策:エネルギー効率の高い設備への投資、再生可能エネルギーの導入、省エネ運営の強化
内部環境からくる課題と対策:
- デジタル化への対応
- 課題:予約システムやマーケティングのデジタル化の遅れ
- 対策:モバイルチェックインの導入、デジタルマーケティングの強化、CRMシステムの改善
- 人材確保と育成
- 課題:ホスピタリティ人材の確保難、サービス品質の維持
- 対策:人材育成プログラムの強化、働き方改革の推進、自動化可能な業務の見直し
- 店舗間のサービス品質差の解消
- 課題:全国展開に伴う店舗間のサービス品質のばらつき
- 対策:標準化されたサービスマニュアルの整備、定期的な品質監査、好事例の水平展開
6. 結論:選ばれる理由の統合的理解
総合的に見て、競合や代替手段がある中でドーミーインはなぜ選ばれるのでしょうか。
消費者にとっての選択理由
機能的側面:
- 温泉・大浴場による効率的な疲労回復効果
- ビジネスホテルの利便性と温泉旅館の満足感の両立
- アクセスの良い立地と適切な価格帯
- 「夜鳴きそば」などの無料サービスによる実用的価値
感情的側面:
- 「第二の我が家」のようなアットホームな雰囲気による安心感
- ビジネスホテルながら温泉を楽しめる「ちょっとした贅沢感」
- 「賢い選択をした」という自己肯定感
- 日常から離れた「小さな非日常体験」による満足感
社会的側面:
- 温泉文化という日本の伝統的価値観への参加感
- 「知る人ぞ知る良いホテル」という共有知識
- SNSで共有したくなる体験価値の提供
- リピーターという「特別な顧客」への所属感
市場構造におけるブランドの独自ポジション
ドーミーインは、ビジネスホテル市場において「温泉があるビジネスホテル」という独自のポジションを確立しています。一般的なビジネスホテルと温泉旅館の中間に位置し、両者の良いところを組み合わせた価値提案を行っています。具体的には、ビジネスホテルの機能性・利便性・価格帯と、温泉旅館のくつろぎ・癒し・特別感を融合させた独自のカテゴリーを創造したと言えます。
この「ハイブリッド型」のポジショニングにより、予算に制約があるビジネスパーソンや観光客に対して、「手の届く贅沢」を提供し、従来のビジネスホテルでは満たせなかった「疲れを効率的に癒したい」というジョブに応えています。
競合や代替手段との明確な差別化要素
- 温泉・大浴場という物理的差別化: 最も明確な差別化要素は、ほとんどの施設に完備されている温泉や大浴場です。一般的なビジネスホテルにはない施設であり、物理的・視覚的に明確な違いを生み出しています。
- 「夜鳴きそば」などの独自サービス: 無料で提供される「夜鳴きそば」は、ドーミーインの象徴的なサービスとなっており、宿泊者の記憶に残る独自性の高い体験を創出しています。
- 「第二の我が家」のようなアットホームな雰囲気: 学生寮の運営からスタートした背景を活かし、他のビジネスホテルよりも温かみのある接客と雰囲気を提供しています。
- 地域性を活かしたローカライズ: 全国展開しながらも、各地の特色を活かした朝食メニューや内装で、画一的なチェーンホテルとは異なる体験を提供しています。
- リピーターを重視した運営: 顧客満足度を重視し、リピーターを大切にする姿勢が、口コミやリピート利用を通じた安定した顧客基盤の構築につながっています。
持続的な競争優位性の源泉
ドーミーインの持続的な競争優位性は、以下の要素から生まれています:
- 物理的設備の模倣困難性: 温泉・大浴場の設置には大きな初期投資と専門知識が必要であり、既存のホテルが容易に模倣することは難しい。
- 企業文化とノウハウの蓄積: 学生寮運営から始まった「帰ってきたような感覚」を大切にする企業文化や、リピーターを重視する姿勢は、長年にわたって培われたものであり、短期間での模倣は困難。
- 規模の経済と範囲の経済: 全国90箇所以上の展開による知名度と効率化、複数ブランド展開によるさまざまな顧客ニーズへの対応力。
- 立地戦略の先行者優位性: 好立地への早期出店による優位性は、後発の競合が容易に覆せるものではない。
- 明確なブランドイメージと顧客ロイヤルティ: 「温泉があるビジネスホテル」という明確なイメージと、リピーターの高い割合がもたらす安定した顧客基盤。
7. マーケターへの示唆
我々マーケターはドーミーインの成功例から何を学べるのでしょうか。
再現可能な成功パターン
- 「カテゴリーブレンド戦略」の活用 ドーミーインは、「ビジネスホテル」と「温泉旅館」という2つの異なるカテゴリーを巧みに融合させることで、新たな価値を創造しました。このように、既存の2つ以上のカテゴリーのいいとこ取りをするブレンド戦略は、多くの業界で応用可能です。 実践ステップ:
- 自社商品・サービスが属するカテゴリーを明確に定義する
- 関連する別カテゴリーの魅力的な要素を特定する
- 両者の良い部分を組み合わせた新たな価値提案を設計する
- 「ハイブリッド型」のポジショニングで新たな顧客層を開拓する
- 「小さな特別感」の提供 ドーミーインの「夜鳴きそば」に代表される「小さいけれど記憶に残る特別なサービス」は、全体のコストに大きな影響を与えずに顧客体験を大幅に向上させる効果的な手法です。 実践ステップ:
- 顧客が予想していない「小さな驚き」を特定する
- 運用コストと顧客満足度のバランスを検討する
- 競合が提供していない独自の要素を設計する
- 口コミやSNSで共有されやすい要素を意識する
- 「基本機能×感情価値」の両立 ドーミーインは、ビジネスホテルとしての基本機能を確保しながらも、「帰ってきたような感覚」という感情価値を重視しています。機能的価値と感情的価値の両方を提供することで、より強い顧客ロイヤルティを築いています。 実践ステップ:
- 商品・サービスの基本機能を徹底的に磨く
- 顧客の感情に訴える要素を特定する
- 両者を自然に融合させた体験設計を行う
- スタッフ教育や企業文化にも感情価値を浸透させる
業界・カテゴリーを超えて応用できる原則
- 「当たり前を疑う」発想 ドーミーインは、「ビジネスホテルに温泉はない」という業界の「当たり前」を疑うことから革新を生み出しました。あらゆる業界において、既存の常識や前提を疑い、再定義することで新たな価値を創造できる可能性があります。 チェックポイント:
- 業界の「当たり前」や「常識」とされている要素は何か
- その「当たり前」は顧客にとって本当に最適なのか
- 異なる業界の要素を取り入れることで、どのような新しい価値を提供できるか
- 既存の制約や前提を取り払うことで、何が可能になるか
- 「ジョブの複合解決」アプローチ ドーミーインは、「宿泊」という基本的なジョブだけでなく、「疲れを癒す」「リラックスする」「特別感を味わう」といった複数のジョブを同時に解決しています。一つの商品・サービスで複数のジョブを解決することで、より強い差別化が可能になります。 チェックポイント:
- 顧客の主要なジョブは何か
- 関連する二次的なジョブや隠れたジョブは何か
- それらの複数のジョブを同時に解決する方法はあるか
- 競合は顧客のどのジョブを解決していないか
- 「再訪率を高める」持続的関係構築 ドーミーインは、リピーターを重視した運営により、安定した顧客基盤を構築しています。初回利用者を獲得するためのマーケティングよりも、既存顧客の再訪率を高めることに力を入れるアプローチは多くの業界で応用可能です。 チェックポイント:
- 顧客の再訪率や継続率を測定しているか
- 再訪を促す特別な要素や仕組みがあるか
- 顧客の記憶に残る「シグネチャー体験」を提供しているか
- リピーターに特別な価値や認識を提供しているか
まとめ
ドーミーインが消費者から選ばれ続ける理由について、多角的な分析を行ってきました。その成功の核心は以下のポイントにまとめられます:
- 明確な差別化ポイント: 「ビジネスホテルに温泉という付加価値」という明確なポジショニングにより、競合との差別化に成功している
- 複数のニーズを同時解決: 予算内での宿泊という機能的ニーズと、温泉による癒しという感情的ニーズの両方を満たしている
- 「小さな特別感」の創出: 「夜鳴きそば」などの比較的低コストでありながら強い印象を残すサービスにより、顧客体験を向上させている
- 「カテゴリーブレンド」の実現: ビジネスホテルと温泉旅館という異なるカテゴリーのいいとこ取りにより、新しい価値を創造している
- 感情に訴える体験設計: 「帰ってきたような感覚」というアットホームな雰囲気づくりにより、感情的なつながりを構築している
- リピーターを重視した運営: 一度の利用で終わらせず、リピーターとの長期的な関係構築を重視した戦略を展開している
- 地域特性を活かした展開: 全国一律ではなく、立地に応じた特色を持たせることで、地域との結びつきを強化している
これらの要素が複合的に機能することで、ドーミーインは単なる宿泊施設を超えた独自の価値を提供し、持続的な競争優位性を確立しています。
私たちマーケターは、このドーミーインの事例から「カテゴリーの境界を超える」「当たり前を疑う」「機能と感情の両面から訴求する」といった普遍的な原則を学び、自社のマーケティング戦略に応用していくことができるでしょう。