はじめに
「また新しいブームが生まれたと思ったら、気がついたら消えている...」
マーケターとして働いていると、こんな経験はありませんか?一時的な話題性は作れるものの、その後の持続的な成長につなげることの難しさを痛感する場面は多いはずです。
2005年に日本上陸し、「歌うアイス屋」として一大ブームを巻き起こしたコールド・ストーン・クリーマリー(以下、コールドストーン)は、まさにその典型例と言えるでしょう。六本木ヒルズに1号店をオープンした際は連日長蛇の列ができ、全国34店舗まで拡大しましたが、2025年春には実質的に日本市場から撤退(残り1店舗のみ)という結末を迎えました。
なぜ圧倒的な話題性を誇ったブランドが、わずか20年で市場から姿を消すことになったのか?
本記事では、コールドストーンの日本撤退事例を詳細に分析し、若手マーケターの皆さんが今後のキャリアで活かせる実践的な教訓を抽出していきます。ブームの創出から持続的成長、そして競争優位性の構築まで、現代マーケティングの重要なポイントを事例ベースで学んでいきましょう。
コールドストーン撤退の全体像:20年間の軌跡
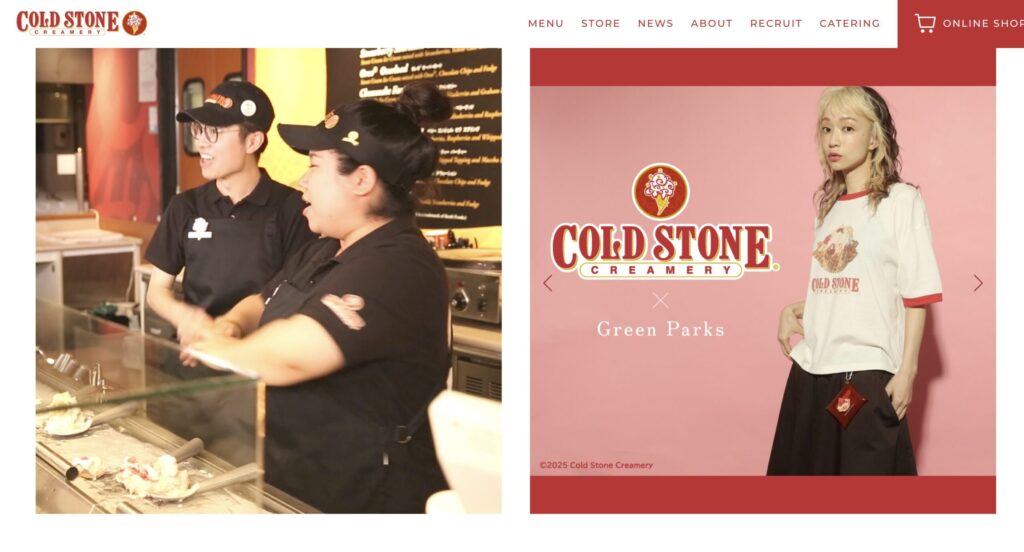
華々しいスタートから急速な拡大期(2005-2012年)
コールドストーンの日本進出は、当初は順風満帆なスタートを切りました。2005年11月の六本木ヒルズ1号店オープンから、以下のような特徴で市場を席巻したのです。
| 期間 | 主な出来事 | 店舗数の推移 |
|---|---|---|
| 2005年11月 | 六本木ヒルズ1号店オープン | 1店舗 |
| 2006-2008年 | 「歌うアイス屋」として大ブーム | 急速拡大 |
| 2012年前後 | 全国展開のピーク | 34店舗(16都道府県) |
成功要因として挙げられるのは:
- エンターテインメント性:マイナス9℃の石板上でアイスクリームにフルーツやナッツを混ぜながら歌うパフォーマンス
- 体験価値の創出:単なる商品購入ではなく、「体験」を提供
- 話題性:メディア露出により知名度急上昇
しかし、この華々しいスタート自体に、後の失敗の種が潜んでいたのです。
成長停滞と経営体制の変化(2012-2019年)
2012年をピークに、コールドストーンの成長は急速に鈍化します。この時期の変化を時系列で整理すると以下のようになります。
| 年 | 主な変化 |
|---|---|
| 2014年 | ホットランド(銀だこ運営会社)が数億円規模で買収 |
| 2015年 | ワゴン車や催事出店「コールドストーン アイスキャンディ」開始 |
| 2016年 | 不採算店の閉店開始 |
| 2018年 | 売上高約22億円に対し最終赤字約3,900万円を計上 |
| 2019年 | ホットランドが吸収合併を実施 |
注目すべきは、買収後の戦略転換です。ホットランドは銀だこの夏場の売上減少を補完する目的でコールドストーンを買収しましたが、これは「季節補完」という限定的な役割に位置づけられたことを意味します。
急速な縮小と実質的撤退(2020-2025年)
2020年以降、新型コロナウイルスの影響もあり、コールドストーンは急速な店舗閉鎖を余儀なくされました。
このような急速な撤退劇の背景には、どのような戦略的な問題があったのでしょうか?
撤退の根本原因:マーケティング戦略の視点から
戦略的ミス1:初期戦略の誤算と非現実的な成長目標
コールドストーンの最初の大きな誤算は、市場規模とポテンシャルの過大評価にありました。
具体的な問題点:
| 計画 | 実績 | ギャップの要因 |
|---|---|---|
| 2009年までに150店舗体制 | ピーク時34店舗(約2割) | ・大型店舗を出せる立地の限界 ・アイスクリーム専門店への需要の過大評価 |
澤田貴司氏(ファミリーマートやユニクロ経営に携わった投資ファンド代表)が主導したこの拡大戦略は、「コンセプトの独自性」に過度に依存していました。しかし、独自性だけでは持続的な成長は困難だったのです。
これは現代のマーケターにとって重要な教訓です。新しいコンセプトで市場参入する際は、以下の点を慎重に検討する必要があります:
- 市場の天井を正確に把握する
- 模倣可能性を考慮した差別化戦略を立てる
- 初期の話題性と長期的な需要を区別して予測する
戦略的ミス2:ホットランド傘下での方向性の混乱
2014年のホットランド買収後、コールドストーンの戦略は大きく迷走しました。
戦略転換の内容と問題点:
| 従来戦略 | 新戦略 | 問題点 |
|---|---|---|
| 店舗での体験価値提供 | 小売・外販事業への軸足移動 | ブランドアイデンティティの希薄化 |
| 「歌うアイス屋」 | 「コールドストーン アイスキャンディ」 | 消費者の認知との乖離 |
| プレミアム体験 | 手頃な価格帯での商品展開 | ブランドポジショニングの混乱 |
この戦略転換は一時的には成果を上げました。アイスキャンディ事業は全国約60箇所で展開され、1本300~500円程度の価格で若年層にもアピールしました。しかし、本来のブランドコンセプトとの整合性を欠いた展開となり、長期的なブランド価値の毀損につながったのです。
戦略的ミス3:収益構造の根本的な問題
コールドストーンのビジネスモデルには、構造的な収益性の課題がありました。
コスト構造の分析:
| コスト項目 | 内容 | 問題点 |
|---|---|---|
| 人件費 | パフォーマンススタッフの配置・トレーニング | 一定以上のスタッフ配置が必須 |
| 店舗コスト | 平均35坪の大型店舗 | 広い店舗面積に見合う集客が困難 |
| 運営費 | 混雑時以外のパフォーマンス人員の遊休化 | 非効率な人員配置 |
客単価は600~800円前後と高めでしたが、これらのコスト構造により、構造的に利益を出すのが困難な状態が続きました。2018年時点でも赤字が解消できなかったことからも、この問題の深刻さがうかがえます。
市場環境と競合分析:外部要因の影響
競合優位性の喪失:サーティワンとの比較
コールドストーンが苦戦する一方で、競合のサーティワンアイスクリーム(B-R31)は安定した成長を続けました。
競合比較分析:
| 比較項目 | コールドストーン | サーティワン |
|---|---|---|
| 上陸年 | 2005年 | 1974年 |
| 店舗数(ピーク時) | 34店舗 | 約1,000店舗 |
| ビジネスモデル | 直営中心の大型店舗 | フランチャイズ中心 |
| ブランド戦略 | パフォーマンス特化 | 幅広い年齢層への訴求 |
| 2024年業績 | 実質撤退 | 営業利益約23億6,300万円(前期比30%増) |
サーティワンの成功要因は以下の通りです:
- ネットワーク効果の活用:1,000店舗規模による認知度の維持
- 継続的な商品開発:季節ごとの新フレーバー投入
- 効果的なプロモーション:「31日割引」「お試しスプーン無料」などの施策
- ターゲット層の拡大:子供から大人まで幅広い顧客層
デザートトレンドの多様化への対応遅れ
2000年代後半以降、日本のデザート市場では次々と新たなブームが生まれました。
デザートトレンドの変遷:
特に2017年に創業した「ロールアイスクリームファクトリー」は、原宿で最大7時間待ちの行列を作るブームとなりました。冷えた鉄板上に液状アイスを薄く伸ばしてクルクルと巻き取るというライブ感は、コールドストーンと類似のポジションを狙ったものでした。
コールドストーンは、このようなトレンドの変化に対応する柔軟性を欠いていたのです。
消費者行動の変化:購買チャネルの多様化
市場環境の変化として見逃せないのが、消費者の購買チャネルの変化です。
購買チャネルの変化:
| 変化の内容 | 影響 |
|---|---|
| コンビニでのプレミアムアイス拡充 | 「アイスはお店で食べるもの」から「買って家で食べるもの」へ |
| ハーゲンダッツや明治エッセルなどの高級市販アイス | 手軽で美味しい選択肢の増加 |
| ECサイトでの冷凍食品購入の一般化 | 専門店に足を運ぶ動機の減少 |
ホットランドも2016年時点で「コンビニ・スーパーなどで売る高級アイスの急増により既存店が苦戦した」と分析しており、この変化の影響を認めています。
消費者心理とブランド戦略の失敗
パフォーマンスへの賛否両論
コールドストーンの最大の特徴である「店員の歌うパフォーマンス」は、時間の経過とともに日本人消費者には合う人と合わない人が明確に分かれる要素となりました。
パフォーマンスに対する消費者反応:
| ポジティブ反応 | ネガティブ反応 |
|---|---|
| ・エンターテインメント性を評価 ・SNS映えする体験 ・非日常感を楽しむ | ・「日本人は恥ずかしがり屋だから居心地が悪い」 ・「放っておいて静かに食べたい」 ・一人客には気まずい |
実際、原宿店では1人来店の客に対し「歌ってもよろしいですか?」とスタッフが断りを入れる配慮をしていましたが、歌自体を断るのも互いに気まずくなるという構造的な問題がありました。
ブームの短命化と飽きの問題
日本の若年層消費者は流行に敏感である反面、「一度体験したら満足して次へ移る」傾向も強いのが特徴です。
ブームサイクルの分析:
| フェーズ | 期間 | 消費者行動 |
|---|---|---|
| 導入期 | 2005-2006年 | メディア話題化、行列形成 |
| 成長期 | 2007-2008年 | 全国展開、模倣体験 |
| 成熟期 | 2009-2012年 | 「派手なパフォーマンスにも飽きた」 |
| 衰退期 | 2013年以降 | 日常的なリピート利用に結び付かず |
事実、原宿店閉店のニュースが報じられると久々に来店者が殺到したものの、平常時は閑散としていたことが指摘されていました。これは「閉店の報に接するまで思い出す機会がなかった」層が多かったことを示しており、日常的なリピート利用には結び付いていなかったのです。
嗜好の多様化と健康志向への対応不足
アイスクリーム自体の嗜好にも変化が生じました。
消費者嗜好の変化:
| 従来の嗜好 | 変化後の嗜好 |
|---|---|
| ボリューム感重視 | 少量で色々な味を楽しみたい |
| 濃厚なプレミアムアイス | 甘すぎるものは控えたい |
| 大容量サイズ | 健康志向(低カロリー等) |
サーティワンがレギュラーサイズより小さいキッズサイズの用意やファミリー層への対応、低カロリーフレーバーの投入など健康志向にも対応を見せているのに対し、コールドストーンは基本サイズがやや大きめで価格も高いため、「重たい」「高カロリー」という印象から頻繁な利用を避けられた可能性があります。
マーケターが学ぶべき5つの重要な教訓
教訓1:独自性だけでは持続的成長は困難
問題の本質: コールドストーンは「歌いながら混ぜる」という独自コンセプトに過度に依存し、環境変化への適応力を欠いていました。
現代マーケターへの示唆:
- 独自性は入り口であり、ゴールではない
- 独自性は顧客が求めることが必須
- 模倣されることを前提とした多層的な差別化戦略が必要
- コンセプトへの過度な依存は事業モデルの柔軟性を奪う
実践的な対策:
| フェーズ | 対策内容 |
|---|---|
| コンセプト設計時 | 模倣困難性の高い要素(ネットワーク効果、データ蓄積等)を組み込む |
| 成長期 | 複数の差別化ポイントを段階的に構築 |
| 成熟期 | 新たな価値創出のための事業モデル進化 |
教訓2:スケールメリットの軽視は致命的
問題の本質: 大型店舗を前提とした出店モデルは早々に限界を迎え、フランチャイズ展開による急拡大も実現しませんでした。
現代マーケターへの示唆:
- 初期段階からスケーラビリティを考慮した事業設計が重要
- 広告宣伝効果や物流効率といったスケールメリットの確保
- 地域密着 vs 全国展開の戦略選択を明確にする
教訓3:収益構造の健全性確保
問題の本質: パフォーマンススタッフの配置、大型店舗の維持費用など、構造的に高コストなビジネスモデルでした。
実践的なチェックポイント:
教訓4:ブランド再構築の難しさ
問題の本質: 外販事業や新商品開発は本来の店内体験型ブランドと乖離し、一貫したブランドイメージの維持が困難でした。
現代マーケターへの示唆:
- ブランド拡張は慎重に。コアアイデンティティとの整合性を最優先に
- 短期的な売上拡大と長期的なブランド価値のバランス
- 異なる事業領域への進出時は別ブランド化も検討
教訓5:環境変化への対応スピード
問題の本質: デザートトレンドの変化、消費者の購買チャネルの変化、健康志向の高まりなどに対する対応が後手に回りました。
実践的な対策フレームワーク:
| 監視領域 | チェック項目 | 対応アクション |
|---|---|---|
| 競合動向 | 新規参入企業、模倣サービス | 差別化戦略の強化 |
| 消費者行動 | 購買チャネル、嗜好変化 | 顧客接点の多様化 |
| 社会トレンド | 健康志向、環境意識 | 商品・サービスの進化 |
| 技術変化 | デジタル化、自動化 | オペレーション効率化 |
成功事例との比較:なぜサーティワンは生き残ったのか
サーティワンが長期的に成功し続けている要因を分析することで、コールドストーンとの違いをより明確に理解できます。
サーティワンの成功要因分析
1. ネットワーク効果の最大化
| 戦略要素 | サーティワン | コールドストーン |
|---|---|---|
| 店舗展開戦略 | フランチャイズ中心で1,000店舗 | 直営中心で最大34店舗 |
| 認知度構築 | 全国規模での継続的露出 | 限定的な地域での話題性 |
| スケールメリット | 広告費効率、仕入れコストの最適化 | スケールメリットを享受できず |
2. 継続的なイノベーション
サーティワンは小さな改善と新機軸を継続的に投入することで、ブランドの新鮮さを保ち続けました。
3. ターゲット層の拡大戦略
| ターゲット層 | アプローチ方法 |
|---|---|
| 子供・ファミリー | キッズサイズ、キャラクターコラボ |
| 若年層 | SNS映えする商品、限定フレーバー |
| 大人 | プレミアムライン、季節感のある商品 |
| 健康志向層 | 低カロリー商品、フルーツ系フレーバー |
コールドストーンが学べた戦略
もしコールドストーンが以下の戦略を取っていたら、結果は変わっていたかもしれません:
仮想的な改善戦略:
| 改善領域 | 具体的施策 |
|---|---|
| 事業モデル | フランチャイズ化による急速な店舗拡大 |
| 商品戦略 | パフォーマンス以外の差別化要素の追加 |
| ブランド戦略 | 体験型から商品力重視への段階的移行 |
| マーケティング | 継続的なコラボ企画、リピート促進施策 |
| 収益改善 | 小型店舗フォーマットの開発 |
現代マーケターのための実践的フレームワーク
コールドストーンの事例から導き出された教訓を、実際のマーケティング業務で活用できるフレームワークとして整理します。
持続的成長のための戦略チェックリスト
Phase 1: コンセプト設計段階
| チェック項目 | 評価基準 | 対策例 |
|---|---|---|
| 顧客ニーズ | コンセプトは顧客が求めるものか | デプスインタビュー、アンケート |
| 模倣困難性 | 真似されにくい要素があるか | ネットワーク効果、データ蓄積、特許技術 |
| スケーラビリティ | 拡大可能なモデルか | フランチャイズ化、デジタル化 |
| 収益構造 | 健全な利益率を確保できるか | 変動費比率の最適化 |
Phase 2: 成長段階
| チェック項目 | 評価基準 | 対策例 |
|---|---|---|
| 競合対応 | 差別化ポイントは複数あるか | 機能、感情、社会的価値の多層化 |
| 顧客基盤 | リピート率は健全か | ロイヤルティプログラム |
| ブランド認知 | 継続的な認知維持ができているか | 定期的なPR、コラボ企画 |
Phase 3: 成熟・転換段階
| チェック項目 | 評価基準 | 対策例 |
|---|---|---|
| 環境適応 | トレンド変化への対応は迅速か | 顧客行動モニタリング体制 |
| 事業進化 | 新たな価値創出ができているか | 隣接市場への展開 |
| ブランド一貫性 | 拡張戦略は一貫しているか | ブランドガイドライン |
リスク早期発見のためのKPI設計
ブランド健全性の監視指標:
| KPI分類 | 具体的指標 | 警戒水準 | 対応アクション |
|---|---|---|---|
| 市場シェア | カテゴリー内シェア | 前年同期比5%減 | 競合分析、差別化強化 |
| 顧客行動 | リピート購入率 | 30%未満 | 顧客体験の見直し |
| ブランド認知 | 純粋想起率 | 前年比10%減 | PR戦略の見直し |
| 収益性 | 店舗別営業利益率 | 業界平均未満 | オペレーション改善 |
環境変化対応のための情報収集システム
監視すべき情報源と頻度:
| 情報分類 | 情報源 | 監視頻度 | 責任者 |
|---|---|---|---|
| 競合動向 | 業界ニュース、展示会 | 週次 | 競合分析チーム |
| 消費者行動 | SNS、レビューサイト | 日次 | カスタマーサクセス |
| 社会トレンド | トレンド調査、調査会社 | 月次 | マーケティング企画 |
| 技術動向 | 技術ニュース、特許情報 | 月次 | 事業開発チーム |
まとめ
コールドストーンの日本撤退事例は、現代のマーケターにとって非常に重要な教訓を含んでいます。一時的な話題性やブームの創出は可能でも、持続的な成長を実現するためには、戦略的な思考と継続的な改善が不可欠です。
Key Takeaways:
- 独自性は入り口であり、ゴールではない:模倣されることを前提とした多層的な差別化戦略が必要
- スケールメリットの確保は生存の前提:初期段階からスケーラビリティを考慮した事業設計が重要
- 収益構造の健全性は妥協できない:構造的な高コストは長期的に事業を圧迫する
- ブランド一貫性の維持は拡張時の最重要課題:短期的売上と長期的ブランド価値のバランスが肝要
- 環境変化への適応スピードが競争優位を決定する:継続的な市場監視と迅速な対応体制の構築が必須
マーケターとして、私たちは常に「なぜこのブランドは選ばれ続けているのか」「なぜこのブランドは選ばれなくなったのか」を深く分析し、自社の戦略に活かしていく必要があります。コールドストーンの事例は、その思考のプロセスを鍛える格好の材料と言えるでしょう。
現在進行形で変化し続ける市場環境において、持続的な成長を実現するブランドを築き上げるために、この分析から得られた教訓を日々の実践に活かしていきましょう。


