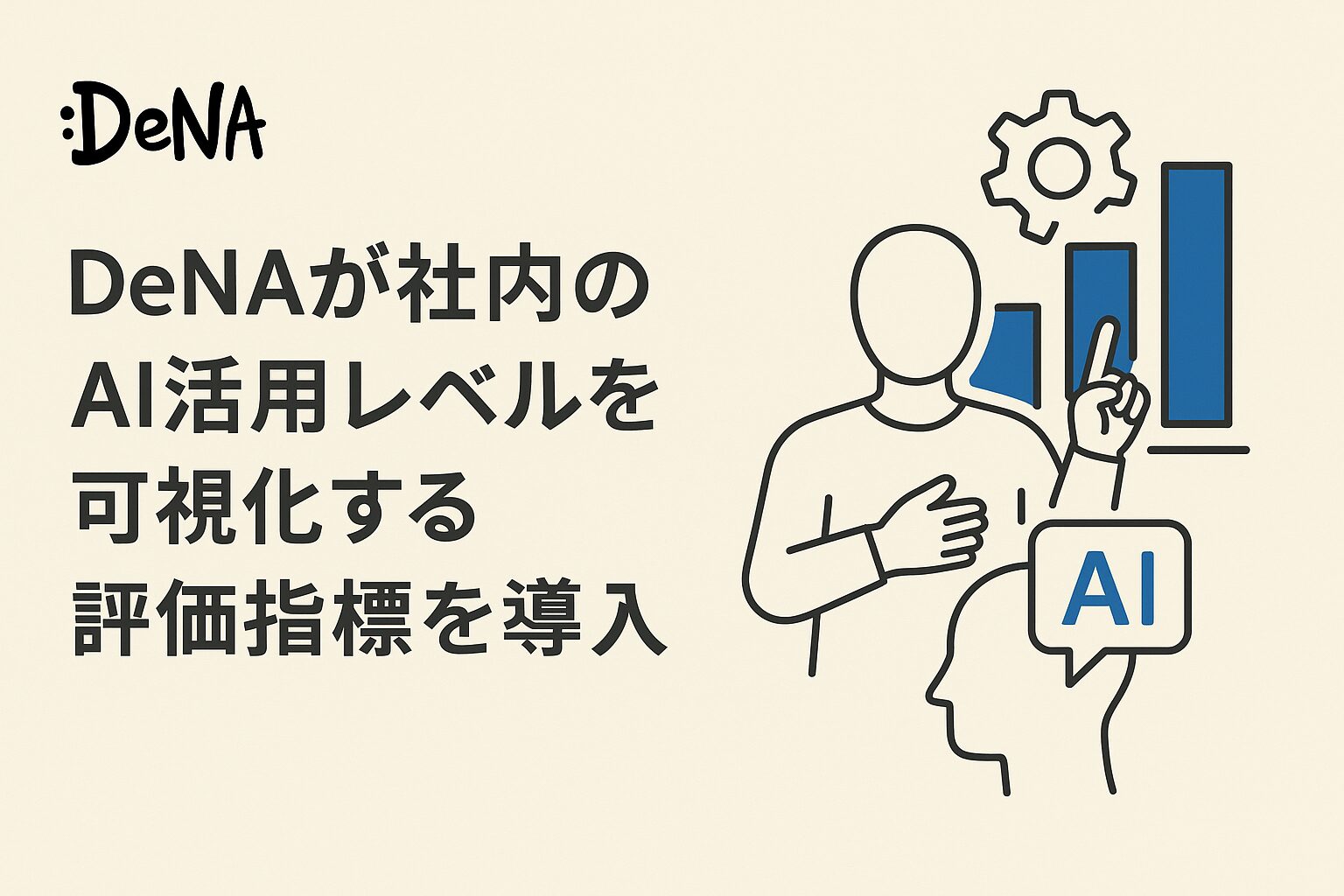はじめに:多くの企業が抱えるAI活用の見えない課題
「うちの会社でもAIを活用しよう」そんな掛け声は聞こえるものの、実際にどれだけの社員がAIを使いこなせているのか、組織全体のAI活用レベルはどの程度なのか、明確に把握できている企業はどれくらいあるでしょうか。
多くの企業では次のような課題を抱えています。一部の先進的な社員だけがAIツールを使っていて、全社的な底上げができていない。AI導入の投資対効果が見えにくく、経営層への説明が困難。どの部署がどのレベルでAIを活用できているのか実態が分からない。社員のAIスキル向上をどう支援すべきか方針が立てられない。
こうした課題に対して、ゲーム大手のDeNA(株式会社ディー・エヌ・エー)が2025年8月に導入した「DARS(DeNA AI Readiness Score)」という評価指標が注目を集めています。この指標は、全社員のAI活用レベルを定量的に測定し、組織全体のAI成熟度を可視化する画期的な仕組みです。
今回は、DARSの詳細な内容を分析し、他の企業がこの取り組みから何を学び、どう活かせるかを解説してみます。
出典:DeNA プレスリリース
DARSとは:全社のAI活用レベルを測る革新的指標
DARSの基本概念
DARS(DeNA AI Readiness Score)は、従業員一人ひとりのAI活用レベルを測る「個人レベル」と、部署・チーム単位のAI活用レベルを測る「組織レベル」の2つの側面で構成された評価指標です。
この指標の特徴は、半期の評価サイクルごとに可視化していく点です。つまり、定期的にAI活用状況をチェックし、継続的な改善を図る仕組みが組み込まれています。
また、DARSは現状では個人の人事評価には直結させず、個人に期待される役割や成果を明確に示すためのグレード(等級)における推奨要素として位置づけられています。これにより、社員が過度なプレッシャーを感じることなく、自然にAIスキル向上に取り組める環境を作り出しているのもポイントです。
DeNAがDARSを導入した背景
DeNAは2025年2月5日のイベント「DeNA × AI Day || DeNA TechCon 2025」で、全社を挙げてAI活用を推進する「AIオールイン」宣言を公表しました。この宣言では「全社の生産性向上」「既存事業の競争力強化」「AIによる新規事業の創出とグロース」の3つの柱を掲げています。
しかし、AIネイティブな企業への変革を加速させるためには、従業員や組織がAIを日常的に活用し、その能力を最大限に引き出すことが不可欠です。現状では一人ひとりのAI活用状況やスキルレベルが把握しにくいという課題がありました。
そこで、従業員や組織のAI活用レベルを客観的に評価・可視化することで、従業員全体のAI活用レベルを底上げし、より強固なAIネイティブな組織を構築するため、DARSの導入を決定したのです。
個人レベル評価:5段階でAIスキルを明確化
開発者と非開発者の分類
DARSの個人レベル評価では、まず従業員を開発者(開発を主業務とするエンジニア)と非開発者(ビジネス/クリエイティブ職/マネージャー等)に分類します。
これは非常に重要な観点で、エンジニアとビジネス職では求められるAIスキルが根本的に異なるためです。エンジニアにはコード生成やプログラミング支援でのAI活用が求められる一方、ビジネス職には文書作成やデータ分析、業務プロセス改善でのAI活用が重要になります。
5段階のレベル設定
個人レベルは、AI活用の習熟度に応じてレベル1から5までの段階を設定しています。
| レベル | 非開発者の状態 | 開発者の状態 |
|---|---|---|
| レベル1 | 基礎的な知識や利用習慣がある | AIを対話的にコード生成や情報収集を行い、基本的なプロンプティングでAIを活用 |
| レベル2 | 日常的にAI活用をし、仕事でかかる時間を短縮している | AIをエディタ/IDEに統合し、自分でコード解説や生成を活用、プロンプトを意識 |
| レベル3 | 社内展開のAI利用において各業務改善のために利用している | 複数のAIエージェントを管理し、作業の一部を代行、多様なチェーンを活用 |
| レベル4 | 社内共有のAI利用の応用や仕組み作りを牽引している | スタンドアロン型のエージェントを選択できるチームのメンバーとして動き、専門一般のAIエージェントを管理・発見する |
| レベル5 | 目標だけでなく他部の生産性向上を推進している | AI Platform、フレームワーク、ツール群をオーケストレーションしエージェントを管理する、エコシステムを管理 |
この段階的な設定により、社員は自分の現在地を把握し、次のレベルに向けた具体的な行動目標を設定できます。
組織レベル評価:部署・チーム単位のAI成熟度測定
組織レベルの5段階評価
組織レベルでは、組織のAI活用フェーズに応じてレベル1から5までの段階を設定しています。
| レベル | 状態イメージ | 定量要件 |
|---|---|---|
| レベル1 | 組織の中でAIを試し始めている段階 | 5割以上のメンバーが個人レベル1以上 |
| レベル2 | 継続としてAI活用が日常的にされている段階 | 5割以上のメンバーが個人レベル2以上 |
| レベル3 | AI活用をリードする人が存在し、継続的な改善・活用を進め組織の活用レベルが向上している段階 | 7割以上のメンバーが個人レベル2以上、かつ3割以上がレベル3以上とレベル1を下げる |
| レベル4 | AIによって既存業務のやり方が変わり組織課題にもそれが対応できる段階 | 5割以上がレベル3以上とレベル2、かつ3割以上がレベル4以上とレベル1を上げる |
| レベル5 | AIだからこそ可能な戦略が実行されている段階 | 7割以上がレベル3以上とレベル2、かつ3割以上がレベル4以上設立以上、個人レベル5以上が1名以上存在 |
この組織レベル評価の優れた点は、個人レベルの分布に基づいた定量的な基準を設けていることです。これにより、組織のAI成熟度を客観的に判断できます。
DeNAの具体的な目標設定
短期目標:2025年度末までの全社レベル2達成
DeNAは協業などやむを得ない事情がある一部の組織を除き、2025年度末までに全組織がDARSの組織レベル2に到達することを目標としています。
組織レベル2は「継続としてAI活用が日常的にされている段階」を意味し、5割以上のメンバーが個人レベル2以上(日常的にAI活用をし、仕事でかかる時間を短縮している状態)に達する必要があります。
中長期目標:職種別の専門性向上
中長期的には、より具体的で職種別の目標を設定しています。
エンジニア向けの目標
- AI導入による生産性向上
- AIエージェントの活用
- LLMOps(Large Language Model Operations)への精通
エンジニア以外の目標
- 日常的なAI活用の定着
- 定型業務のプロセス改善
- AIによる高度な課題解決能力の確立
この職種別のアプローチは、それぞれの業務特性に応じたAI活用を促進する上で非常に効果的です。
他企業が学べる5つの重要ポイント
この先進的な取り組みをぜひ多くの企業が真似して欲しいと考えております。改めてポイントを整理します。
1. 評価と人事制度の分離
DARSの最も画期的な特徴の一つは、AI活用スキルの評価を直接的な人事評価から切り離していることです。これにより、社員は失敗を恐れることなくAIツールを試行錯誤できる環境が生まれます。
多くの企業では新しいスキルの習得を人事評価に直結させがちですが、これは逆効果になる場合があります。AIのような新しい技術では、試行錯誤を通じた学習が重要であり、失敗を許容する文化が必要不可欠です。
2. 段階的かつ具体的なレベル設定
DARSのレベル設定は、各段階で何ができるようになる必要があるかが具体的に定義されています。これにより、社員は現在の自分の位置を把握し、次のレベルに向けた明確な行動指針を得ることができます。
曖昧な「AI活用ができる」ではなく、「日常的にAI活用をし、仕事でかかる時間を短縮している」といった具体的な状態定義が、実践的なスキル向上を促進します。
3. 個人と組織の両面からの評価
個人のスキルだけでなく、組織全体のAI活用レベルも同時に測定することで、個人の成長と組織の変革を連動させています。これにより、優秀な個人だけでなく、チーム全体の底上げが図れます。
4. 職種別のアプローチ
開発者と非開発者で異なる評価基準を設けることで、それぞれの職種に適したAI活用スキルの向上を促しています。一律の基準ではなく、職種の特性を考慮した評価制度は、より実践的で効果的です。
5. 継続的な改善サイクルの組み込み
半期ごとの評価サイクルにより、定期的な振り返りと改善のメカニズムが組み込まれています。これにより、AI技術の急速な進歩に対応しながら、継続的にスキル向上を図ることができます。
導入時の実践的な注意点とプロセス
段階的導入の重要性
DARSのような包括的な評価制度を一度に導入するのは困難です。以下のような段階的なアプローチが推奨されます。
第1段階:現状把握とパイロット実施 まず、特定の部署や職種でパイロット実施を行い、評価基準や運用方法を検証します。この段階では、社員からのフィードバックを積極的に収集し、制度の改善点を洗い出します。
第2段階:評価基準の調整と拡大 パイロット実施の結果を踏まえ、自社の業務特性に合わせて評価基準を調整します。その後、対象部署を段階的に拡大していきます。
第3段階:全社展開と継続改善 全社展開後も、定期的に制度の見直しを行い、AI技術の進歩や業務の変化に応じて評価基準をアップデートし続けます。
学習支援体制の整備
評価制度だけでなく、社員のスキル向上を支援する仕組みも同時に整備する必要があります。
DeNAでは、eラーニングやエンジニア、ビジネス職問わず有志の勉強会を多数開催し、それらの情報を集約した社内の学習ポータルを整備する予定としています。
効果的な学習支援の要素
- 職種別の学習コンテンツ
- 実践的なワークショップやハンズオン
- 社内のAI活用事例共有
- メンターやエキスパートによるサポート
- 最新AI技術の情報提供
経営層のコミットメントの確保
AI活用推進には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。DeNAの「AIオールイン」宣言のように、全社を挙げてAI活用に取り組む姿勢を明確に示すことが重要です。
これには、予算の確保、人材への投資、組織体制の整備などが含まれます。評価制度の導入だけでなく、AI活用を支援するためのインフラ整備も同時に進める必要があります。
業界別応用のヒント
製造業での応用
製造業では、生産効率の向上、品質管理、予知保全などの分野でAI活用が期待されます。DARSを参考にした評価制度では、以下のような職種別アプローチが考えられます。
生産技術職
- 生産データの分析とAIを活用した最適化
- 予知保全システムの構築と運用
- 品質管理でのAI技術活用
営業・企画職
- 需要予測でのAI活用
- 顧客データ分析による営業戦略立案
- AIツールを活用した業務効率化
サービス業での応用
サービス業では、顧客体験の向上、業務自動化、パーソナライゼーションなどの分野でAI活用が重要です。
接客・営業職
- チャットボットや音声認識技術の活用
- 顧客データに基づくパーソナライズされたサービス提供
- AIを活用した顧客対応の効率化
バックオフィス職
- 事務処理の自動化
- データ分析による業務改善
- AIツールを活用した文書作成・管理
金融業での応用
金融業では、リスク管理、不正検知、投資アドバイスなどの分野でAI活用が進んでいます。
リスク管理職
- AIモデルを活用したリスク評価
- 不正検知システムの構築と運用
- 規制対応でのAI技術活用
営業・商品企画職
- 顧客の投資傾向分析
- AIを活用した商品推奨
- マーケティングでのデータ活用
成功のための組織文化づくり
失敗を許容する文化の醸成
AI活用スキルの向上には、試行錯誤を通じた学習が不可欠です。そのため、失敗を許容し、学習を奨励する組織文化の醸成が重要です。
DARSが人事評価から切り離されているのも、この考え方に基づいています。社員が安心してAIツールを試し、失敗から学べる環境を作ることが、長期的なスキル向上につながります。
知識共有の促進
AI活用の成功事例や失敗事例を組織内で積極的に共有することで、全体のレベル向上を図ります。これには、以下のような仕組みが効果的です。
- 定期的な事例共有会の開催
- 社内WikiやポータルサイトでのKnowledge管理
- メンターバディ制度の導入
- 部署を超えたプロジェクトでの協働
継続的な学習の習慣化
AI技術は急速に進歩しているため、継続的な学習が重要です。組織として学習を支援し、個人の成長を促進する仕組みを整備します。
- 学習時間の確保(20%ルールなど)
- 外部研修や資格取得の支援
- 社内勉強会の活性化
- 最新技術情報の定期共有
測定と改善のPDCAサイクル
定期的な評価とフィードバック
DARSでは半期ごとの評価サイクルを設けていますが、より細かい頻度でのチェックインも重要です。
月次レビュー
- 個人の学習進捗確認
- 課題の早期発見と対応
- 短期目標の設定と調整
四半期レビュー
- 部署・チーム単位でのAI活用状況確認
- 成功事例と課題の共有
- 次四半期の戦略検討
半期レビュー
- 全社的なAI活用レベルの評価
- 制度の見直しと改善
- 長期目標の確認と調整
データドリブンな改善
評価結果は定量的なデータとして蓄積し、分析を通じて継続的な改善を図ります。
分析すべき指標
- 各レベルの人数分布と推移
- 職種別・部署別のAI活用レベル
- 研修参加率と効果測定
- AI活用による業務効率化の成果
これらのデータを基に、研修内容の改善、評価基準の調整、支援体制の強化などを行います。
まとめ:key takeaways
DeNAのDARSから学べる企業のAI活用推進に関する重要なポイントを以下にまとめます。
AI活用評価制度の設計では、評価と人事制度を分離することで、社員が安心してスキル向上に取り組める環境を作ることが重要です。失敗を恐れずに新しい技術を試行錯誤できる文化の醸成が、長期的な成功につながります。
個人レベルと組織レベルの両面から評価することで、個人の成長と組織の変革を同時に推進できます。優秀な個人だけでなく、チーム全体の底上げを図ることが、真のAIネイティブ組織への変革を実現します。
職種別のアプローチにより、それぞれの業務特性に適したAI活用スキルの向上を促すことができます。一律の基準ではなく、職種の特性を考慮した評価制度が、より実践的で効果的な結果をもたらします。
段階的で具体的なレベル設定により、社員は現在の位置を把握し、次のステップに向けた明確な行動指針を得ることができます。曖昧な目標ではなく、具体的な状態定義が実践的なスキル向上を促進します。
継続的な改善サイクルを組み込むことで、AI技術の急速な進歩に対応しながら、持続的にスキル向上を図ることができます。定期的な振り返りと改善のメカニズムが、制度の効果を最大化します。
学習支援体制の整備と経営層のコミットメントが、AI活用推進の成功には不可欠です。評価制度だけでなく、社員の成長を支援する仕組みと組織としての強い意志が、変革を加速させます。
これらのポイントを参考に、各企業の特性に合わせてAI活用推進の仕組みを構築することで、真にAIネイティブな組織への変革を実現できるでしょう。