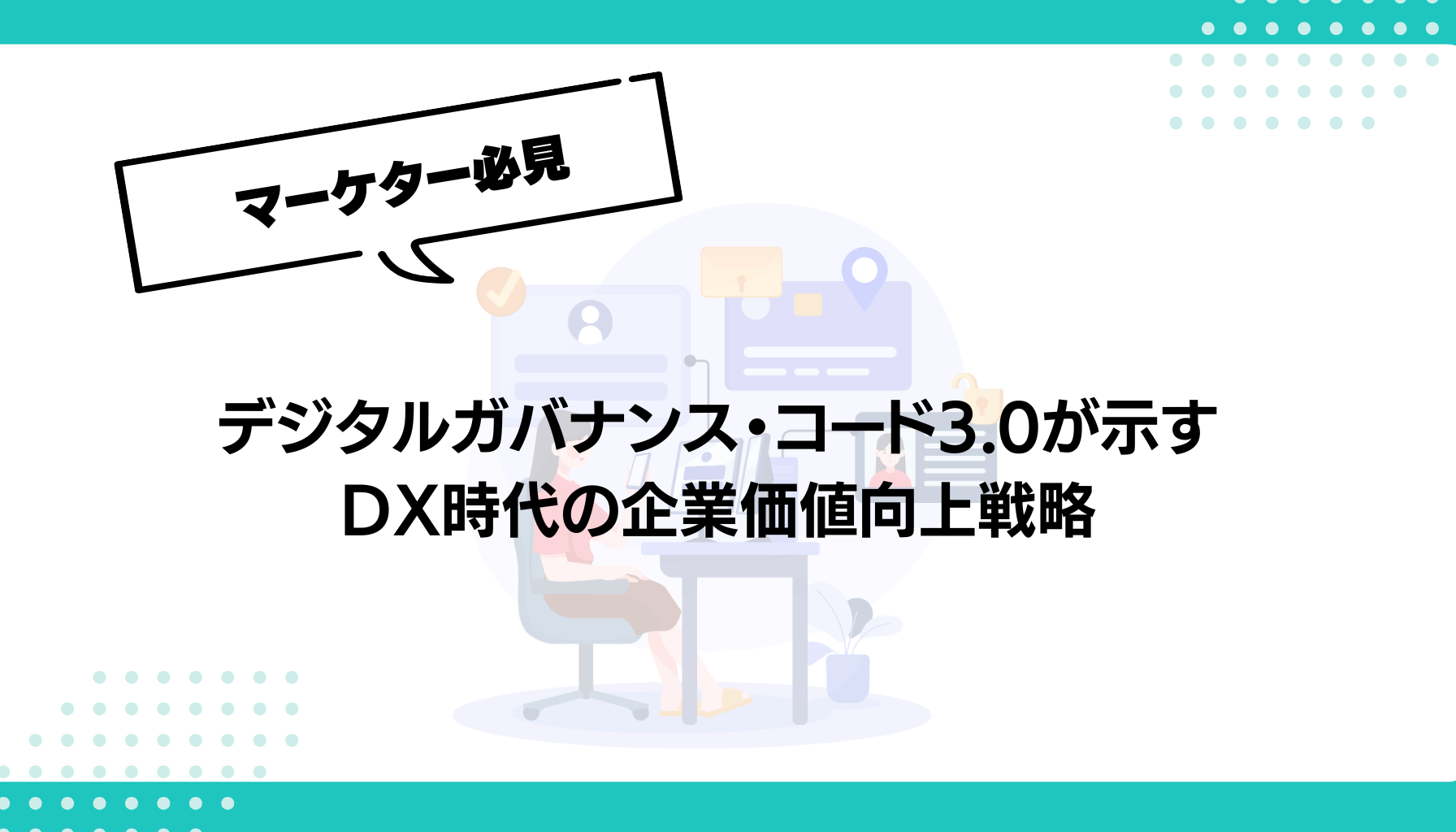はじめに
「うちの会社もDXを進めなければ...」そんな声をよく聞くようになりましたが、実際にどこから手をつければいいのか、どんな基準で進めればいいのか迷っている企業も多いのではないでしょうか。
特にマーケターの皆さんは、デジタル技術を活用したマーケティング施策の重要性を日々感じながらも、全社的なDX戦略との連携がうまく取れていないという課題を抱えているかもしれません。また、経営陣からDXの成果を求められても、「具体的に何をどう評価すればいいのかわからない」という悩みもあるでしょう。
そんな中、2024年9月に改訂された「デジタルガバナンス・コード3.0」は、企業がDXを通じて価値創造を実現するための明確な指針を示しています。この新しいガイドラインは、単なるIT化ではなく、真の意味でのデジタルトランスフォーメーションによる企業価値向上を目指すための道筋を具体的に示したものです。
本記事では、デジタルガバナンス・コード3.0の内容を詳しく解説し、マーケターとして知っておくべきポイントや、自社のDX戦略にどう活かせるかを具体的にお伝えします。これを読めば、DXの全体像が見えて、自分の業務がどう企業価値向上につながるかが理解できるはずです。
デジタルガバナンス・コード3.0とは何か
デジタルガバナンス・コード3.0は、経済産業省が策定した「企業がDXを通じて価値創造を実現するためのガイドライン」です。正式名称は「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」で、2024年9月に最新版が公開されました。
2024年9月最新版:こちら
このコードは、単なる推奨事項ではありません。実は、DX認定制度やDX銘柄の選定基準としても活用されており、投資家や金融機関からの評価にも直結する重要な指標となっています。
なぜバージョン3.0になったのか
デジタルガバナンス・コードは、時代の変化に合わせて進化してきました。3.0への改訂では、特に以下の変化に対応しています。
| 変化の背景 | 対応内容 |
|---|---|
| 生成AI技術の急速な進展 | 最新デジタル技術への対応強化 |
| データ活用の重要性増大 | データ経営・データ連携の重視 |
| 人材不足の深刻化 | デジタル人材育成の具体的指針 |
| サイバー攻撃の高度化 | セキュリティ対策の強化 |
| 投資家の関心増大 | ステークホルダー対話の充実 |
3.0で追加された重要なポイント
今回の改訂で特に注目すべきは、「DX経営に求められる3つの視点」が新たに追加されたことです。これは「人材版伊藤レポート2.0」の3つの視点と整合させたもので、DXと人的資本経営を一体的に進める重要性を示しています。
DXが企業価値向上に与える真のインパクト
ここで改めて考えてみましょう。なぜ今、これほどまでにDXが重要視されているのでしょうか。デジタルガバナンス・コード3.0では、DXがもたらす具体的なメリットを明確に示しています。
DXによる4つの価値創造
| メリット | 具体的な効果 | マーケターへの影響 |
|---|---|---|
| ビジネスモデル変革 | 既存ビジネスの深化と新規事業創出 | 新たな顧客接点とマーケティング機会の創出 |
| 人的資本向上 | 生産性向上、従業員エンゲージメント向上 | より創造的なマーケティング活動への集中 |
| リスク最小化 | サイバーセキュリティ対策による損失回避 | 安全なデータ活用によるマーケティング施策の実現 |
| データ連携価値 | 産業・組織を超えたデータ活用 | より精度の高い顧客分析と予測マーケティング |
実際の成果:DX銘柄企業の株価上昇
興味深いことに、デジタルガバナンス・コードに沿った経営を行う「DX銘柄」選定企業の株価は、日経平均株価を上回る成長を示しています。これは、DXへの取り組みが実際に市場から評価されていることを示す重要な証拠です。
DX経営に求められる3つの視点を理解する
デジタルガバナンス・コード3.0の大きな特徴の一つが、「DX経営に求められる3つの視点」の導入です。これらの視点は、全ての施策を貫く基本的な考え方として位置づけられています。
視点1:経営ビジョンとDX戦略の連動
最初の視点は、DX戦略を経営ビジョンと切り離して考えてはいけないというものです。多くの企業で見られる「とりあえずDXをやってみよう」という approach では、真の価値創造は実現できません。
具体的に求められること:
- 経営陣がDX戦略の策定を主導する
- 経営ビジョンとDX戦略の関連性を明確にする
- デジタル課題に対する具体的なアクションとKPIを設定する
マーケターとしての活用ポイント: 例えば、あなたの会社の経営ビジョンが「顧客との深いつながりを通じた価値創造」だとしたら、マーケティングのDX戦略も「顧客との関係性強化」を軸に据える必要があります。単なる広告配信の自動化ではなく、顧客理解の深化や個別最適化されたコミュニケーションの実現を目指すべきです。
視点2:As is - To be ギャップの定量把握・見直し
二つ目の視点は、現状と理想のギャップを数値で把握し、継続的に見直すことです。感覚的な判断ではなく、データに基づいた客観的な評価が求められます。
実践的なアプローチ:
- 現在の状況(As is)を具体的な指標で測定する
- 目指すべき姿(To be)を明確な数値目標として設定する
- 定期的にギャップを測定し、戦略を見直す
マーケティング領域での適用例:
| 項目 | As is(現状) | To be(目標) | 測定指標 |
|---|---|---|---|
| 顧客理解度 | 基本属性のみ把握 | 行動・嗜好まで把握 | データポイント数、予測精度 |
| パーソナライゼーション | 一律配信 | 個別最適化 | エンゲージメント率、コンバージョン率 |
| 意思決定速度 | 月次レポート待ち | リアルタイム判断 | 意思決定にかかる時間 |
視点3:企業文化への定着
三つ目の視点は、DXを一過性の取り組みで終わらせず、企業文化として定着させることです。これは技術導入よりもむしろ難しい課題かもしれません。
文化定着のための要素:
- DX戦略策定段階から目指す企業文化を明確にする
- 全社員がデジタル技術を自然に活用できる環境を整備する
- 継続的な学習と改善のマインドセットを醸成する
DX経営を支える5つの柱:実践的解説
デジタルガバナンス・コード3.0では、DX経営を実現するための「5つの柱」が定められています。これらは相互に関連し合いながら、包括的なDX推進を支える構造となっています。
柱1:経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
最初の柱は、DXを前提とした経営ビジョンとビジネスモデルの策定です。ここで重要なのは、デジタル技術がもたらす変化を「リスク」と「機会」の両面から捉えることです。
基本的事項:
- データ活用・デジタル技術の進化による影響を踏まえた経営ビジョンの策定
- 経営ビジョン実現に向けたビジネスモデルの明確化
- これらの方向性の公表
望ましい方向性として挙げられている先進的な取り組み:
| 取り組み | 内容 | マーケティングへの示唆 |
|---|---|---|
| 既存ビジネスモデルの強化 | DX戦略による既存事業の深化 | 既存顧客との関係性をデジタルで強化 |
| 企業間連携の推進 | データ共有による価値創造 | 他社との連携マーケティングの可能性 |
| 社会課題解決への貢献 | 業界全体のDX牽引 | 社会価値と経済価値の両立 |
| グローバル対応力 | 迅速な市場変化への対応 | 多市場での一貫したブランド体験 |
柱2:DX戦略の策定
二つ目の柱は、経営ビジョン実現のための具体的なDX戦略策定です。ここでは特に「データを重要な資産」として認識することが強調されています。
データ活用における重要な観点:
- データの発掘・整理・管理能力の向上:散在するデータを統合し、活用可能な形に整備する
- データに基づく意思決定の実践:経営陣が実際にデータを活用して判断を行う
- データ連携とガバナンスの確立:他社とのデータ連携を法令遵守の下で実施する
マーケターが注目すべきDX戦略の要素:
既存ビジネス変革の取り組みとして、顧客関係やマーケティングの変革が明示的に挙げられています。これは、マーケティング部門がDX戦略の中核を担うことを意味しています。
具体的には以下のような変革が求められます:
- 顧客接点のデジタル化とデータ収集の強化
- マーケティングプロセスの自動化と最適化
- 顧客満足度向上のための新たなサービス創出
柱3:DX戦略の推進
三つ目の柱は、策定したDX戦略を実際に推進するための体制づくりです。これは「3-1.組織づくり」「3-2.デジタル人材の育成・確保」「3-3.ITシステム・サイバーセキュリティ」の3つのサブカテゴリーに分かれています。
3-1.組織づくり
DX推進のための組織づくりでは、組織横断的な取り組みが重視されています。従来のIT部門主導ではなく、事業部門を巻き込んだ全社的な推進体制が求められます。
重要な役職と責任:
| 役職 | 英語名 | 主な責任 |
|---|---|---|
| デジタル責任者 | Chief Digital Officer (CDO) | DX推進の統括 |
| 技術責任者 | Chief Technology Officer (CTO) | 技術戦略の統括 |
| 情報責任者 | Chief Information Officer (CIO) | IT基盤の統括 |
| データ責任者 | Chief Data Officer (CDO) | データ活用の統括 |
組織文化変革の重要性: 単に組織図を変更するだけでは不十分です。「新しい挑戦を促す制度」や「継続的な挑戦マインドの醸成」といった文化的な変革も同時に進める必要があります。
3-2.デジタル人材の育成・確保
デジタル人材の不足は、多くの企業が直面する深刻な課題です。デジタルガバナンス・コード3.0では、デジタルスキル標準を参照した社員のスキル可視化が新たに強調されています。
人材育成の具体的アプローチ:
- 経営者・管理職の意識改革:トップダウンでのデジタル人材育成推進
- 全社員のデジタルリテラシー向上:リスキリング・リカレント教育の仕組み整備
- 専門人材の確保:育成・採用・外部活用の組み合わせ
- キャリア形成支援:自律的なスキル向上を支援する制度
マーケターにとって重要なスキル領域: マーケティング分野では、特に以下のスキルが重要になります:
- データ分析・解釈能力
- マーケティングオートメーションツールの活用
- 顧客体験設計(UX/CX)
- デジタル広告・SNSマーケティング
- AIツールの業務活用
3-3.ITシステム・サイバーセキュリティ
DX推進の基盤となるITシステムの整備と、それを守るサイバーセキュリティ対策は、もはや技術部門だけの課題ではありません。
ITシステムに関する重要な観点:
- 技術的負債の解消:レガシーシステムがDXの足かせとならないよう計画的に更新
- 全社最適の追求:部門個別最適ではなく、全社的なデータ整合性を確保
- 新技術との連携性:既存システムと新しいデジタル技術のスムーズな連携
サイバーセキュリティの経営課題化: 特に注目すべきは、サイバーセキュリティが「経営リスクの一つ」として明確に位置づけられていることです。
重要な対策として以下が挙げられています:
- CISO等の責任者任命と管理体制構築
- 第三者監査の実施
- サプライチェーン全体でのセキュリティ強化
- 事業継続計画(BCP)策定と演習実施
柱4:成果指標の設定・DX戦略の見直し
四つ目の柱は、DX戦略の効果を適切に測定し、継続的に改善していく仕組みです。ここでは、単なる活動指標ではなく、企業価値創造につながる成果指標の設定が求められます。
指標設定の3つのレベル:
| 指標の種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 企業価値創造指標 | 財務的な成果を示す指標 | 売上高、利益率、ROI |
| DX効果指標 | DX戦略の直接的な効果 | 顧客満足度、プロセス効率化率 |
| DX進捗指標 | 計画の進捗状況 | システム導入率、人材育成完了率 |
取締役会の役割強化: 特に取締役会設置会社では、取締役会がDX戦略の監督機能を適切に果たすことが求められています。これには、取締役へのDX教育機会の提供も含まれます。
柱5:ステークホルダーとの対話
最後の柱は、DXの取り組みを社外に向けて積極的に発信し、対話を行うことです。これは単なる情報開示を超えて、企業価値向上のためのコミュニケーション戦略として位置づけられています。
効果的な情報発信のポイント:
- 経営者自身の言葉でのメッセージ発信
- 価値創造ストーリーとしての統合的な説明
- 具体的な取り組みと成果の開示
- デジタル人材戦略の魅力的な発信
開示すべき情報の範囲:
| 開示内容 | 対象ステークホルダー | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 経営ビジョンとDX戦略 | 投資家、金融機関 | 投資判断の材料提供 |
| デジタル人材育成方針 | 求職者、従業員 | 優秀な人材の獲得・定着 |
| サイバーセキュリティ対策 | 取引先、顧客 | 信頼関係の構築 |
| 具体的成果とKPI | 全ステークホルダー | 透明性と説明責任の履行 |
マーケターが実践すべき具体的アクション
ここまでデジタルガバナンス・コード3.0の内容を詳しく見てきましたが、「では、マーケターとして何から始めればいいのか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。以下に、実践的なアクションプランをご提案します。
ステップ1:現状分析(As is の把握)
まずは、自社・自部門の現状を客観的に把握することから始めましょう。
チェックすべき項目:
- マーケティング活動でのデータ活用度
- 顧客との接点におけるデジタル化の進展度
- マーケティングツールの統合状況
- チーム内のデジタルスキルレベル
- セキュリティ対策の現状
ステップ2:経営ビジョンとの連動確認
自社の経営ビジョンやDX戦略を確認し、マーケティング活動との連動性を評価します。
確認すべき点:
- 会社のDX戦略にマーケティングの位置づけが明確か
- マーケティングKPIが企業価値指標と連動しているか
- 部門を超えたデータ連携ができているか
ステップ3:優先順位の設定
限られたリソースを効果的に活用するため、取り組みの優先順位を設定します。
優先順位設定の観点:
- 経営インパクトの大きさ
- 実現可能性
- 他部門との連携の必要性
- 投資対効果
ステップ4:継続的改善の仕組み構築
一度の取り組みで終わらせず、継続的に改善していく仕組みを作ります。
仕組みづくりのポイント:
- 定期的な成果測定とレビュー
- 最新デジタル技術動向のキャッチアップ
- 他社事例の研究と自社への応用検討
- ステークホルダーとの対話機会の創出
デジタルガバナンス・コード3.0の今後の影響
デジタルガバナンス・コード3.0は、単なるガイドラインを超えて、企業評価の重要な基準として機能していきます。
投資判断への影響拡大
すでにDX銘柄選定企業の株価が日経平均を上回る成長を示しているように、今後も投資家による評価基準として重要性が増していくでしょう。
人材獲得競争での差別化要因
デジタル人材の確保が困難になる中、デジタルガバナンス・コードに沿った人材戦略を明確に発信できる企業は、優秀な人材獲得で有利になると考えられます。
取引先選定の基準
サプライチェーン全体でのセキュリティ強化が重視される中、取引先企業の選定基準としてもデジタルガバナンス・コードへの対応状況が重要になってきます。
まとめ
デジタルガバナンス・コード3.0は、企業がDXを通じて真の価値創造を実現するための包括的なフレームワークです。マーケターとして押さえておくべき重要なポイントをまとめます。
Key Takeaways
- DX戦略は経営ビジョンと一体:マーケティング施策も全社的なDX戦略との連動が不可欠
- データは重要な経営資産:マーケティングデータの戦略的活用と適切なガバナンスが求められる
- 組織横断的な取り組みが必要:IT部門だけでなく、事業部門を巻き込んだDX推進が重要
- 継続的なスキル向上:デジタルスキル標準を参考にした計画的な人材育成が必要
- セキュリティは経営課題:マーケティング活動でもサイバーセキュリティ対策の意識が必要
- 成果指標の適切な設定:活動指標だけでなく、企業価値につながる成果指標の設定が重要
- ステークホルダーとの積極的対話:DXの取り組みを社外に向けて発信することで企業価値向上につなげる
デジタルガバナンス・コード3.0は、DXを「コスト」ではなく「価値創造のための投資」として捉える重要性を示しています。マーケターの皆さんも、この視点を持って自身の業務を見直し、企業価値向上に貢献できるDXマーケティングを実践していきましょう。
参考URL: