はじめに:なぜ「顧客体験」が今、最重要なのか?
顧客体験(Customer Experience:CX)は、かつては「ブランド好感度」や「顧客満足度」を向上させるソフトな概念と捉えられていました。しかし、現代の顧客はこれまで以上に情報感度が高く、選択肢も豊富なため、CXの優劣が直接的に売上に跳ね返る時代です。つまり、CXはもはや「あると良いもの」ではなく、経営戦略の中心に据えるべきコアテーマとなっているのです。
PwCが世界12カ国・15,000人を対象に実施した本調査は、その実態を定量データで明らかにしています。この記事では、そのデータを読み解きつつ、CXがビジネス成果に与えるインパクト、現場での改善策、組織設計に至るまで幅広く解説します。
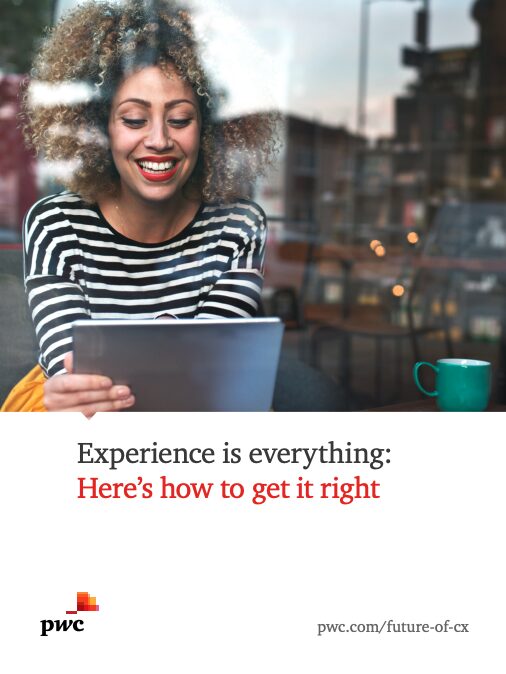
顧客体験の本質:求められているのは「速さ・便利さ・人間味」
PwCの調査によると、消費者が企業に対して求めている体験の特徴は明確です。特に「速さ」「便利さ」「フレンドリーさ」という3つのキーワードが挙げられます。これらは、単に商品やサービスの機能的価値ではなく、接点における「心理的・感情的価値」を重視していることを意味します。
顧客が求めるもの(図表抜粋)
| 要素 | 重視度(米国) | 支払意思あり(%) |
|---|---|---|
| スピード | 非常に高い | 43% |
| 便利さ | 非常に高い | 42% |
| フレンドリーな対応 | 非常に高い | 42% |
| 知識のあるスタッフ | 非常に高い | — |
| 一貫した体験 | 高い | — |
さらに注目すべきは、「これらの体験に対して価格を上乗せしてもよい」と考える人が40%以上も存在することです。これは、CXが単なる満足度向上施策ではなく、「単価向上の鍵」として活用できることを意味します。たとえば、スターバックスのように高単価でも体験価値で選ばれるブランドは、その成功の多くをCXに依存しています。
たった1回の失敗で顧客は離れる
CXの本質を理解するうえで、次の統計データは非常に示唆に富んでいます:
- 32%の米国消費者は、「たった1回の悪い体験でそのブランドを見限る」と回答。
- ラテンアメリカではその割合が49%に達し、いっそうシビア。
- 59%は「数回の悪体験で離脱」する傾向がある。
この数字は「一度や二度の失敗は許される」という従来のビジネス前提がもはや通用しないことを意味しています。SNSやレビューサイトが発達した現代では、失敗が即座にブランド毀損につながるため、CXはリスクマネジメントの観点からも極めて重要です。
また、顧客が「何に」失望しているのかを把握するには、定性的なインタビューだけでなく、NPS(ネット・プロモーター・スコア)やCES(顧客努力指標)などを組み合わせた定量分析も欠かせません。
CX向上が生む成果:価格プレミアムとロイヤルティの向上
CXの改善は、ブランドへの好感度向上だけではなく、「売上単価」「継続率」「LTV(ライフタイムバリュー)」に明確なインパクトをもたらします。
米国におけるCXによる価格プレミアム(PwC調査)
| 商品・サービス | CXが良い場合の価格プレミアム |
|---|---|
| コーヒー | +16% |
| ホテル宿泊 | +14% |
| 健康診断 | +14% |
| ディナー | +12% |
| 航空券 | +10% |
「価格ではなく体験で選ばれる時代」という言葉が現実になっていることが分かります。サブスクリプションビジネス、リテール、BtoBサービスなど、あらゆる業種でCXに投資する企業が増えているのは、このような数値による裏付けがあるからです。
「テクノロジーだけ」ではCXは改善しない
AIやチャットボット、セルフレジ、アプリなど、企業は多くのテクノロジーを導入しています。しかしPwCのレポートは明確に「テクノロジーだけでは顧客満足は得られない」と警鐘を鳴らします。
たとえば、以下のような実態があります:
- 自動化された対応よりも、「親切で共感のある有人対応」を好む人が多数
- 実際、71%の米国消費者は人間とのやり取りを希望
これは、どんなに便利でも「冷たさ」や「押しつけられた体験」には不満を感じるという、心理的バリアが存在することを示しています。
マーケターが設計すべきなのは、テクノロジーと人間性が融合した“バランスの良いCX”です。
組織視点で考えるCX:従業員体験(EX)との相関
優れたCXを実現するには、現場で顧客と接する従業員の体験(EX:Employee Experience)が高い水準でなければなりません。
たとえば、以下のような状況を想像してください:
- 十分な教育やマニュアルがなく、スタッフが困惑している
- 顧客に裁量ある提案ができないほど、内部ルールが厳しい
- KPIが数量的目標に偏り、行動が制約されている
これでは、CXどころかブランドへの信頼を損ねてしまいます。
PwCが提案するCX改善の方程式:
つまり、従業員満足なくして顧客満足なし。これは多くのトップブランドが共通して重視している原則です。
実践ポイント:マーケターが今すぐ取り組むべきこと
CX向上には大掛かりな投資やシステム開発が必要と思われがちですが、実際には「今すぐできること」が多くあります。
| 項目 | 具体アクション例 |
|---|---|
| EX(従業員体験)の強化 | ナレッジの見える化、提案の自由度向上、オペレーション簡素化 |
| 人間味のある設計 | チャット→人間切替のタイミング最適化、共感的トーンスクリプトの設計 |
| 顧客接点のデジタル化 | FAQと有人チャットのハイブリッド、LINE・Instagram連携 |
| パーソナライズ対応 | 行動ログに基づくレコメンド、セグメント別メール配信、シナリオ設計 |
さらに進んだ企業では、カスタマージャーニーマップの定期更新やCXをKPIとして経営陣にレポートする体制も整備されています。
まとめ:顧客体験を“経営の中心”に据えよ
今回ご紹介したPwCのレポートから分かるように、CXは「戦術的な改善」ではなく、「構造的な経営課題の解決策」として捉えるべきテーマです。
特に以下のような要素を見直すことが、CXの飛躍的改善につながります:
- CX向上のKPI化と可視化(NPSやLTVのモニタリング)
- エンド・ツー・エンドのジャーニー設計
- CX責任者(Chief Experience Officer)の設置
Key Takeaways
- 顧客は機能ではなく「体験」にお金を払う
- CXが悪いと1回で離脱される時代
- テクノロジーだけでなく、人間性と融合した設計が不可欠
- 社員の満足度(EX)とCXは連動している
- CX改善は、収益性・ブランド価値・競争力の向上につながる
CXの強化は短期的な施策ではなく、長期的な信頼と持続的成長のための投資です。あなたのブランドが「選ばれ続ける存在」であり続けるために、今日からCXを見直してみませんか?
レポート全文や業種別のデータをご覧になりたい方は、PwC公式サイトをご確認ください。



