はじめに
三菱重工業が2025年度第2四半期の決算を発表しました。受注高は前年同期比9%増の3.3兆円、売上収益は7%増の2.1兆円と堅調な数字が並んでいます。しかし、この数字の背景には何があるのでしょうか。単なる市場の追い風なのか、それとも構造的な競争優位性に基づく「本物の成長」なのか。今回の決算資料を深掘りすることで、B2Bビジネス、特に大型プラント・インフラ事業における「選ばれ続ける企業」の条件が見えてきます。
会社概要
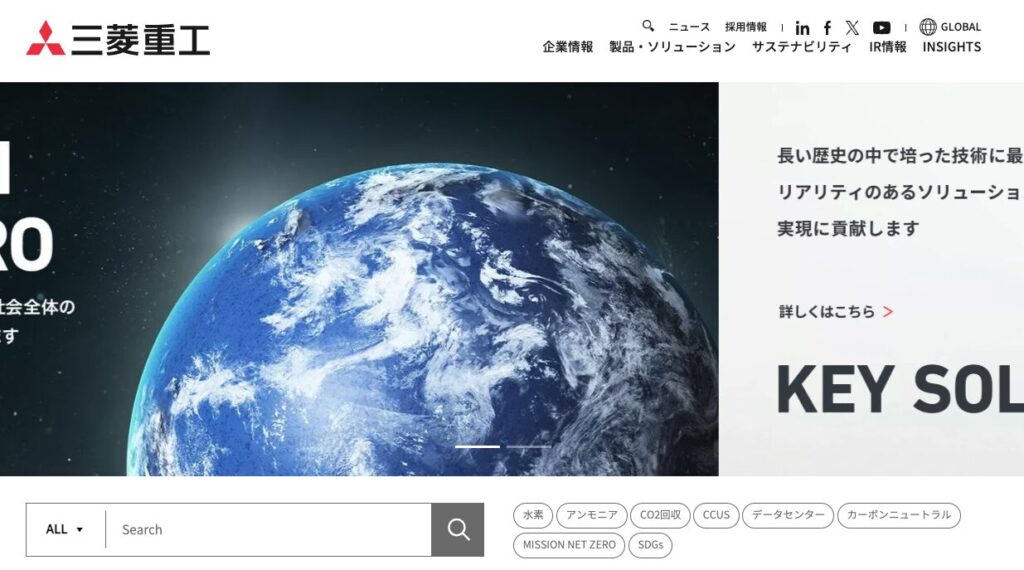
三菱重工業は、発電設備、航空機、防衛装備品、産業機械など幅広い重工業製品を手がける日本を代表する総合機械メーカーです。現在は以下の4つの主要セグメントで事業を展開しています。
エナジー: ガスタービン複合発電(GTCC)、火力発電設備、原子力、航空転用エンジンなど
プラント・インフラ: 製鉄機械、機械システム、エンジニアリング、環境設備など
物流・冷熱・ドライブシステム: 舶用エンジン、ターボチャージャ、空調機器など
航空・防衛・宇宙: 防衛装備品、民間航空機部品、宇宙関連機器など

注目すべきは、2025年9月30日に三菱ロジスネクスト(フォークリフト事業)の非公開化を決定したことです。このため、今回の決算から同社を「非継続事業」として区分し、継続事業のみで業績を開示する形式に変更しています。
業績
2025年度第2四半期(累計)の実績
| 項目 | FY24-2Q<br>(除くML) | FY25-2Q | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 受注高 | 3.05兆円 | 3.31兆円 | +9% |
| 売上収益 | 1.97兆円 | 2.11兆円 | +7% |
| 事業利益 | 1,680億円 | 1,715億円 | +2% |
| 事業利益率 | 8.5% | 8.1% | △0.4pt |
| 当期利益 | 1,071億円 | 1,149億円 | +7% |
| EBITDA | 2,241億円 | 2,296億円 | +3% |
セグメント別の動き
| セグメント | 受注高 前年比 | 売上収益 前年比 | 事業利益 前年比 |
|---|---|---|---|
| エナジー | +52% | +5% | △22% |
| プラント・インフラ | △18% | +10% | +58% |
| 物流・冷熱・ドライブ | △11% | △7% | +23% |
| 航空・防衛・宇宙 | △32% | +25% | +37% |
通期見通し(2025年9月30日公表から修正)
| 項目 | 前回見通し | 今回見通し | 変更 |
|---|---|---|---|
| 受注高 | 5.25兆円 | 6.1兆円 | +8,500億円 |
| 売上収益 | 4.75兆円 | 4.8兆円 | +500億円 |
| 事業利益 | 3,900億円 | 3,900億円 | 変更なし |
成長の質を見極める
①この成長は続くのか?
結論から言えば、エナジーと航空・防衛・宇宙の2セグメントは構造的な成長が期待できます。一方、物流・冷熱・ドライブシステムは市場環境の影響を受けやすく、注意が必要です。
エナジーセグメントの実力
GTCCの受注高は前年同期比+84%の1.4兆円に達しました。これは世界的な脱炭素の流れの中で、石炭火力から天然ガス火力への転換が進んでいることが背景にあります。特に北米とアジアで受注が好調で、2025年2Qだけで23台の大型ガスタービンを受注しています。
注目すべきは、単なる「設備販売」ではなく、長期のメンテナンス契約(アフターサービス)がセットになっていることです。GTCCの売上AS(アフターサービス)比率は51%に達しており、設備を納入した後も継続的な収益が見込めます。これは典型的な「ストック型ビジネス」への転換であり、収益の安定性を高めています。
ただし、スチームパワー(火力発電)では南アフリカの工事で損失を計上するなど、一部に課題も残っています。エナジー全体の事業利益率は前年同期の12.4%から9.3%に低下しました。
航空・防衛・宇宙の構造的優位性
このセグメントの受注高は前年同期比で減少していますが、これは2023~2024年度に大型の防衛装備品開発案件が集中したためです。日本政府の防衛費増額により、2018~2022年度の平均受注高(約5,200億円)の2倍以上となる高水準が今後も続く見込みです。
民間航空機部品も、ボーイング787の出荷機数増加により増収増益を達成しました。航空機ビジネスは一度サプライチェーンに組み込まれると、機体の生涯にわたって部品供給が続くため、極めて参入障壁が高いビジネスモデルです。
一時的要因の影響
- 前年同期に計上された土地売却益(約220億円)のリバウンドがマイナス要因
- 火力発電の一部工事損失(約300億円、うち南アフリカ200億円)もマイナス要因
- 為替影響はプラス170億円(前年同期の差損のリバウンド)
これらを除くと、実力ベースでは事業利益は前年同期比で大幅増となっていた計算です。
②どのセグメント・地域に依存しているか?
セグメント別の売上構成
エナジー(41%)、航空・防衛・宇宙(25%)、プラント・インフラ(20%)、物流・冷熱・ドライブ(13%)という構成です。エナジーへの依存度が高いものの、各セグメントが異なる市場サイクルを持つため、リスク分散は一定程度できています。
地域別の売上構成
日本(43%)、米州(28%)、EMEA(13%)、アジア・パシフィック(16%)となっています。日本国内の防衛需要が大きいため日本比率が高いですが、エナジーでは米州とアジアが成長ドライバーとなっています。
特筆すべきは、米州での売上が前年同期比+27%の5,986億円に達したことです。これはGTCCの受注・売上が北米で好調なためです。
③短期と中長期でどう違うのか?
短期(2025年度下期)の見通し
通期の事業利益見通し3,900億円に対し、上期実績は1,715億円(進捗率44%)です。下期は約2,185億円を計画しており、上期を上回る収益が見込まれています。これは、大型プロジェクトの工事進捗が下期に集中することが理由です。
中長期(1~3年)のトレンド
- GTCCの受注残高は67台(前年同期比+31台)と積み上がっており、今後数年の売上が確保されています
- 防衛装備品は開発から量産に移行する案件が増えており、売上の増加トレンドが続く見込みです
- 民間航空機は787の生産レート向上により、2026年度以降も増収が期待できます
経済的な堀の観点
三菱重工の競争優位性は、技術力に加えて「乗り換えコスト」と「効率的な規模」にあります。一度GTCCを納入すれば、30年以上にわたるメンテナンス契約が続きます。防衛装備品も、自衛隊が採用した装備は数十年にわたり使用され、その間の保守・改修は納入メーカーが独占的に担います。
マーケティングの学び
学び①:「売り切り」から「継続課金」へのビジネスモデル転換
何が起きたか
エナジーセグメントのGTCC事業において、アフターサービス売上比率が51%に達しました。これは設備販売(初期売上)と同等以上のサービス収益が継続的に得られていることを意味します。
なぜそうなったか
GTCCのような大型発電設備は、稼働後の定期点検、部品交換、性能改善が不可欠です。発電事業者にとって、設備の停止は大きな損失につながるため、信頼できるメーカーとの長期契約が合理的な選択となります。三菱重工はこの「顧客の課題」に着目し、30年間の包括メンテナンス契約をセットで提案しています。
どんな打ち手があったか
- 設備納入時に長期サービス契約を標準パッケージ化
- IoT技術を活用した遠隔監視システムの導入により、予防保全を高度化
- グローバルなサービス拠点網の整備により、迅速な対応を実現
自社に活かせることは何か
B2B企業は「製品販売」から「ソリューション提供」へのシフトを常に意識すべきです。初期売上だけでなく、使用後のサポート、データ分析、継続的な改善提案などを組み込むことで、顧客との関係性を長期化し、安定収益を確保できます。これはSaaS型ビジネスと同じ発想です。
学び②:参入障壁の高い市場でのポジショニング戦略
何が起きたか
航空・防衛・宇宙セグメントが売上+25%、事業利益+37%と大幅な成長を達成しました。特に防衛装備品の受注残高は3.5兆円を超え、今後数年の売上が確保されています。
なぜそうなったか
防衛装備品市場は、技術的難易度が高く、セキュリティ要件も厳しいため、新規参入が極めて困難です。また、一度採用されれば30年以上にわたって保守・改修を独占的に受注できます。日本政府の防衛費増額(2023年度以降)という追い風も重なり、既存プレイヤーである三菱重工に案件が集中しました。
どんな打ち手があったか
- 長年培った航空機技術を防衛分野に展開
- 政府の防衛力整備計画に沿った製品開発の提案
- 開発から量産、保守までの一貫体制の構築
自社に活かせることは何か
市場規模だけでなく「参入障壁の高さ」を重視した事業選択が重要です。特にB2B市場では、技術力、実績、規制対応力などが参入障壁となります。大企業が参入しにくいニッチ市場で高シェアを取ることも、中小企業にとって有効な戦略です(これは「効率的な規模」という経済的な堀に相当します)。
学び③:事業ポートフォリオの最適化による経営資源の集中
何が起きたか
三菱重工は三菱ロジスネクスト(フォークリフト事業)を非公開化し、コア事業への経営資源集中を決定しました。同時に、過去10年以上にわたり、工作機械、商業印刷機、リチウムイオン電池など、20以上の事業を売却・統合してきました。
なぜそうなったか
総合機械メーカーとして多様な事業を抱えていましたが、すべての事業で競争優位性を維持することは困難です。特に、フォークリフト事業は物流市場の変化が激しく、中国メーカーとの価格競争も厳しい状況でした。限られた経営資源(資金、人材、経営の時間)を、本当に競争力のある事業に集中投下する判断をしました。
どんな打ち手があったか
- 「戦略的事業評価制度」を2012年度から導入し、全事業を定期的に評価
- 収益性、成長性、競争優位性の3軸で事業を評価
- 「ベストオーナーシップ」の考え方により、他社に任せた方が伸びる事業は売却
自社に活かせることは何か
「やらないことを決める」ことの重要性です。多角化は一見リスク分散に見えますが、実際には経営資源の分散によって、どの事業も中途半端になるリスクがあります。定期的に事業ポートフォリオを見直し、本当に強みを発揮できる領域に集中することが、長期的な競争力につながります。
結論:成長は本物か?
判定:本物の成長と判断できるが、一部セグメントには注意が必要
三菱重工の成長は、GTCCと防衛・宇宙という2つの高収益事業が牽引しており、構造的な競争優位性に基づく「本物の成長」と評価できます。
経済的な堀の観点から見た強み
- 乗り換えコスト: GTCCのメンテナンス契約、防衛装備品の保守は、顧客が他社に切り替えることが極めて困難
- 無形資産(技術力・実績): 大型ガスタービン、航空機部品、防衛装備品は高度な技術と長年の実績が参入障壁
- 効率的な規模: 日本の防衛市場は限定的なため、大手企業でも参入メリットが少なく、既存プレイヤーが安定的に受注
ただし、注意すべきセグメントも
物流・冷熱・ドライブシステムは、市場環境(中国経済、自動車生産台数など)の影響を受けやすく、通期見通しも下方修正されました。このセグメントの事業利益率は3.3%と低く、構造的な課題を抱えています。
総合評価
受注残高11.5兆円、EBITDA2,296億円、営業キャッシュフロー2,079億円という数字は、短期的な一時要因ではなく、実力に基づく成長を示しています。特に、エナジーと航空・防衛・宇宙の2本柱が確立されつつあり、今後3~5年の成長トレンドは継続すると判断できます。
リスクと懸念
| リスク項目 | インパクト | 発生確率 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 火力発電の工事損失 | 大(300億円規模) | 中 | プロジェクト管理体制の強化、リスク分析の高度化 |
| 為替変動(円高) | 大 | 中 | ヘッジ取引、現地調達比率の向上 |
| 防衛費削減 | 大 | 低 | 民間航空機、エナジーなど他セグメントの強化 |
| 中国市場の減速 | 中 | 高 | 北米・アジア他地域へのシフト |
| 脱炭素規制の強化 | 中~大 | 中 | 水素・アンモニア混焼技術の開発、原子力事業の強化 |
| サプライチェーン混乱 | 中 | 中 | 複数ソース化、在庫最適化 |
まとめ
三菱重工の2025年度第2四半期決算から、マーケターが学べる実践的なヒントは以下の通りです。
一時的な施策ではなく、長期的な「経済的な堀」の構築に投資することで、持続的な競争優位性を確立できます。三菱重工はGTCCのアフターサービス契約や防衛装備品の保守ビジネスで、継続的な収益基盤を築いています。
売り切り型ビジネスから継続課金型ビジネスへのシフトは、B2B企業にとって最重要戦略です。製品だけでなく、データ、サービス、継続的な改善提案を組み合わせることで、顧客との関係を長期化できます。
参入障壁の高い市場を選ぶことも、競争戦略上は極めて重要です。市場規模よりも「守りやすさ」を重視した事業選択が、長期的な収益性につながります。
事業ポートフォリオの定期的な見直しと、コア事業への経営資源集中は、限られたリソースを最大限活用するための必須プロセスです。「やらないことを決める」勇気が、組織の競争力を高めます。
前四半期比での成長加速・減速を必ず確認し、通期見通しの根拠を理解することで、企業の実力を正しく評価できます。決算資料は単なる数字の羅列ではなく、企業戦略を読み解くための重要な情報源なのです。
経済的な堀: 三菱重工は「乗り換えコスト」「無形資産(技術力)」「効率的な規模」という3つの堀を組み合わせることで、長期的な競争優位性を確立しています。
あなたの会社にも、競合が簡単には真似できない「堀」がありますか?今日からその堀を意識的に深めていく戦略を考えてみてください。


